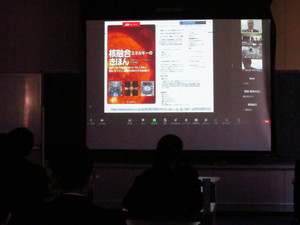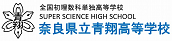高2 探究科学講演会(核融合について)
2月27日(木)、高校2年生を対象に、東京大学大学院名誉教授 小川雄一先生、東京工業大学科学技術創成研究院ゼロカーボンエネルギー研究所准教授 近藤正聡先生をオンラインでお招きして、核融合についての探究科学講演会を実施しました。小川先生からは、核融合反応とはどのようなものかについて教えていただきました。水素の原子核同士が融合する反応を核融合反応と呼び、核融合反応が起こると水素はヘリウムに変わります。その時、ほんの少しの質量が失われ、その分がエネルギーに変化します。このエネルギーを上手く取り出し、発電する技術が核融合発電です。この発電方法は、原子力発電とは異なり、核廃棄物はとても低レベルなものしか出ず、兵器転用も不可能で、また災害等で被害を受けた場合も発電が止まるだけで、深刻な放射能汚染は全く起きません。また、近藤先生からは核融合発電とエネルギー問題についてを教えていただきました。多次元貧困指数(MPI)という、その地域がどのくらい貧困であるかを表す指数を用い考えてみると、エネルギー消費量がある一定を下回ると生活がとても貧しくなることがわかります。エネルギーはあらゆる場所でできるだけ多く必要で、けれども環境のことを考えながら発電しなければなりません。これらを一度に解決出来うるのが核融合発電で、100gの質量を核融合で消費しただけで、東京ドーム21個分の水を沸騰させることができるそうです。そして、核融合発電に必要なリチウムは海水内に含まれ、なんと40億年分の発電をまかなえるそうで、持続可能なエネルギー資源としても期待されています。最後に先生はその一歩として、レーザー核融合を5年以内に実証したい、核融合の研究を引き継いでくれる次世代にも期待したいと話しておられました。今回の講演をきっかけに、将来にはこんな道もあるんだということを生徒達も知ることが出来たかと思います。小川先生、近藤先生、この度は本当にありがとうございました。