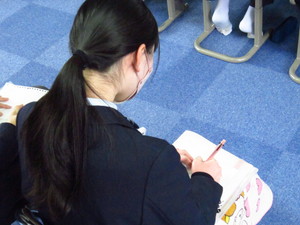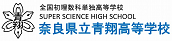高1 統合科学講演会(文理融合)
2月7日(金)の統合科学の授業で、奈良県立大学より尾久土正己(おきゅうどまさみ)学長先生をお招きし、高校1年生を対象に「新しい文理融合の学び~「宇宙と観光」を例に」と題して講演会を実施しました。複雑になっていく社会をより良くしていくためには、一つの分野の専門家では十分ではなく、文系、理系といった枠組みにとらわれず、様々な分野から総合知を得る必要がある、その例として尾久土先生自身が研究され、携わっておられるアストロツーリズムについてお話しいただきました。元々、宇宙物理学の研究者であった先生は、前任の和歌山大学で観光学部を立ち上げに参加され、観光学を教える立場になられた際に、観光とは、「日常の空間を離れて、非日常を体験する」ものであり、また宇宙は究極の非日常であることから、宇宙は観光資源として成り立つので、星空を観光資源にするために研究をすすめてこられました。星空が綺麗に見えるためには、照明器具の光が空に向かっていかないようにする必要があり、例えば、与論島では島民の方々に協力していただき、街灯などの角度を調整して夜空を守る取組をすすめられました。また、先生は与論島を観光名所にするべく、希望者を募り、与論島の方々がガイドとして星空を紹介できるようになるまで星空に関するレクチャーを重ねられました。そうした働きかけの中、与論島に残っていた星空に関する民謡を観光者に歌って紹介する方々もでてこられたそうです。結果的に、与論島の星空は、環境、経済、社会文化の3つ(トリプルボトムライン)のバランスのとれた持続可能な観光資源となりました。このようなことができたのは、宇宙に関する専門的な知識があったからで、観光学だけを志していたのであれば難しかったはずです。だからこそこれからは文理融合、つまり文系、理系の隔たりなく様々な分野に精通している必要があり、その能力が活かされる場面は、複雑化する社会の中でどんどん増えていくはずです。今回のお話しは、生徒達の将来を見据えた学びに、大きな影響を与えてくれたことと思います。尾久土先生、この度は本当にありがとうございました!