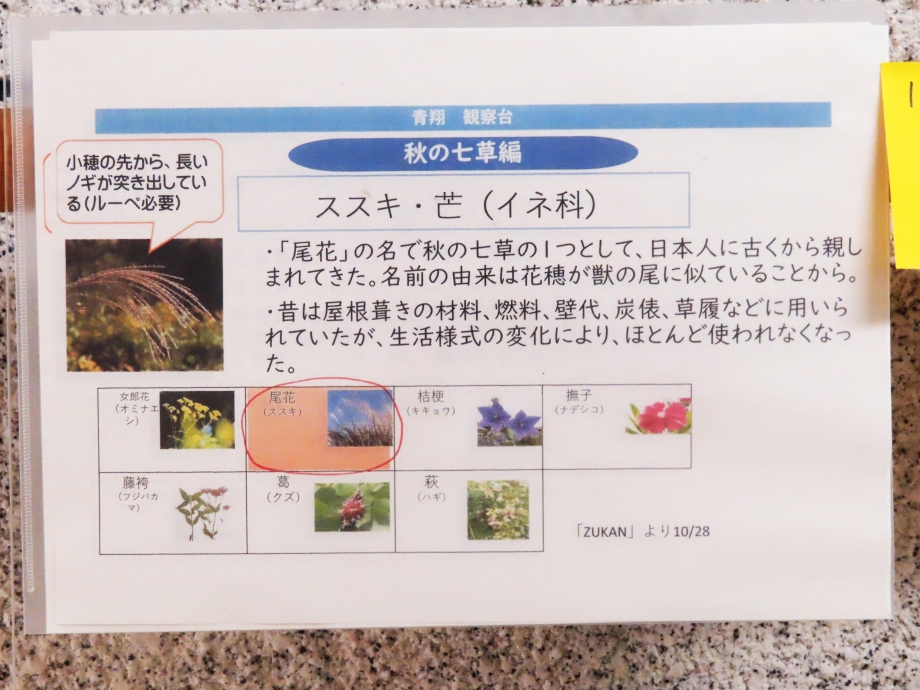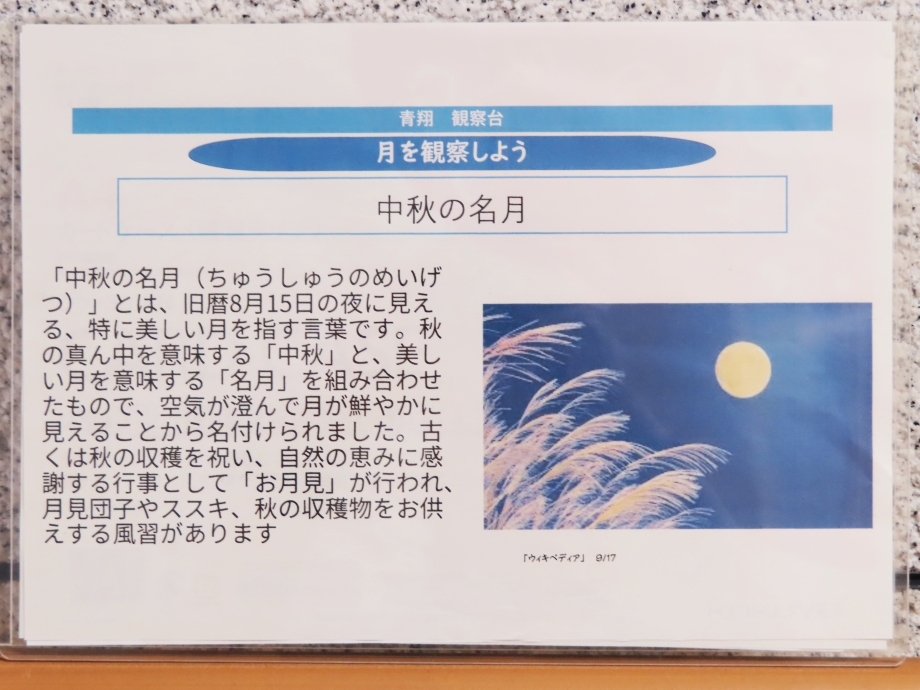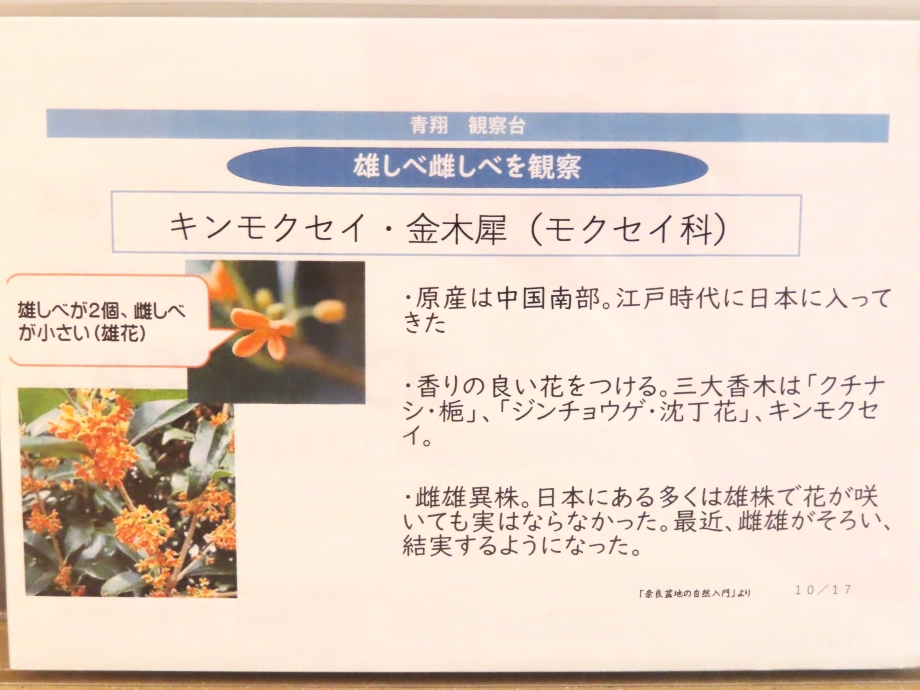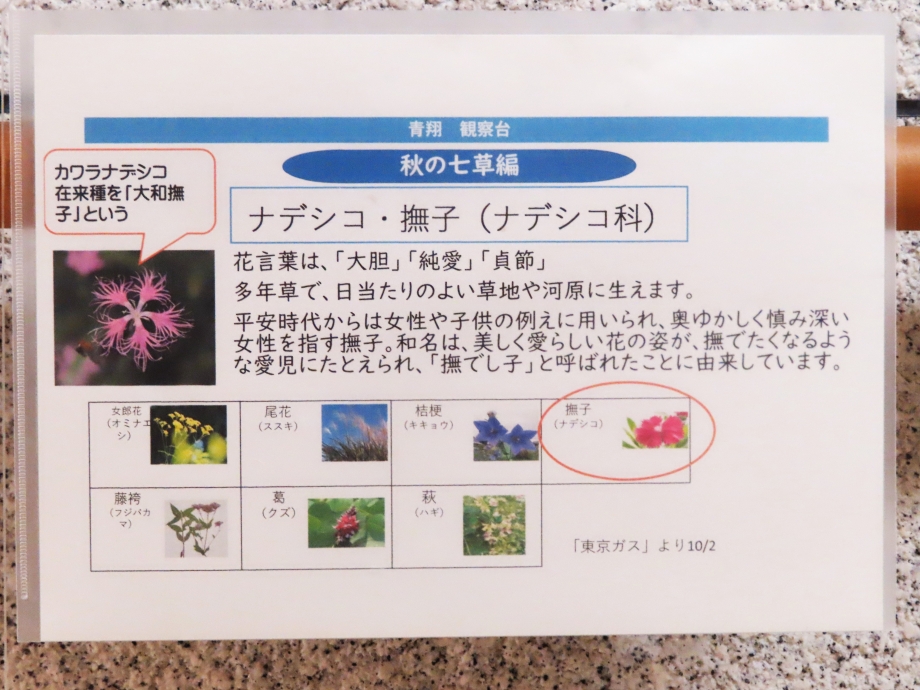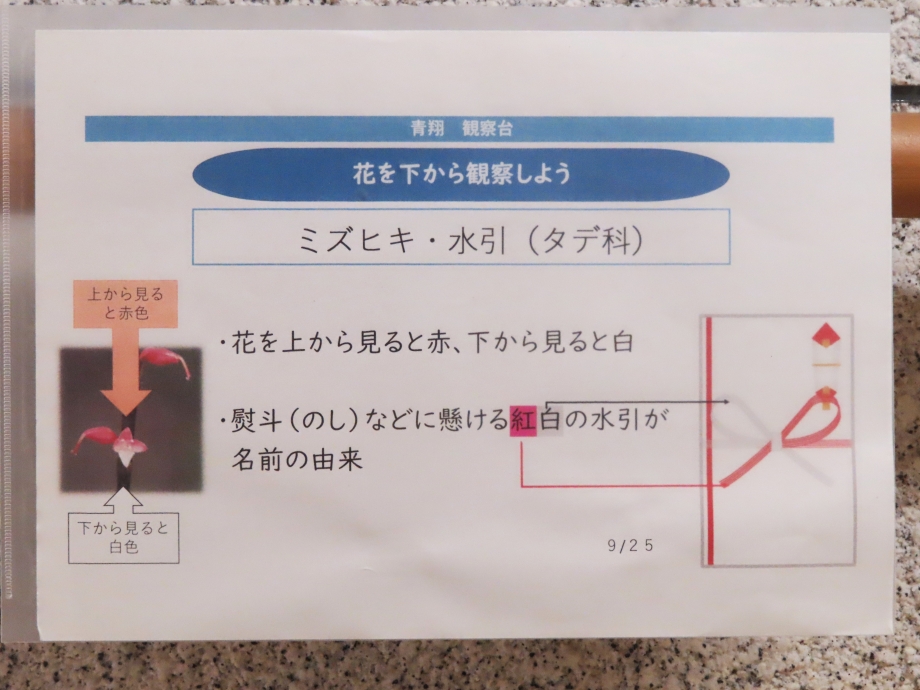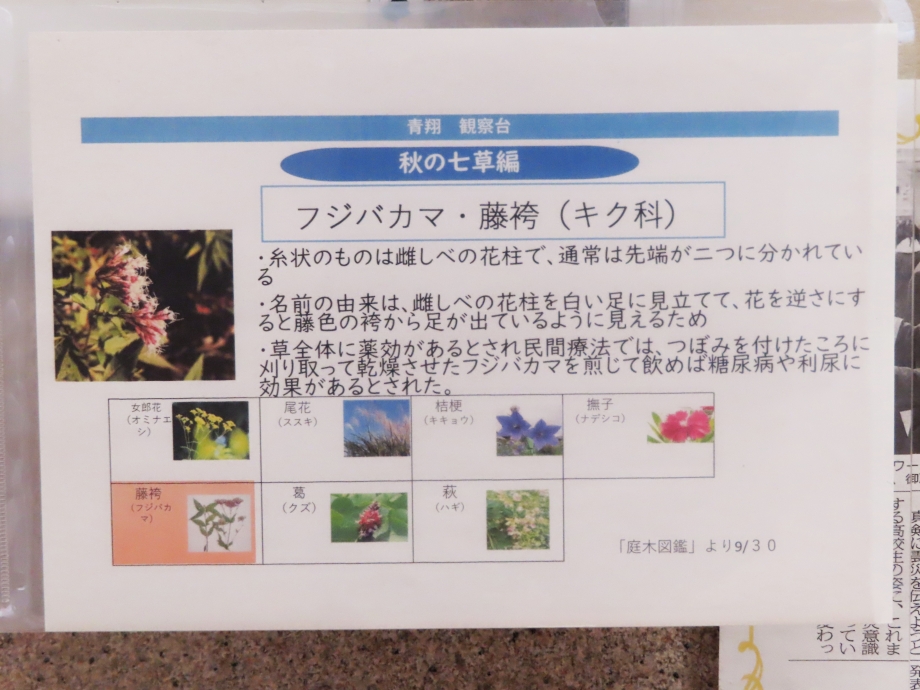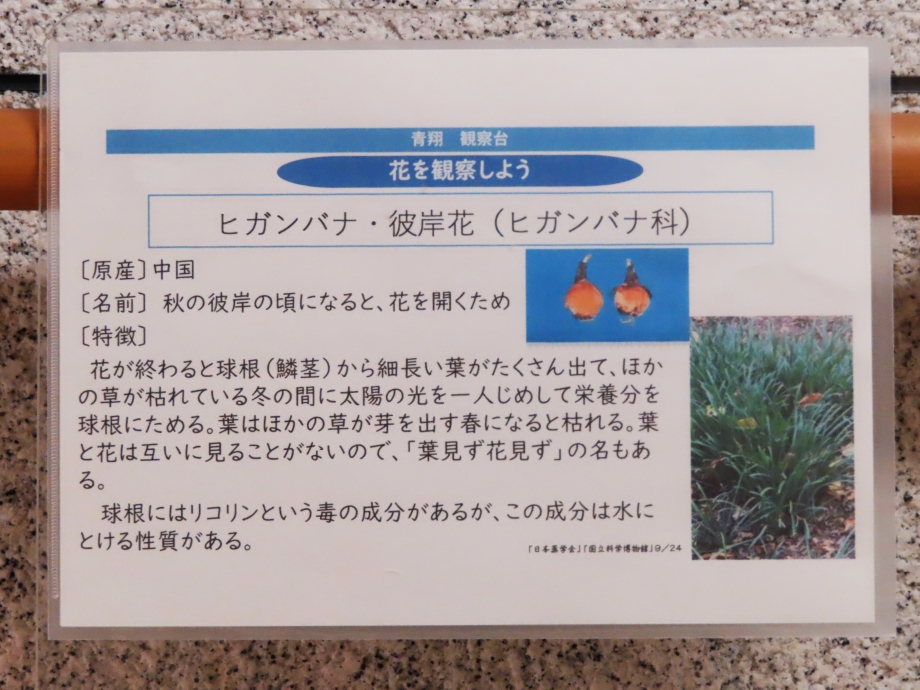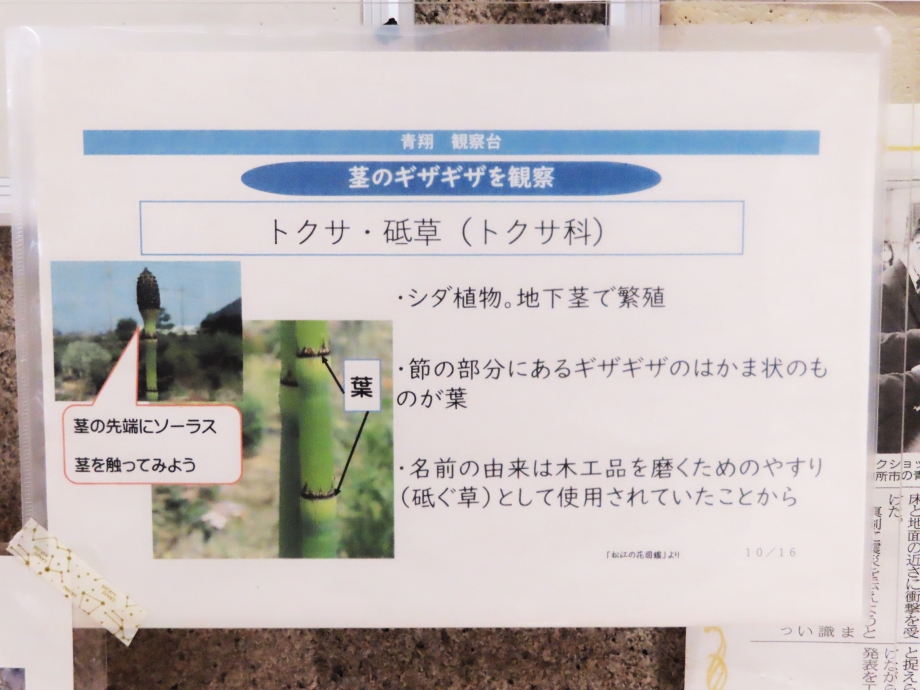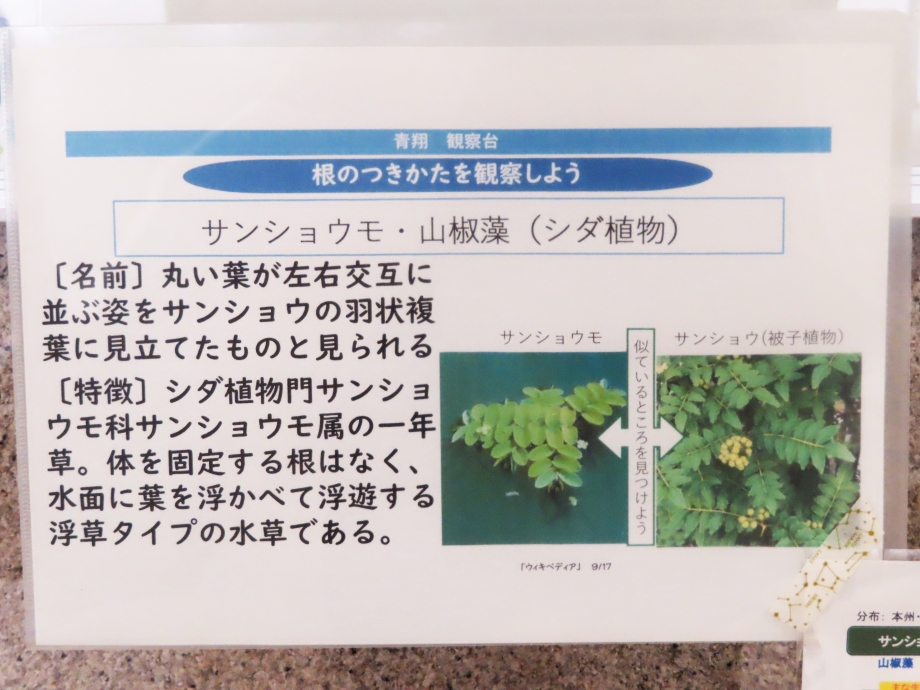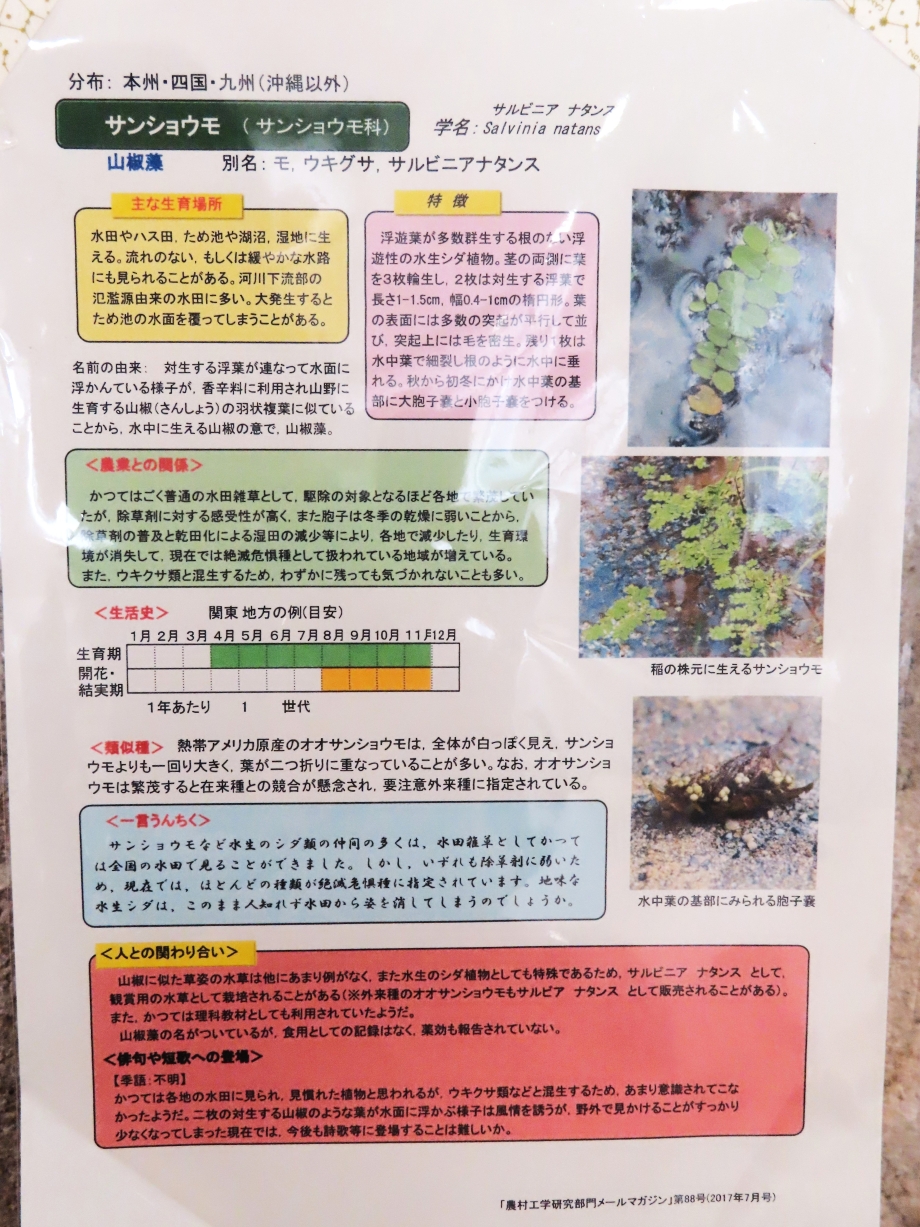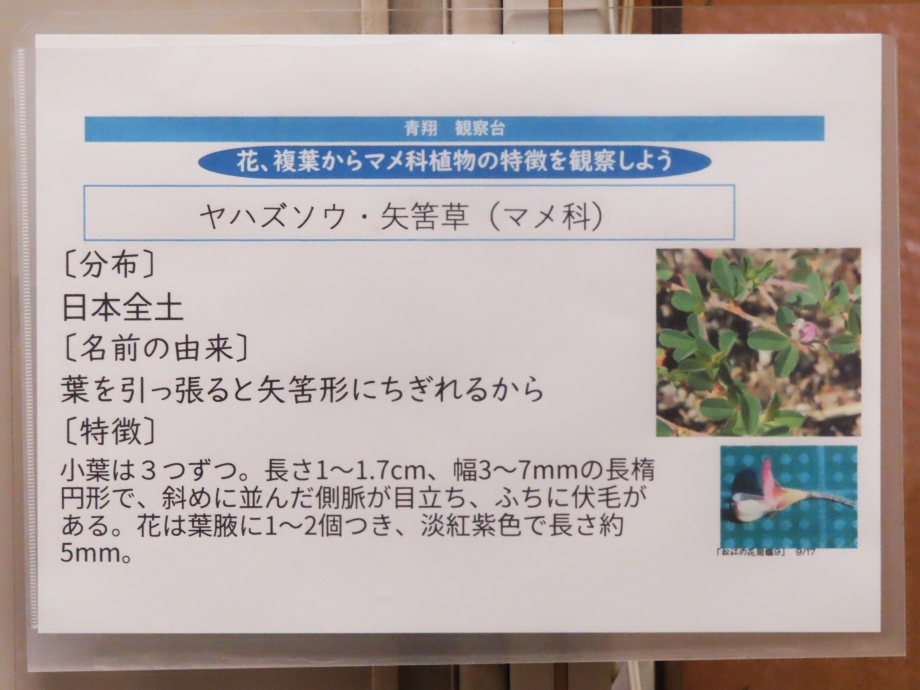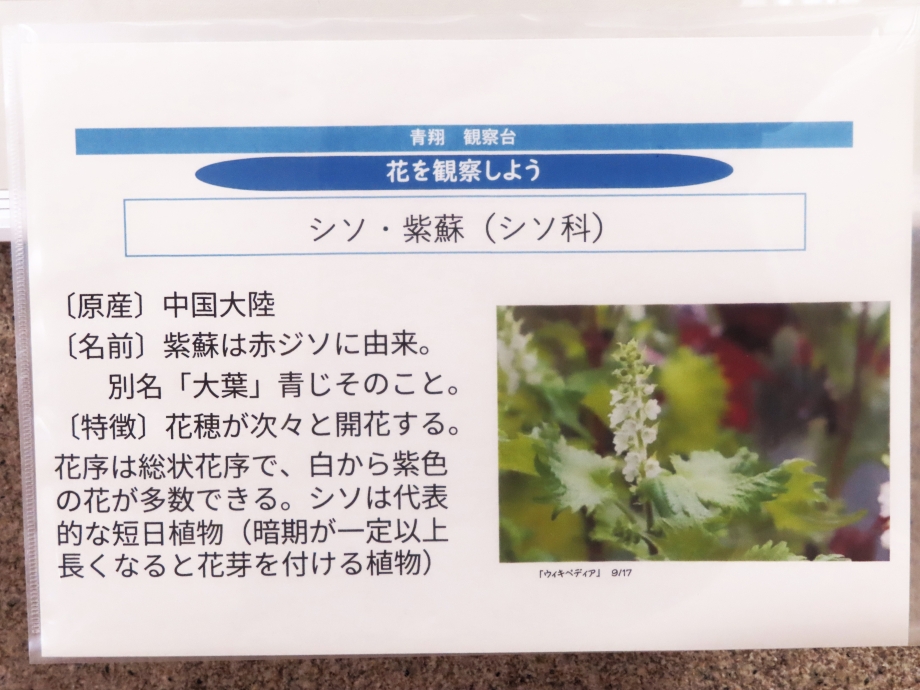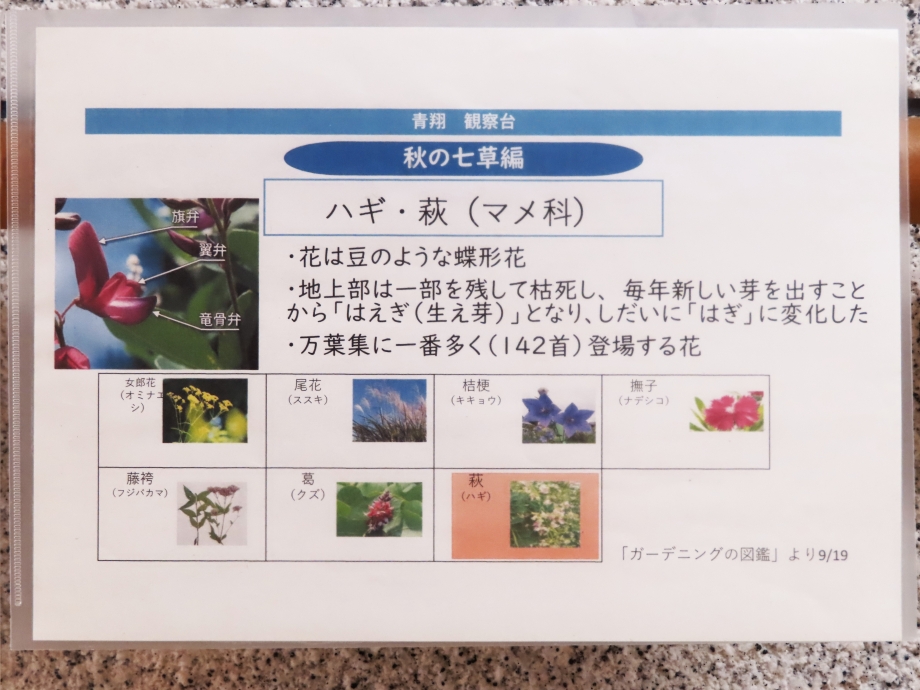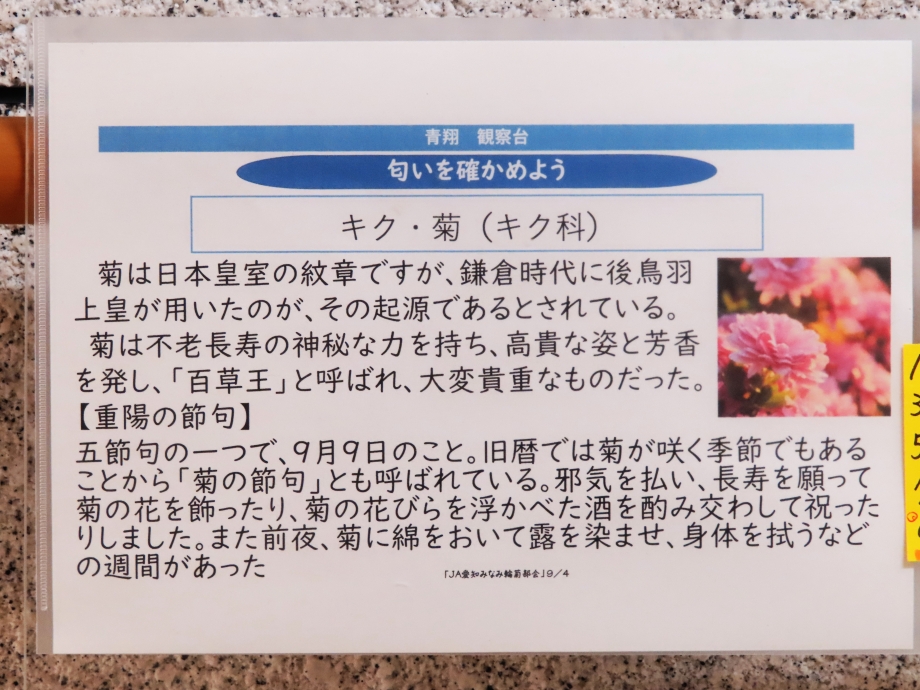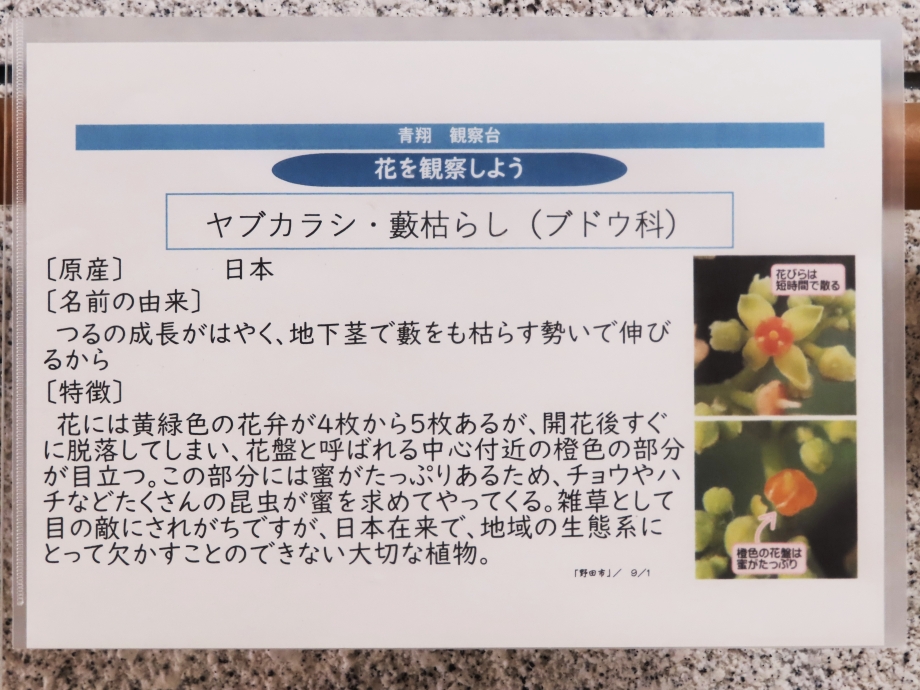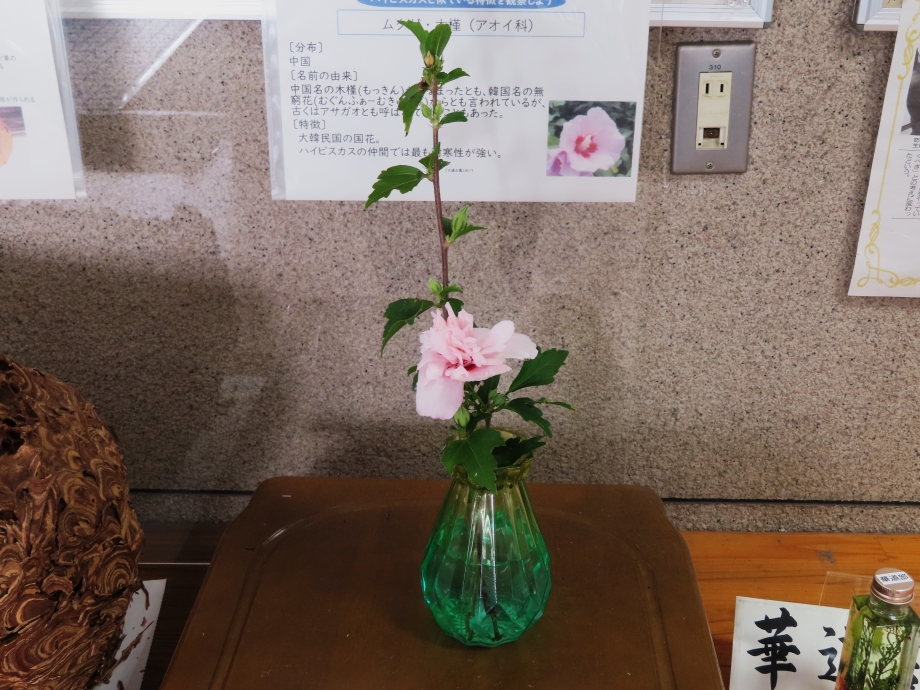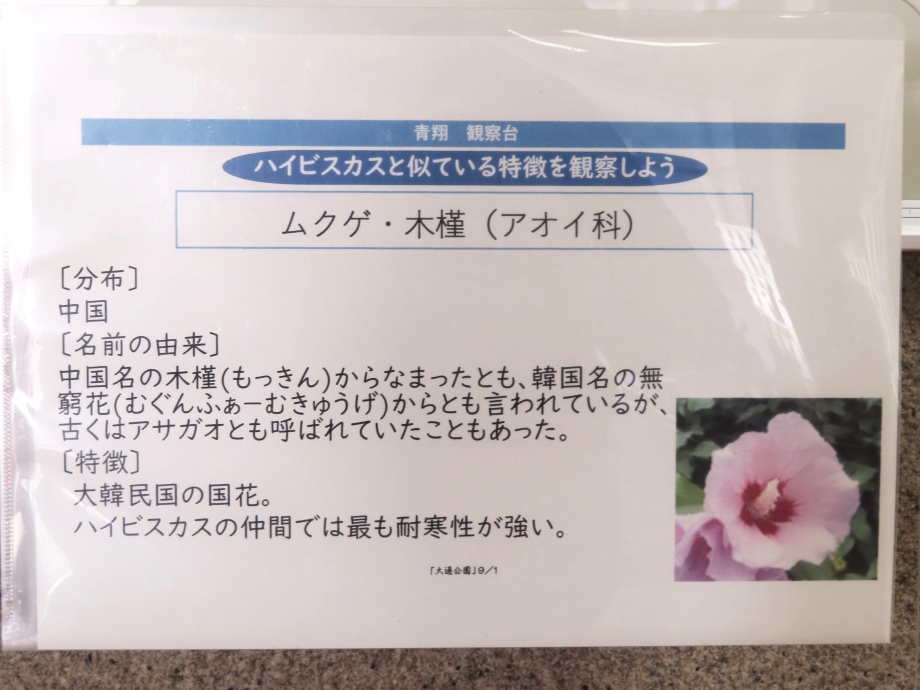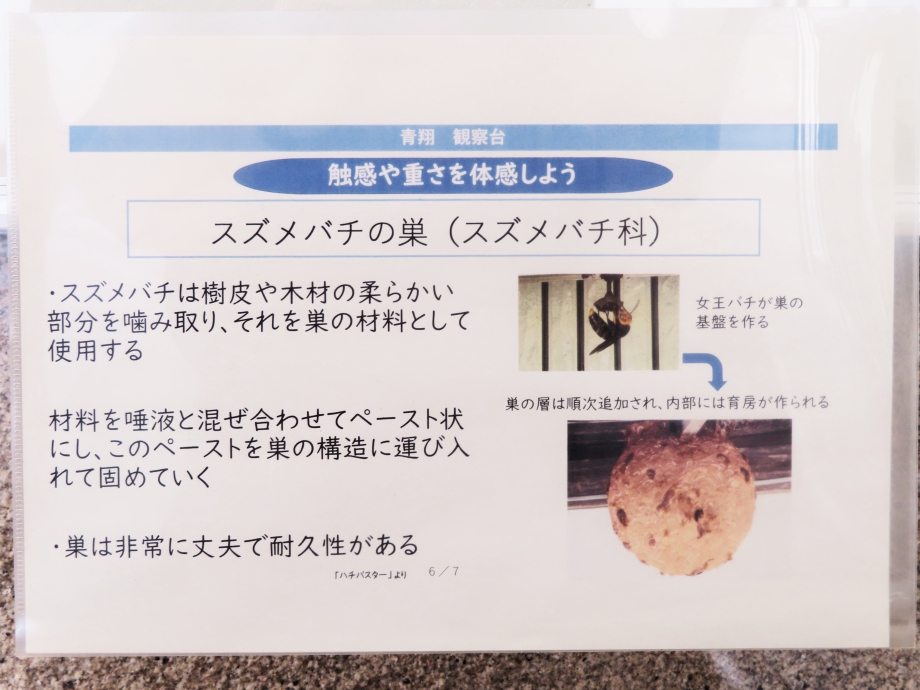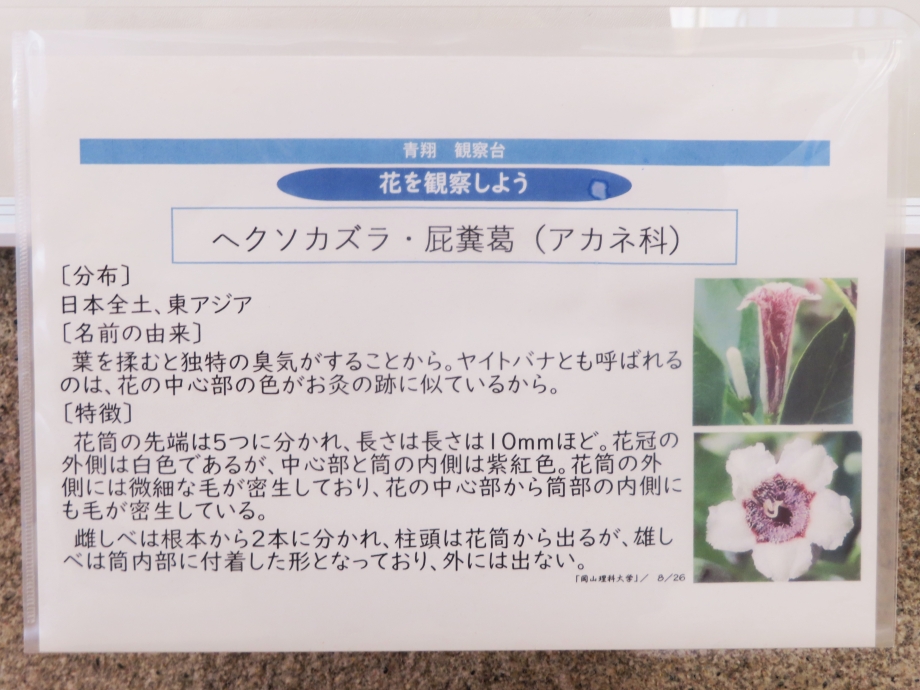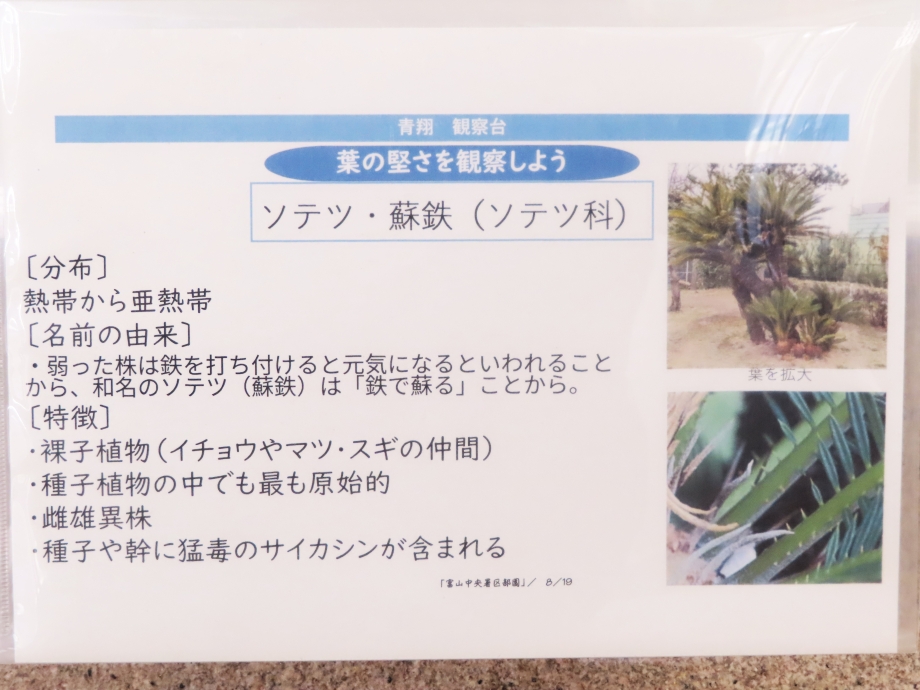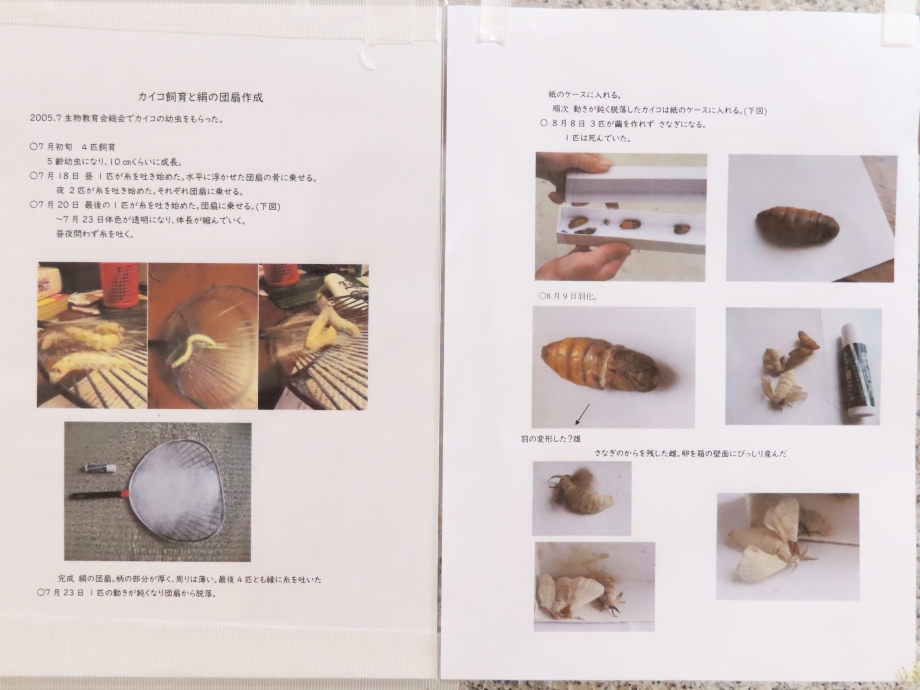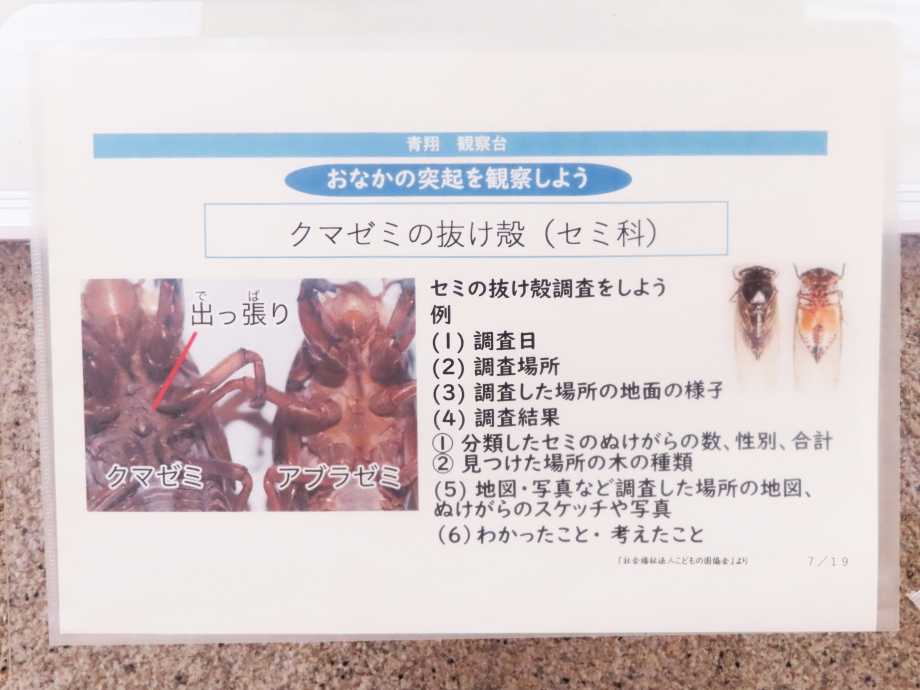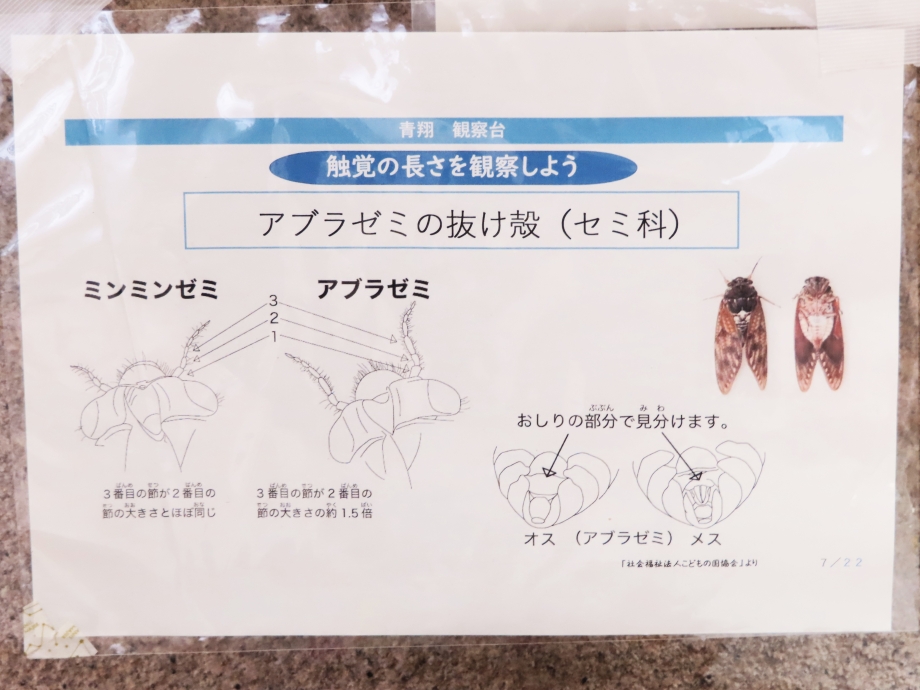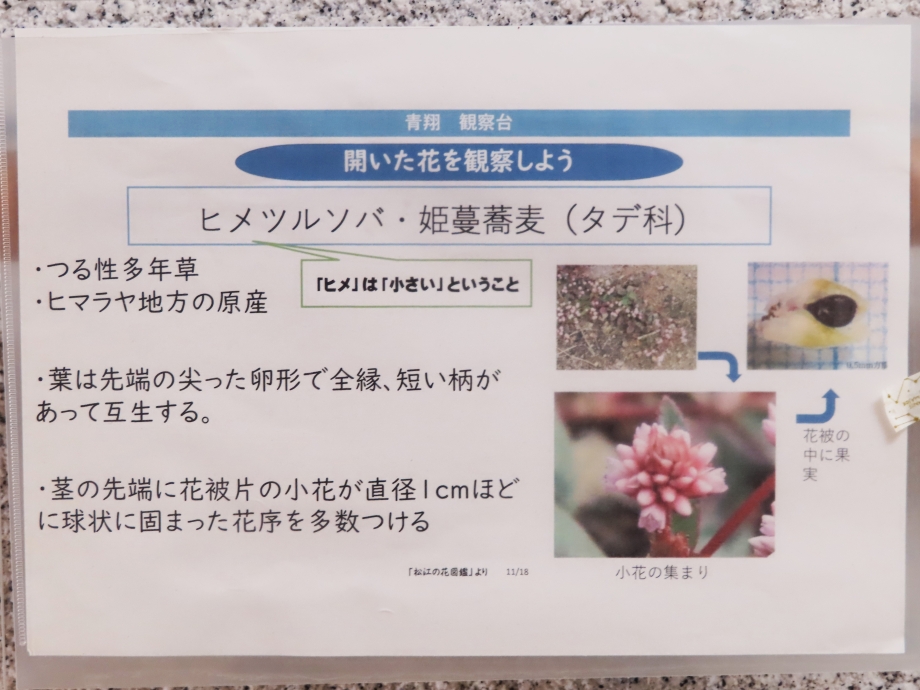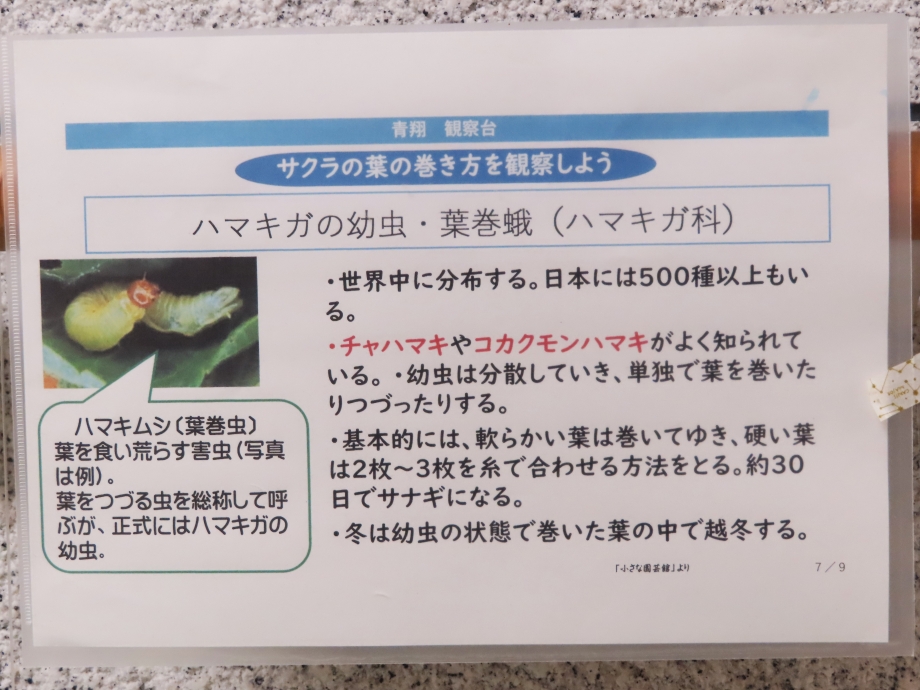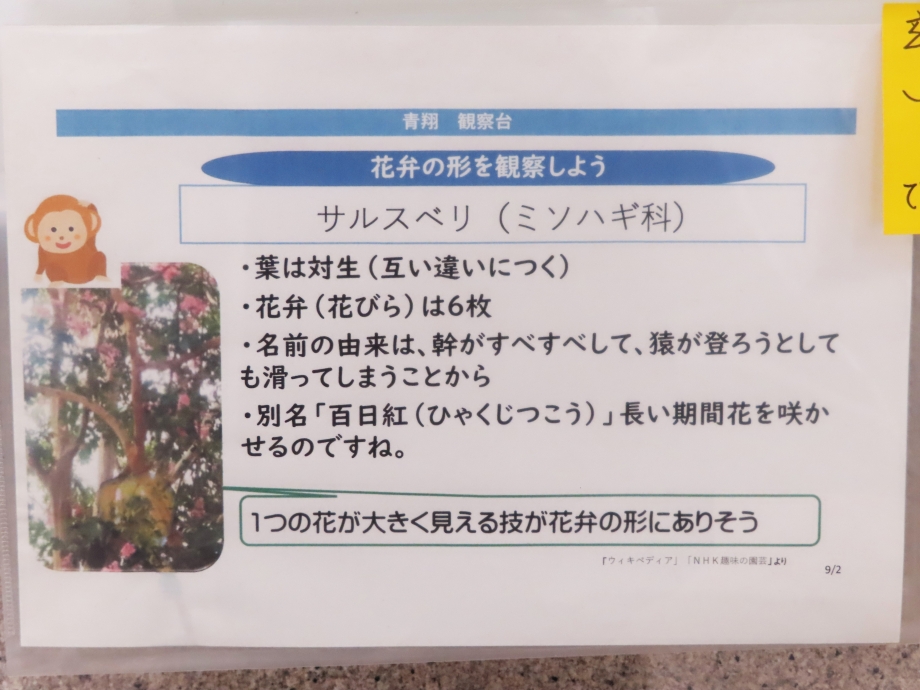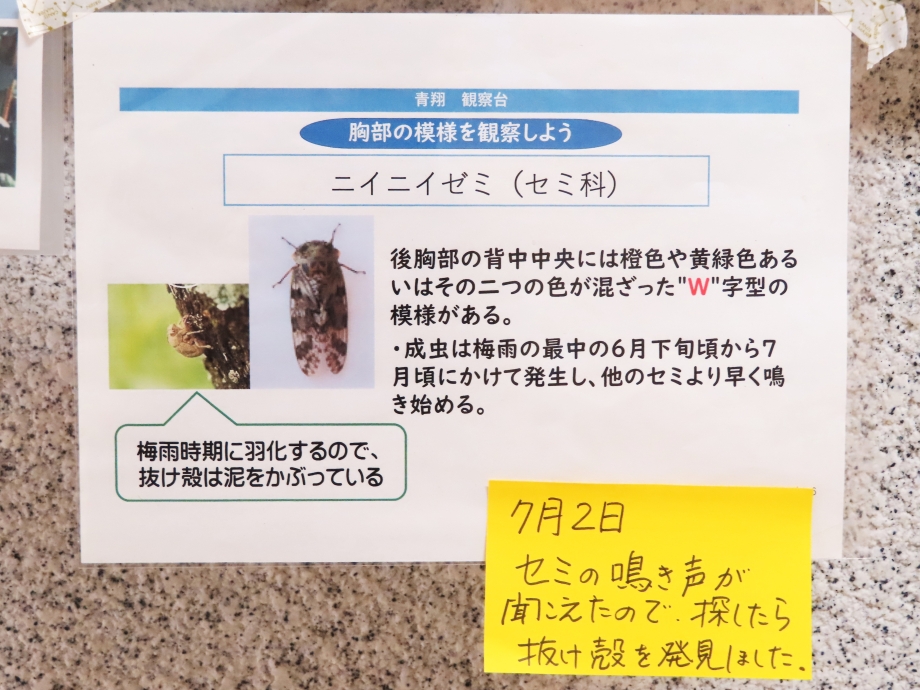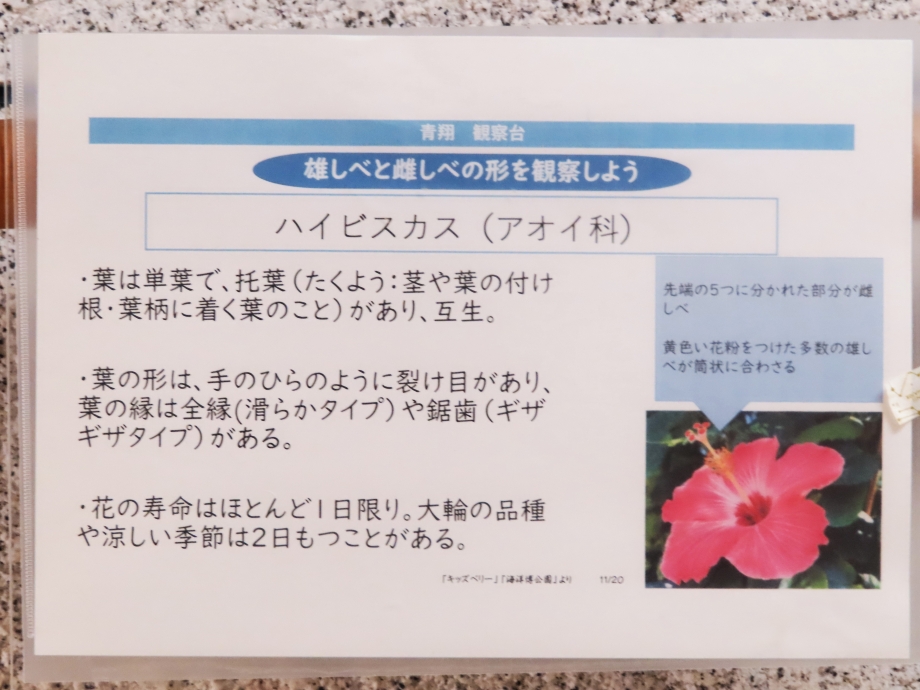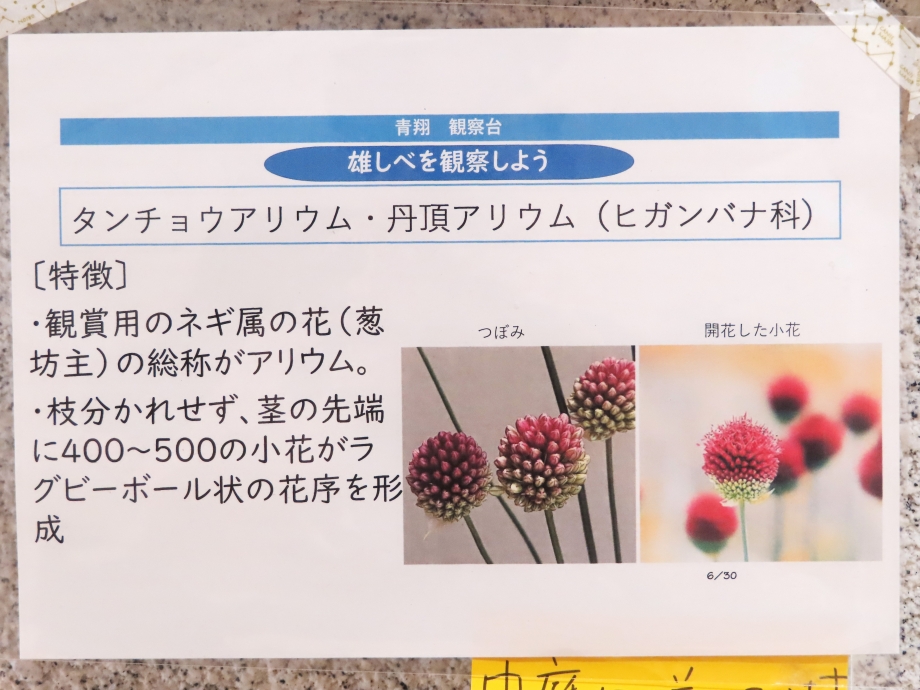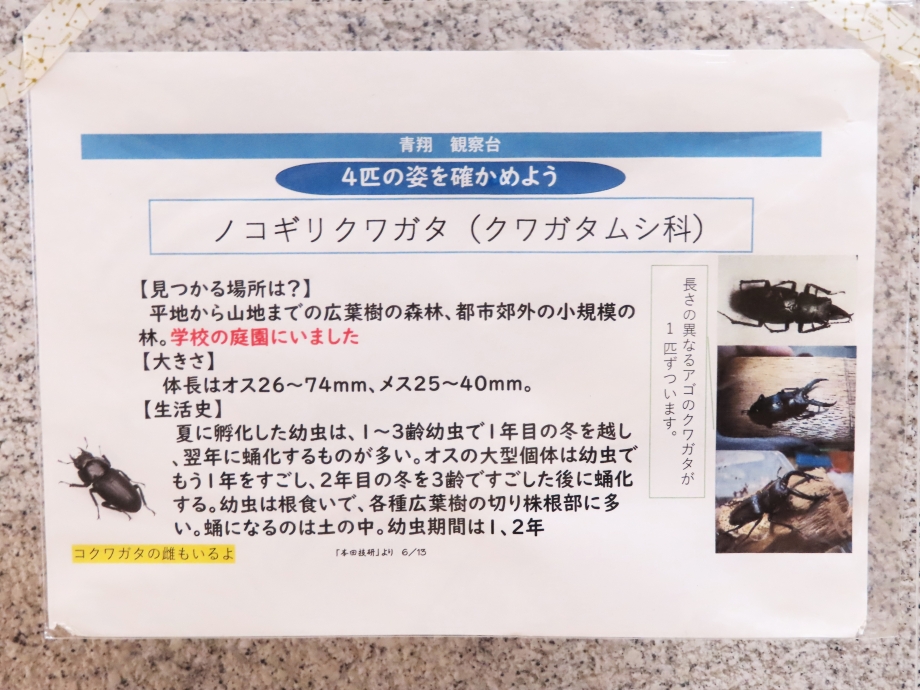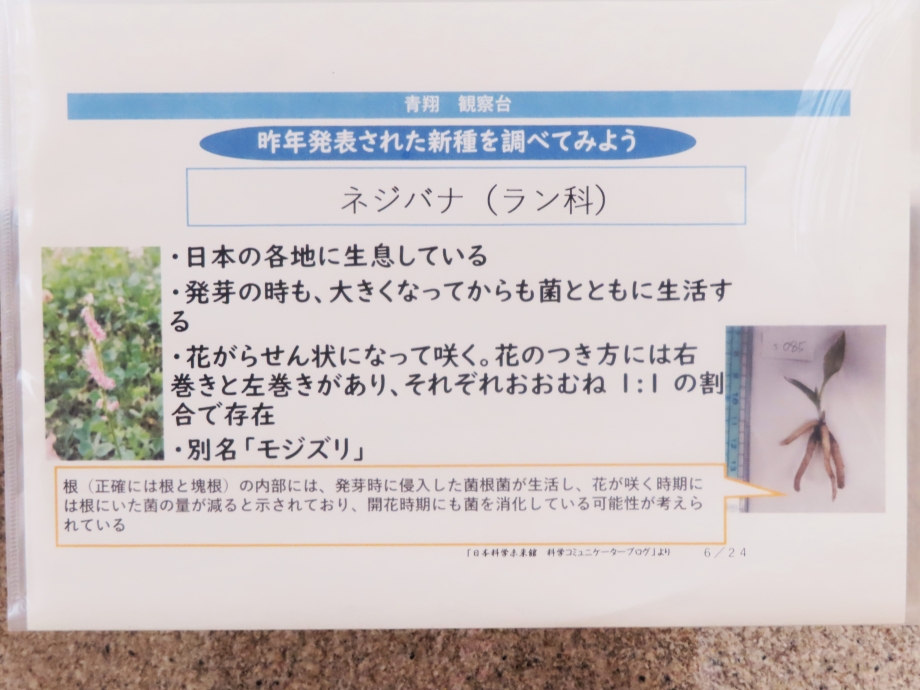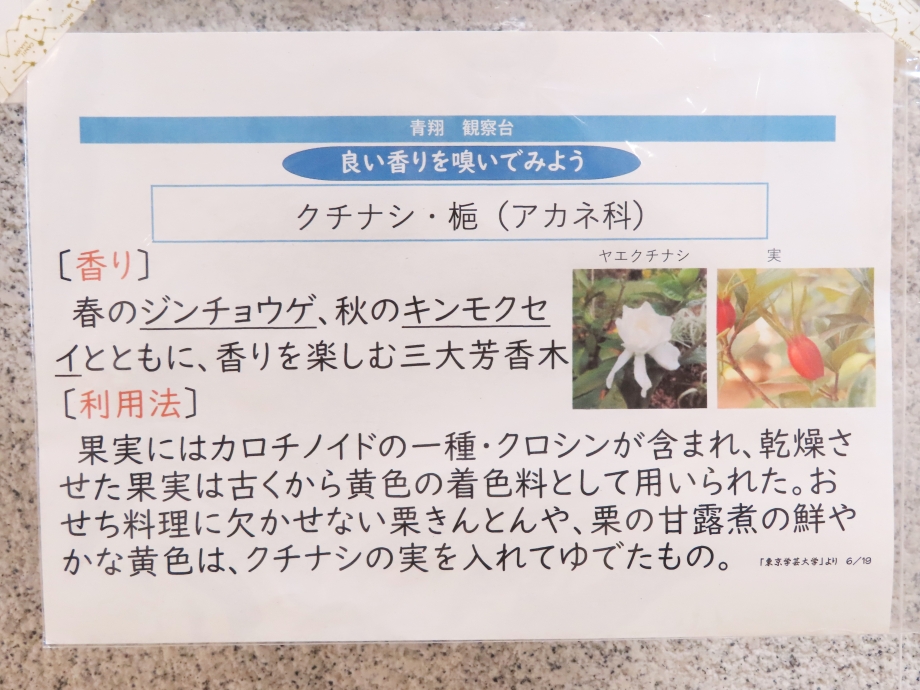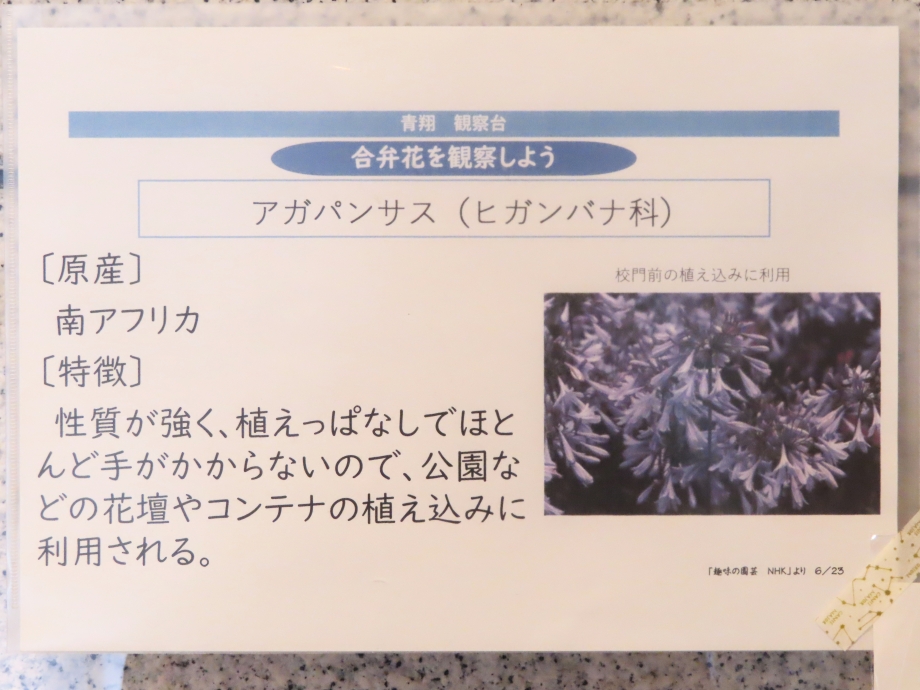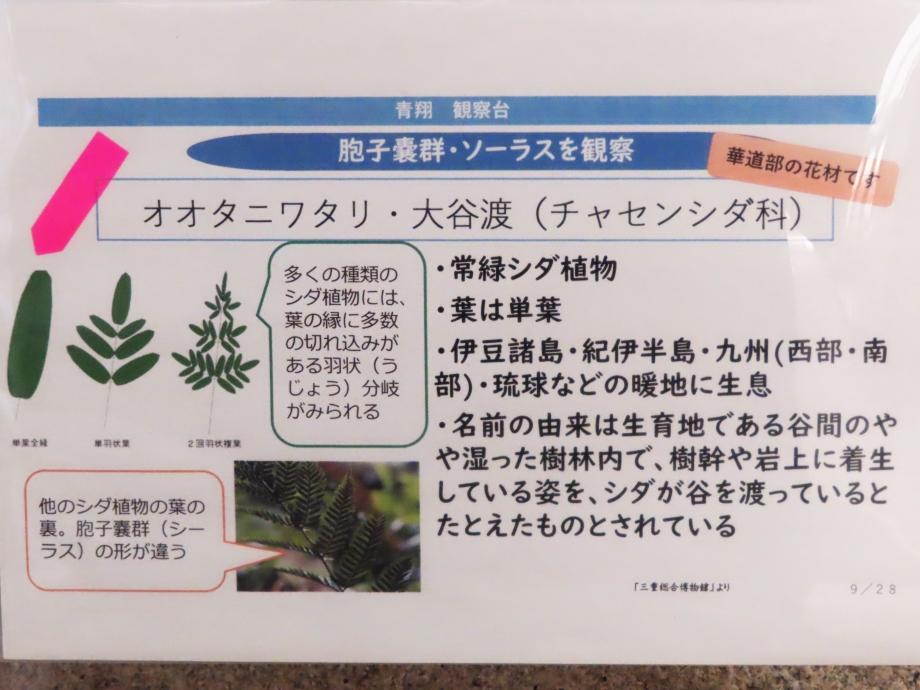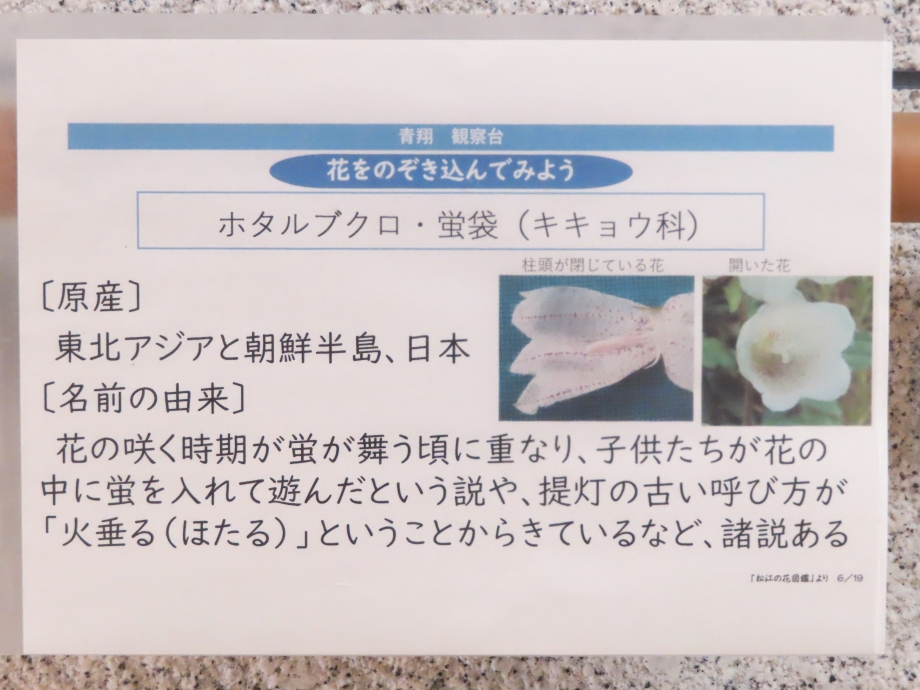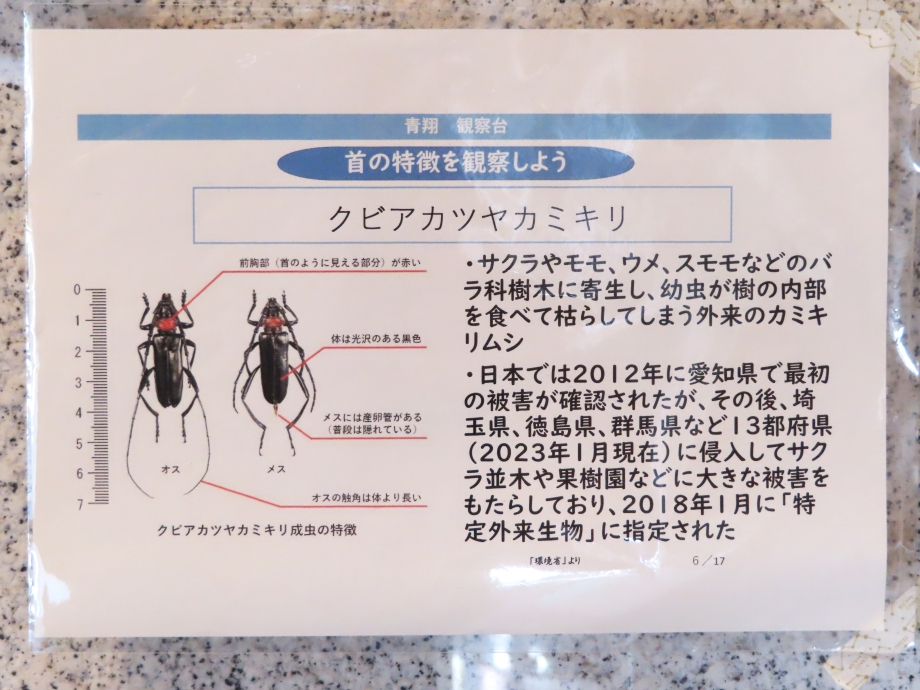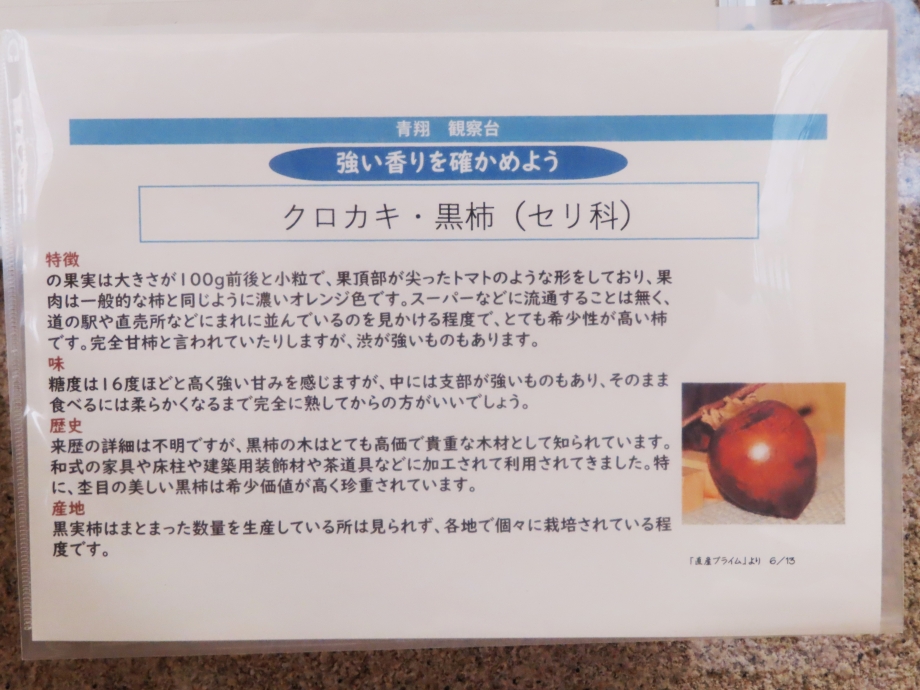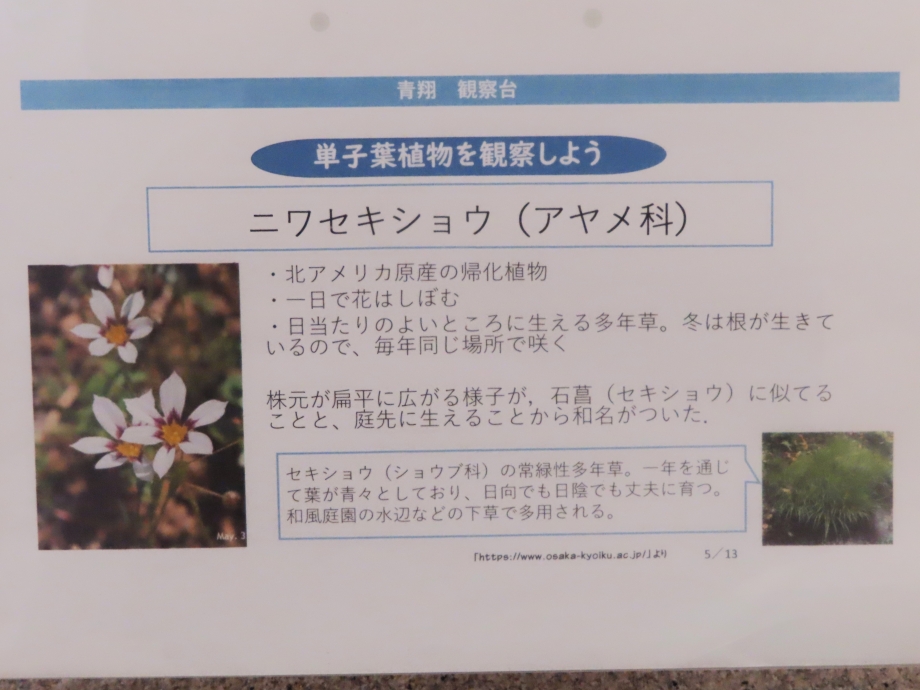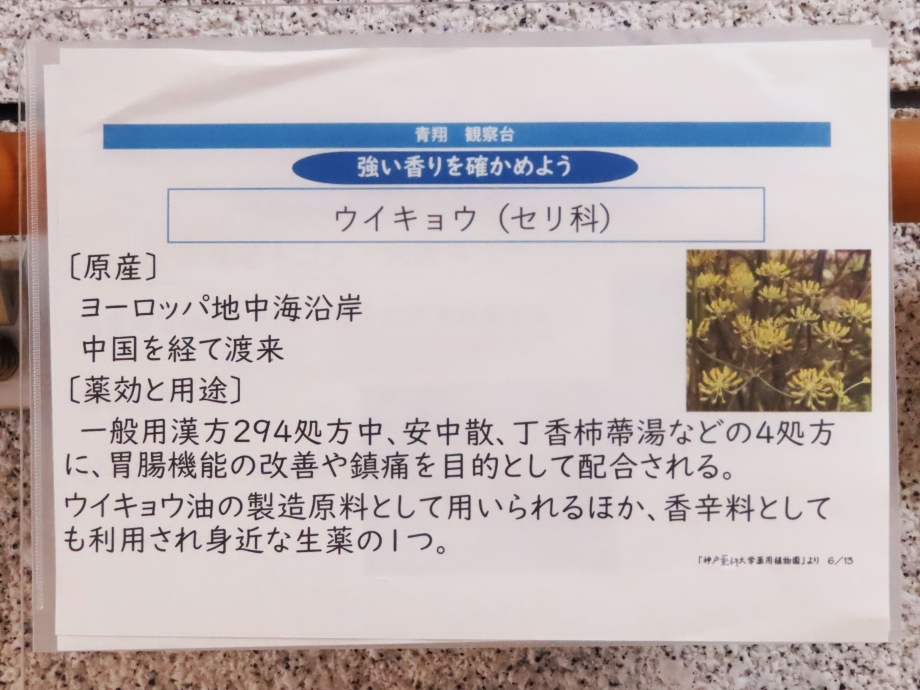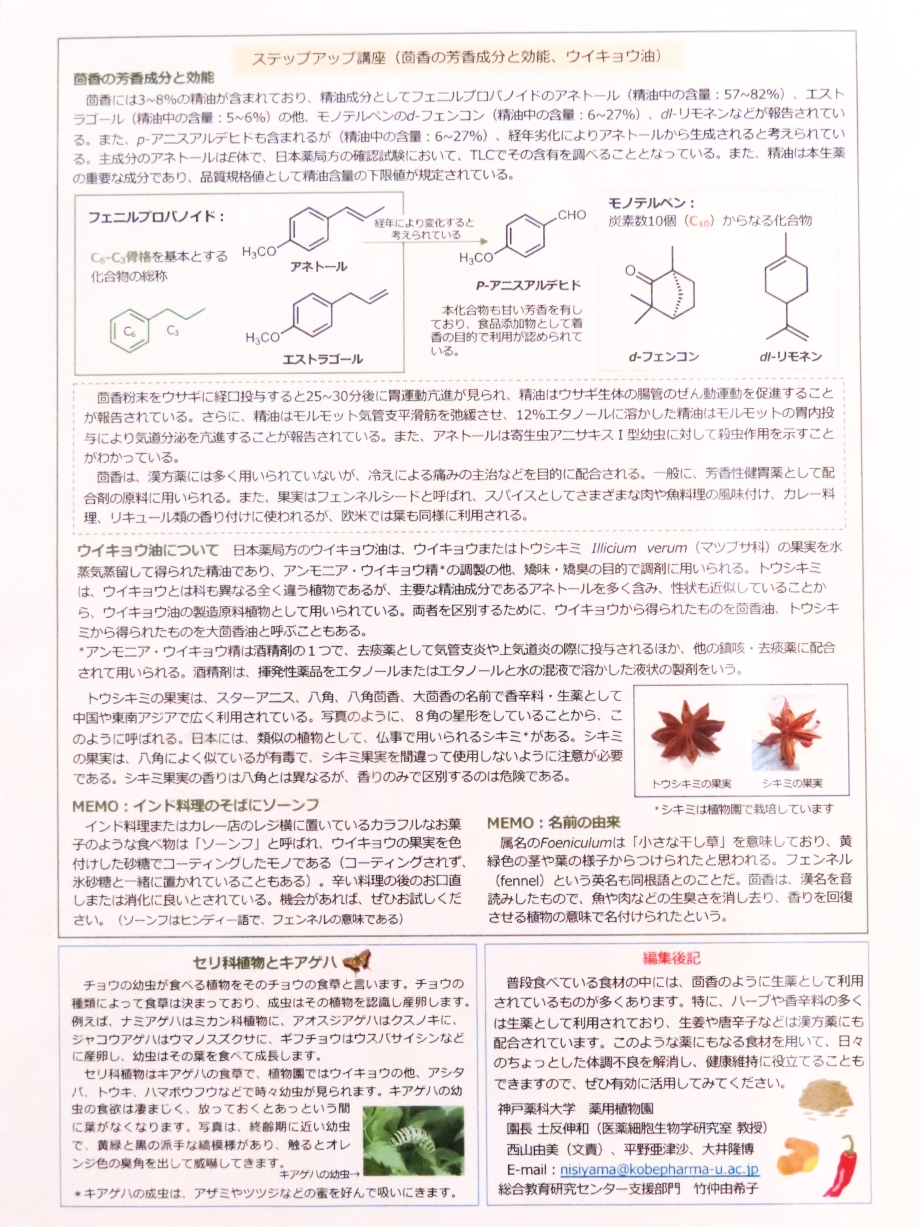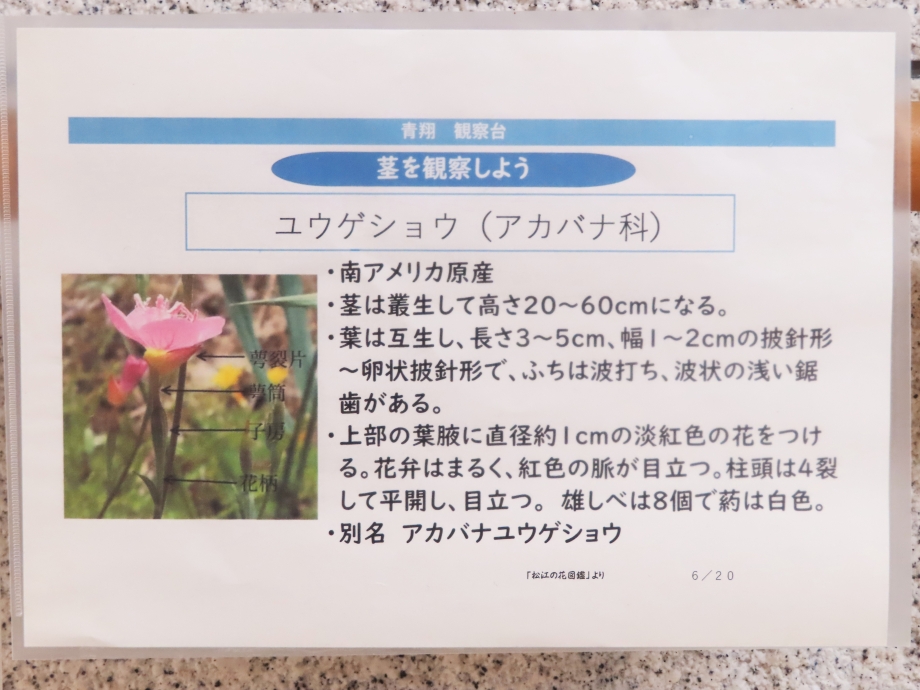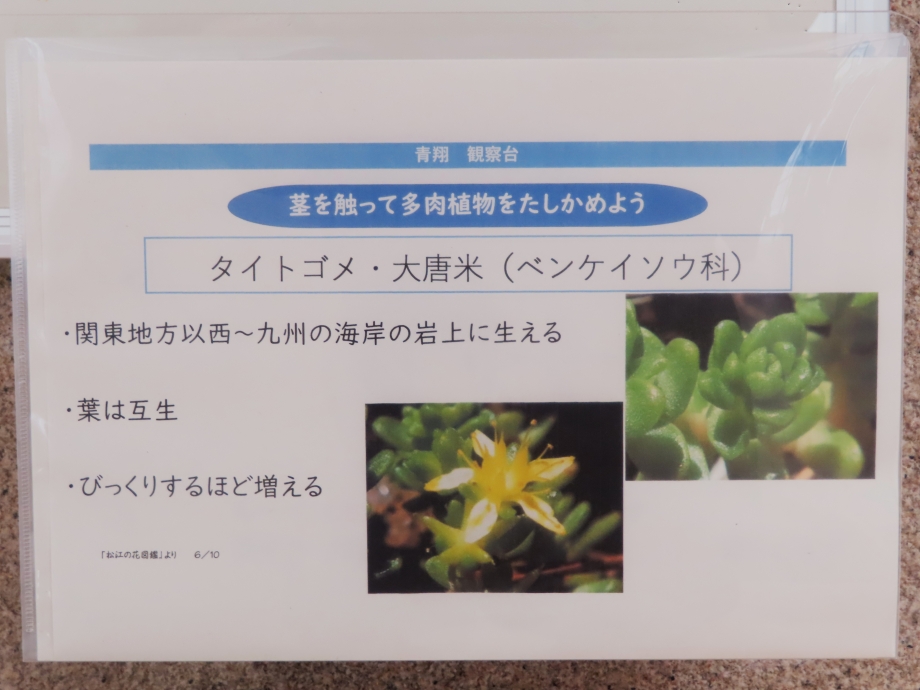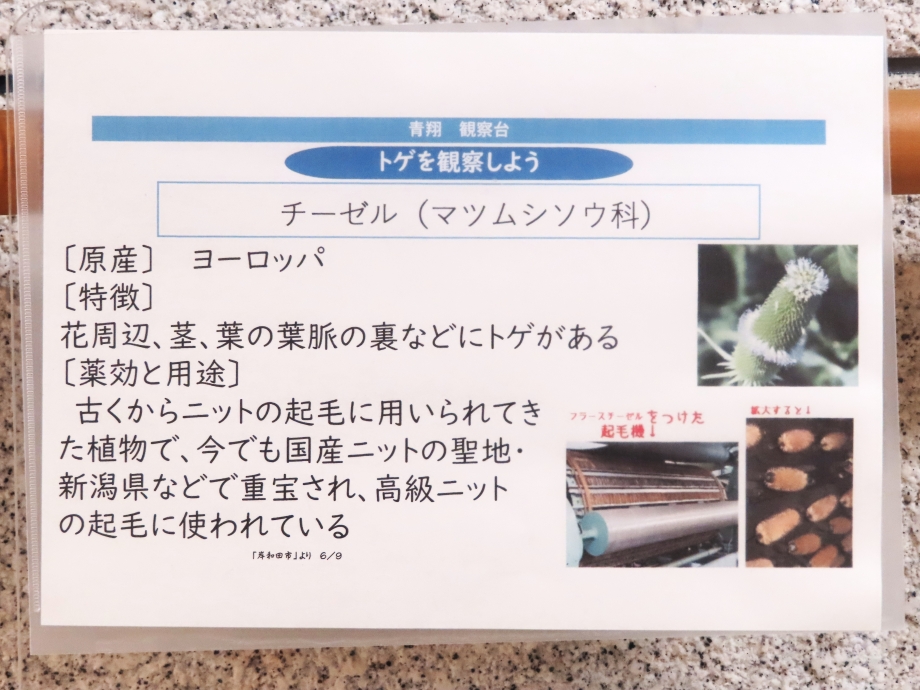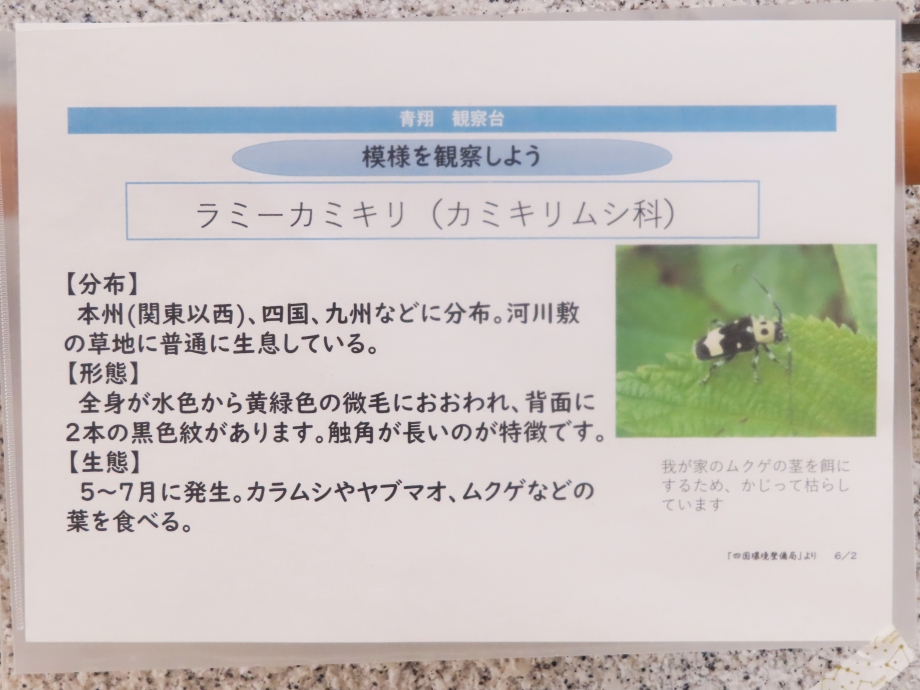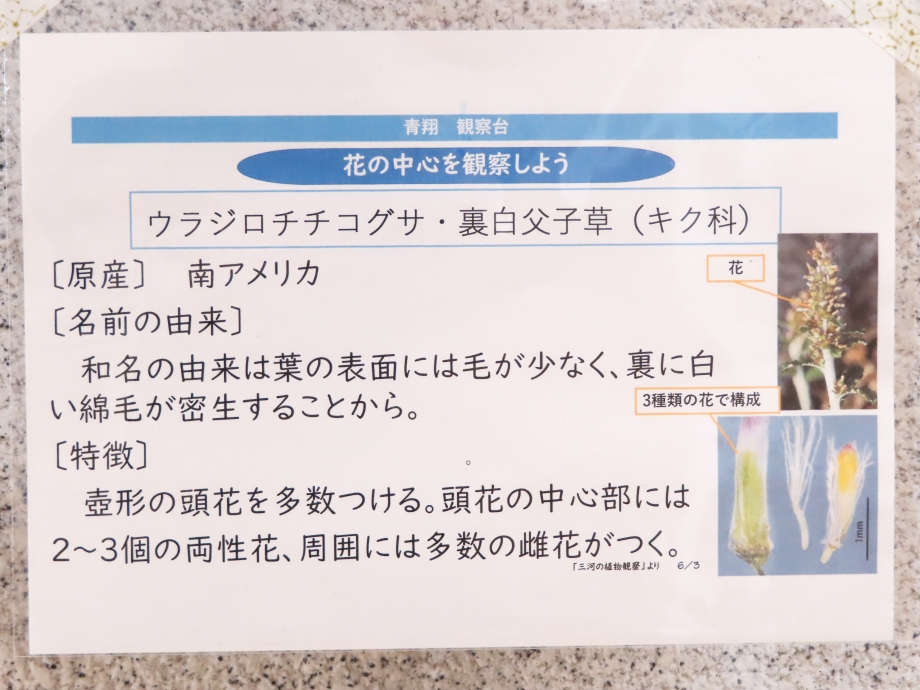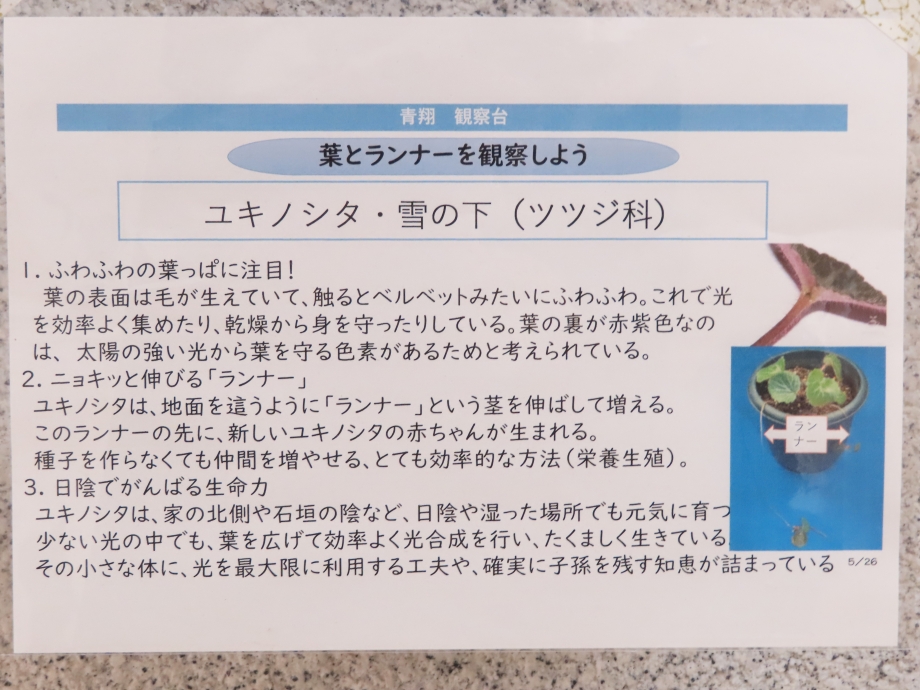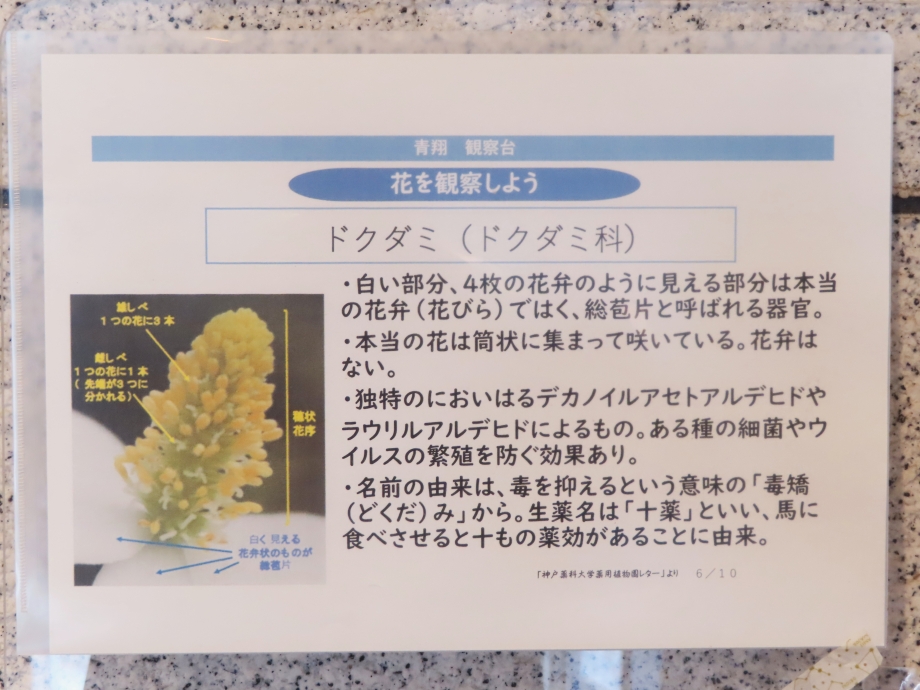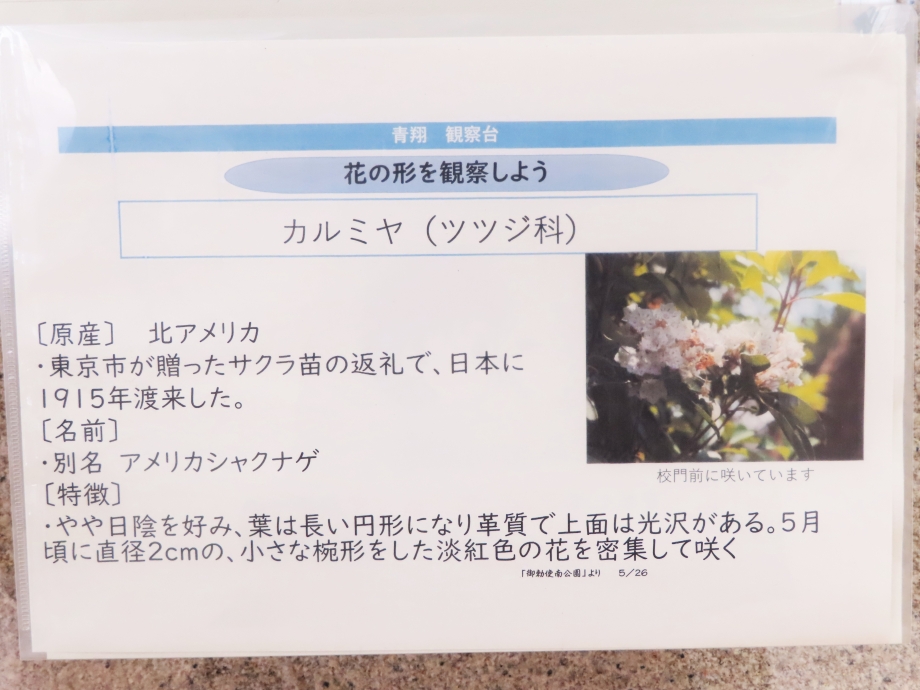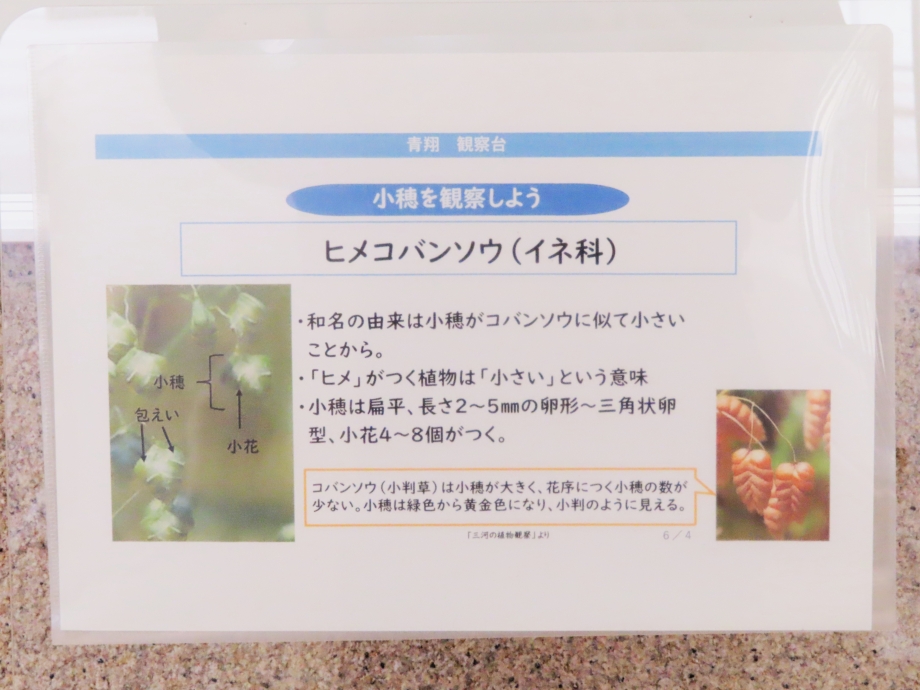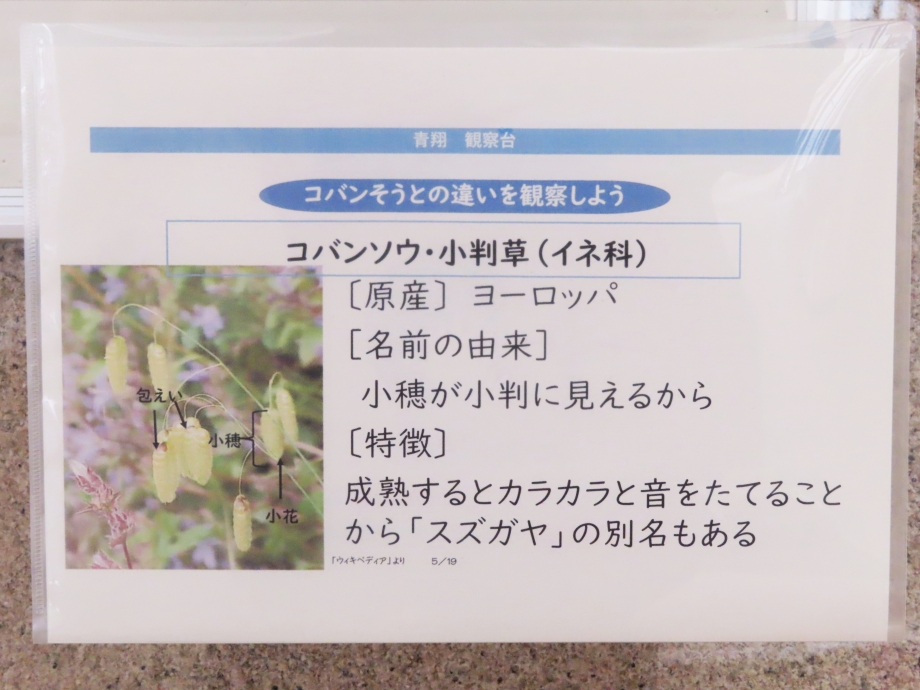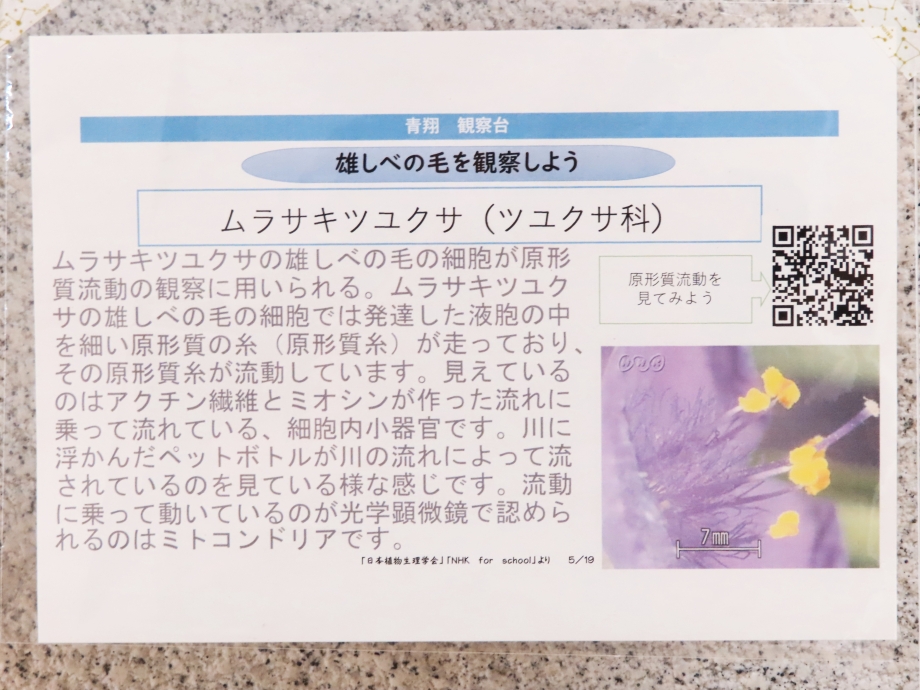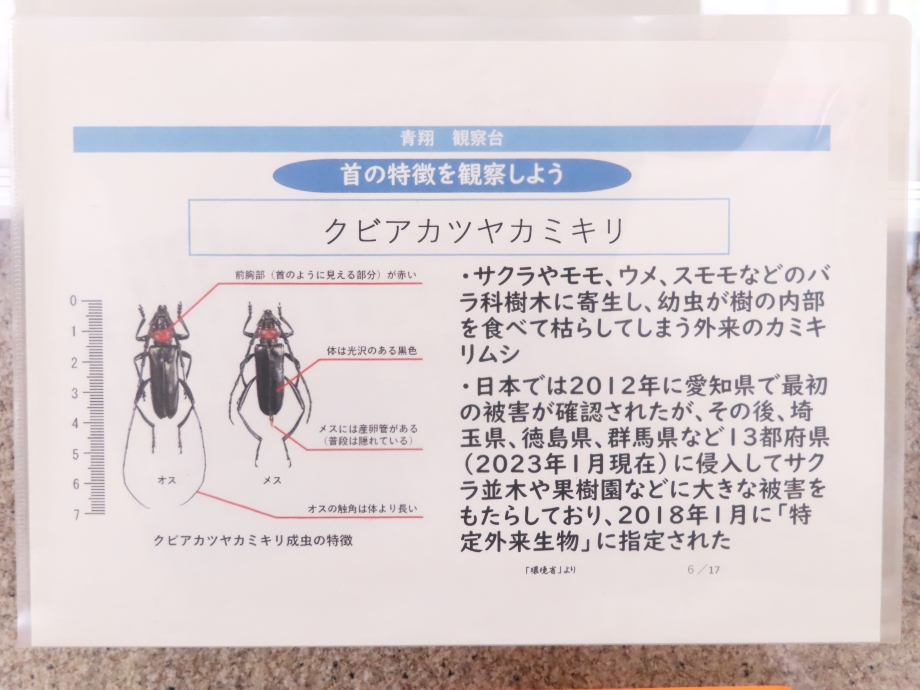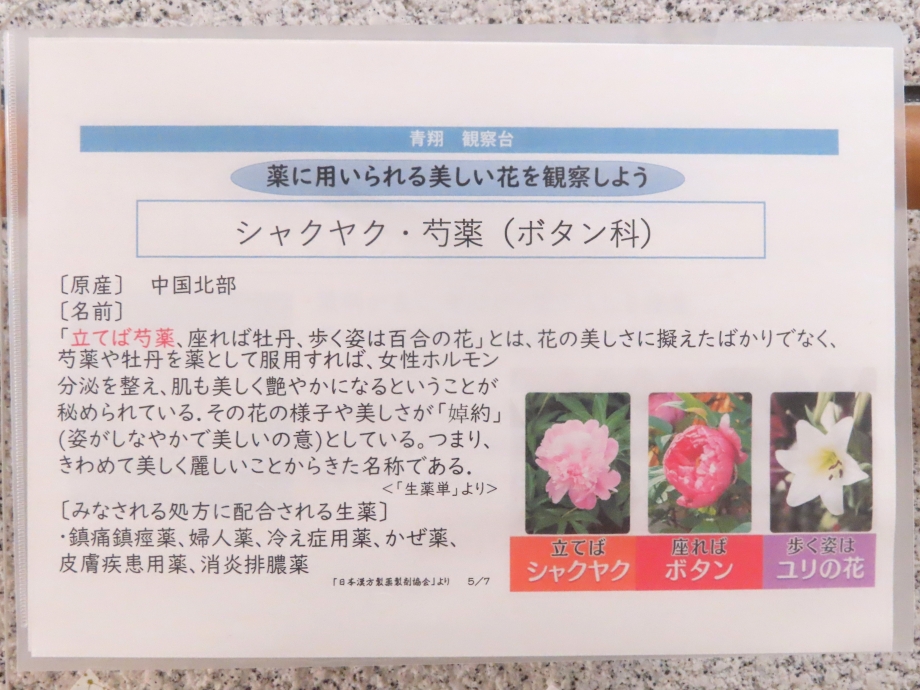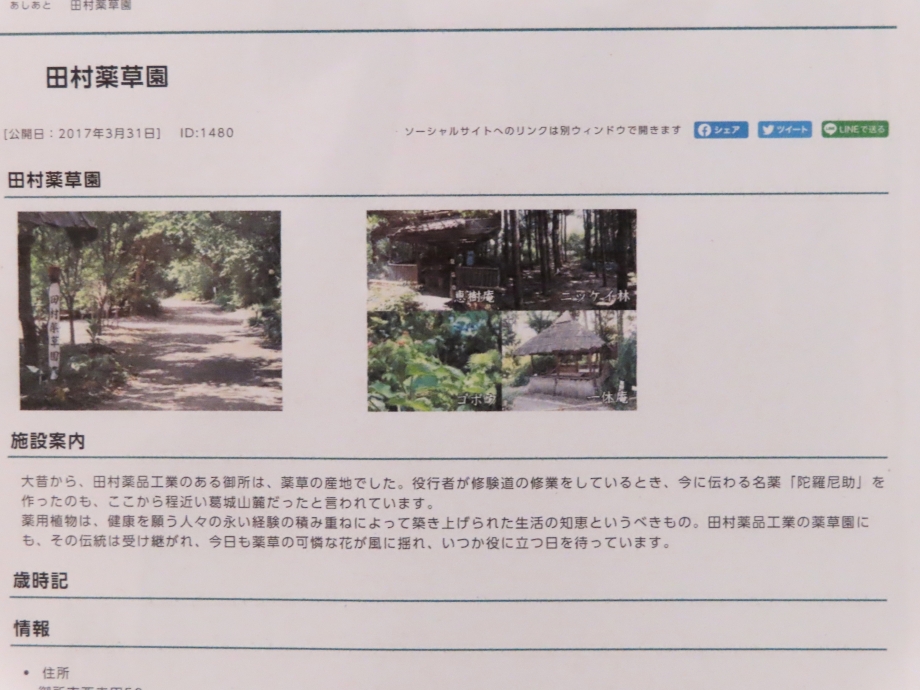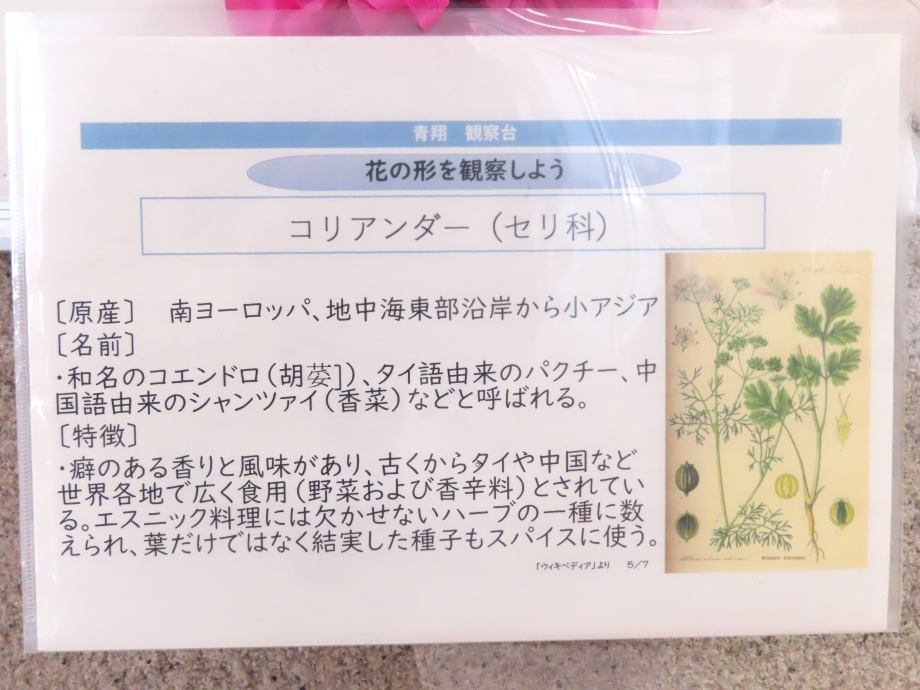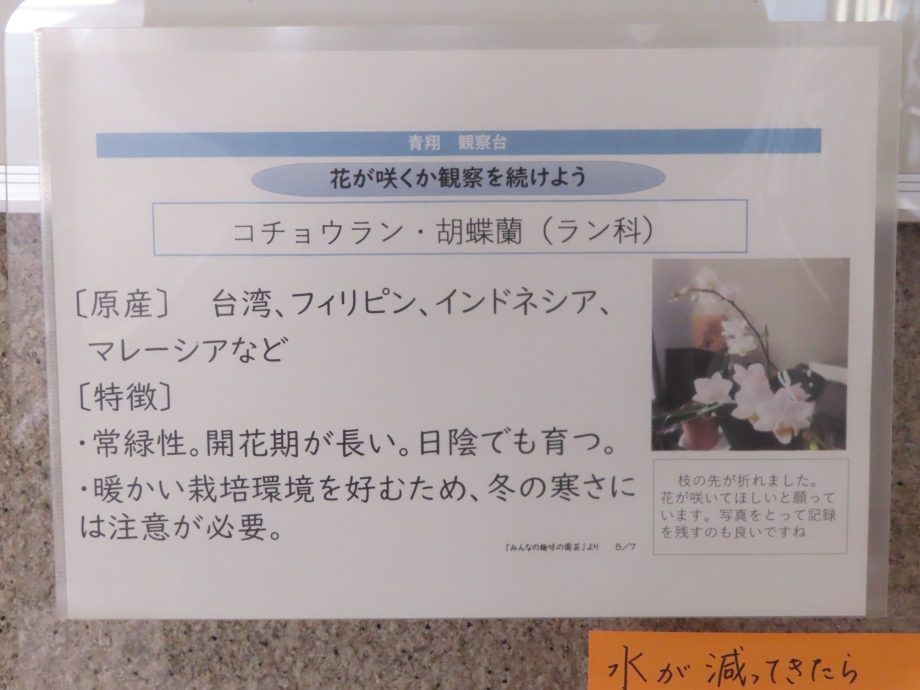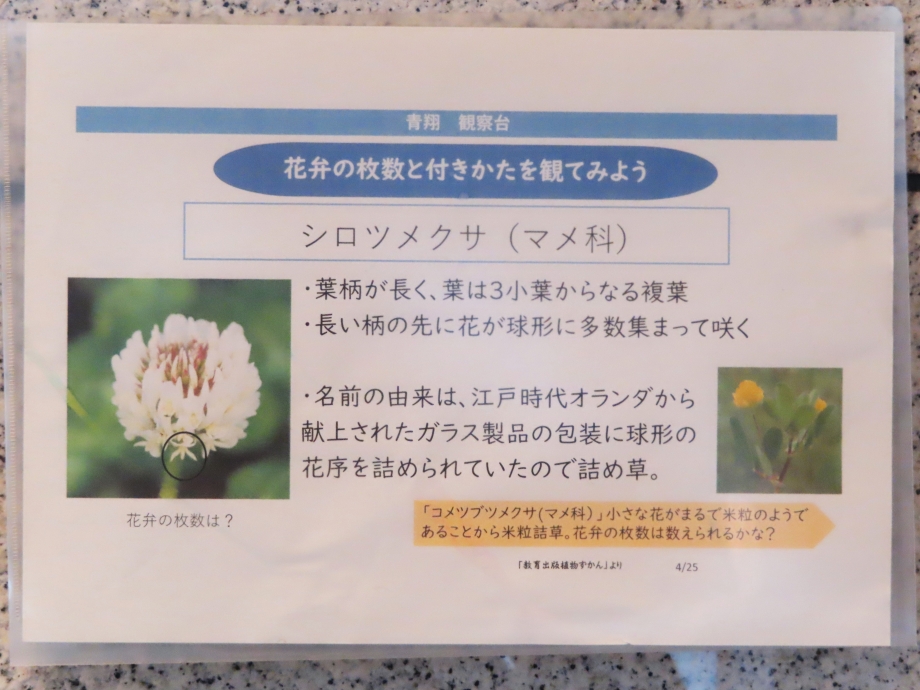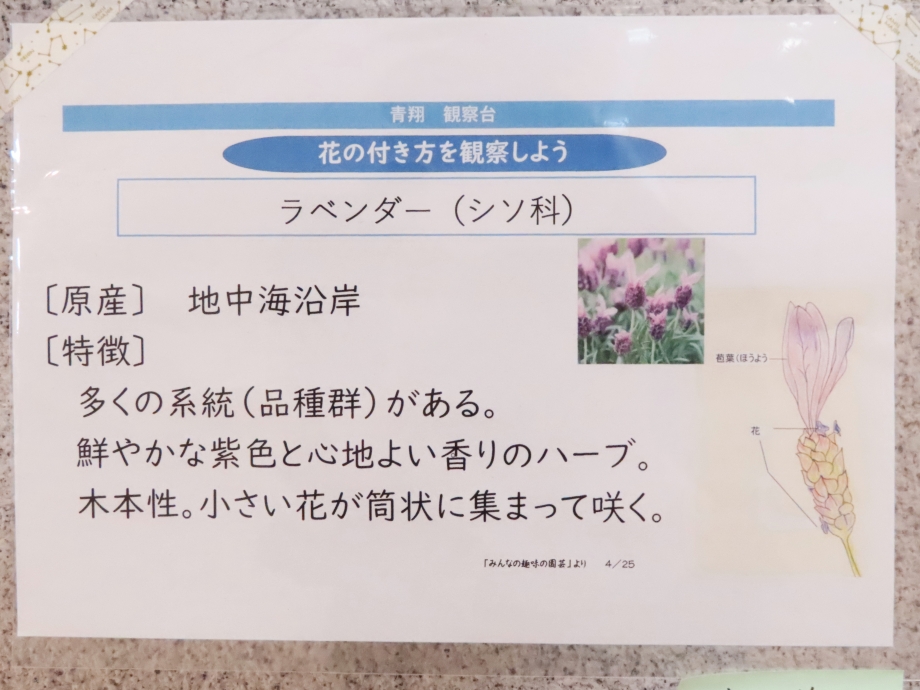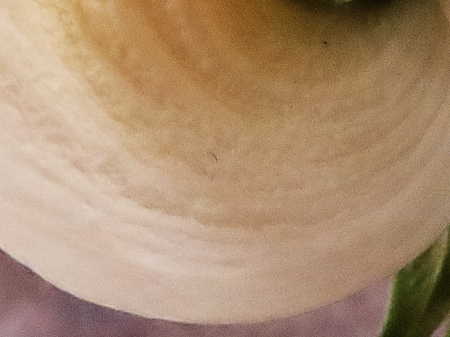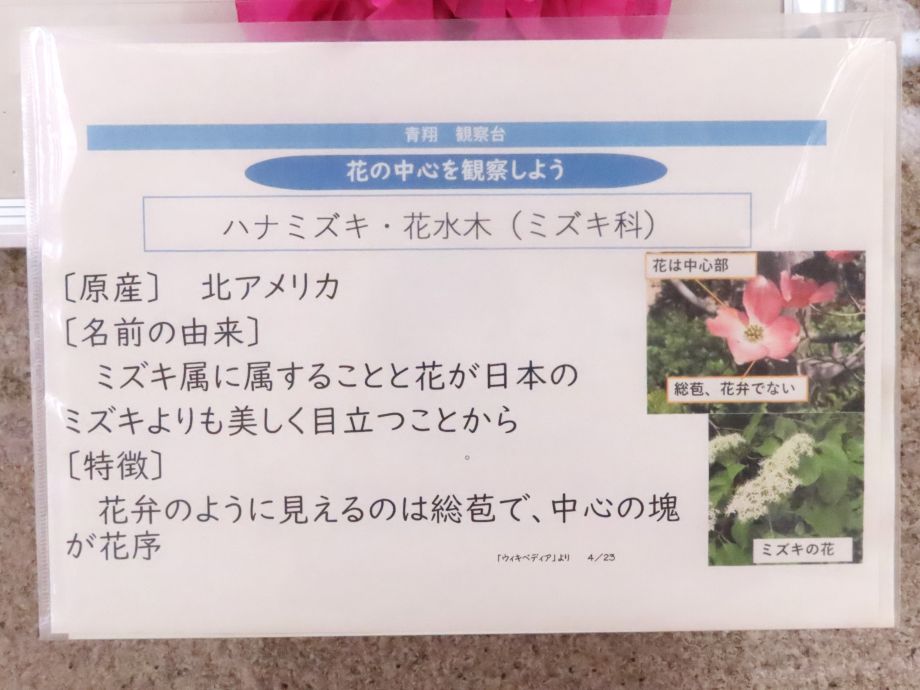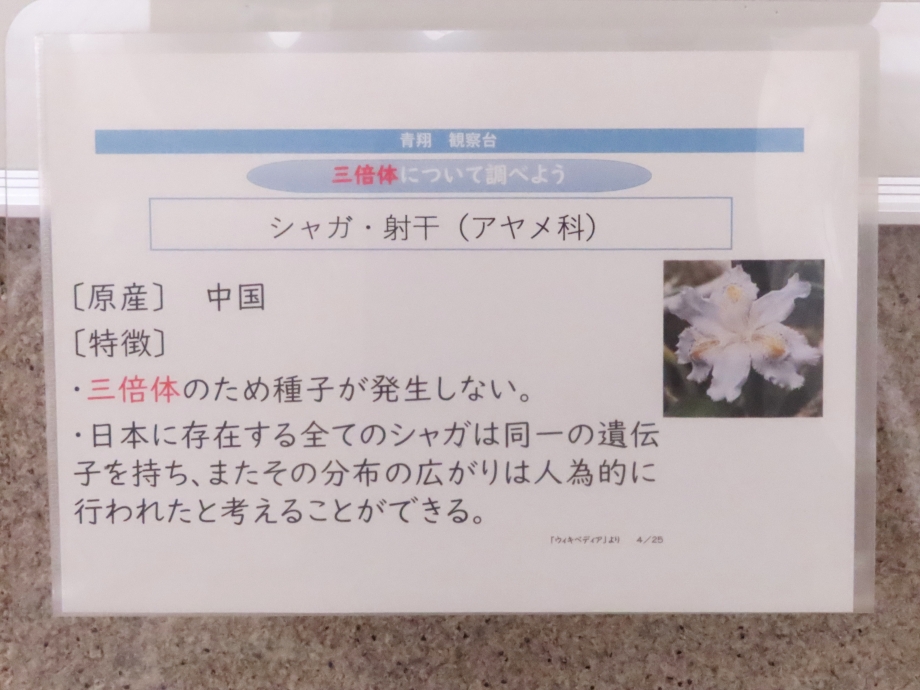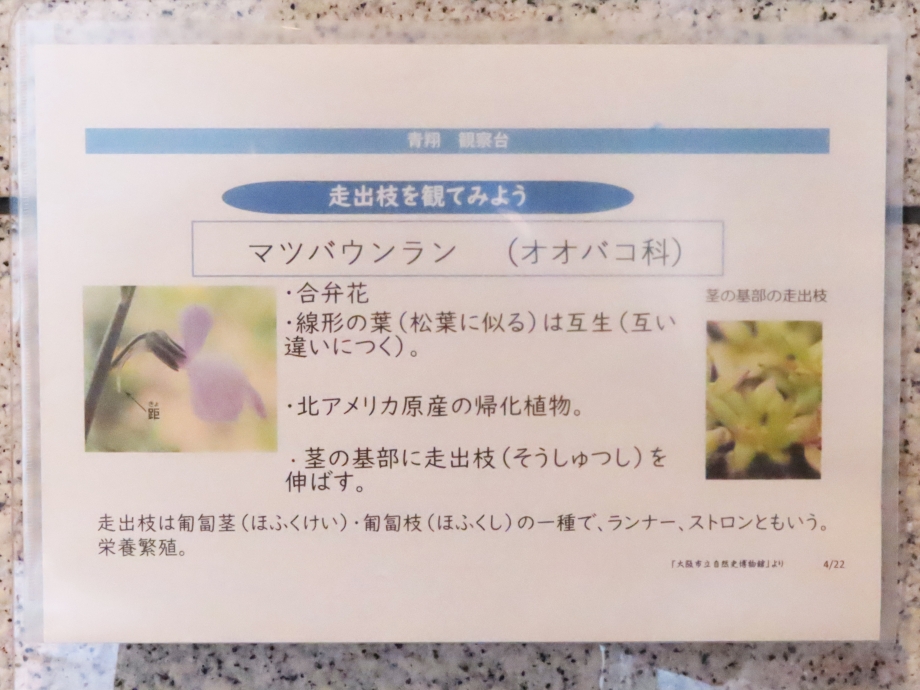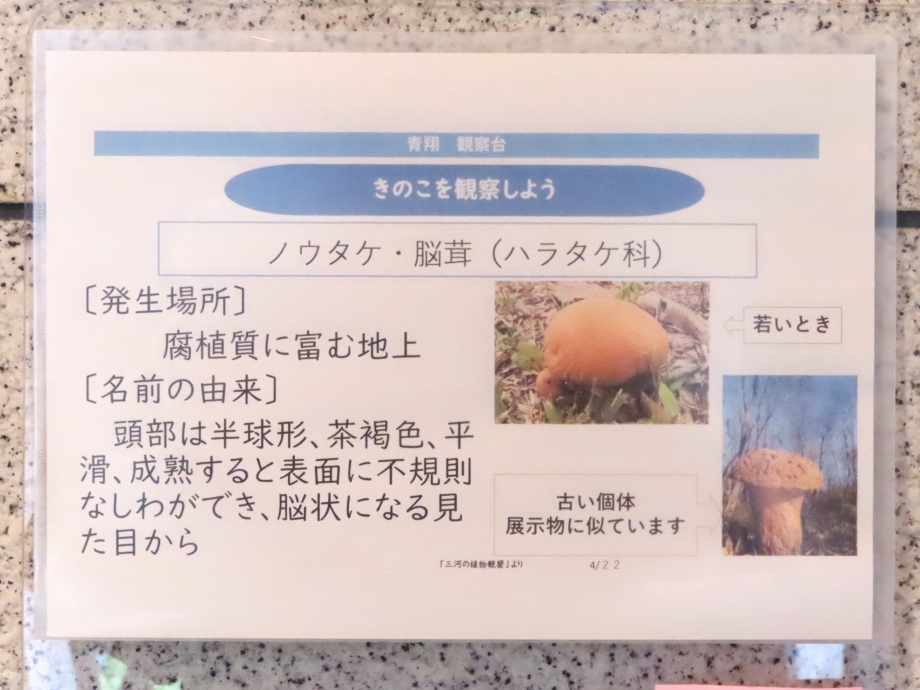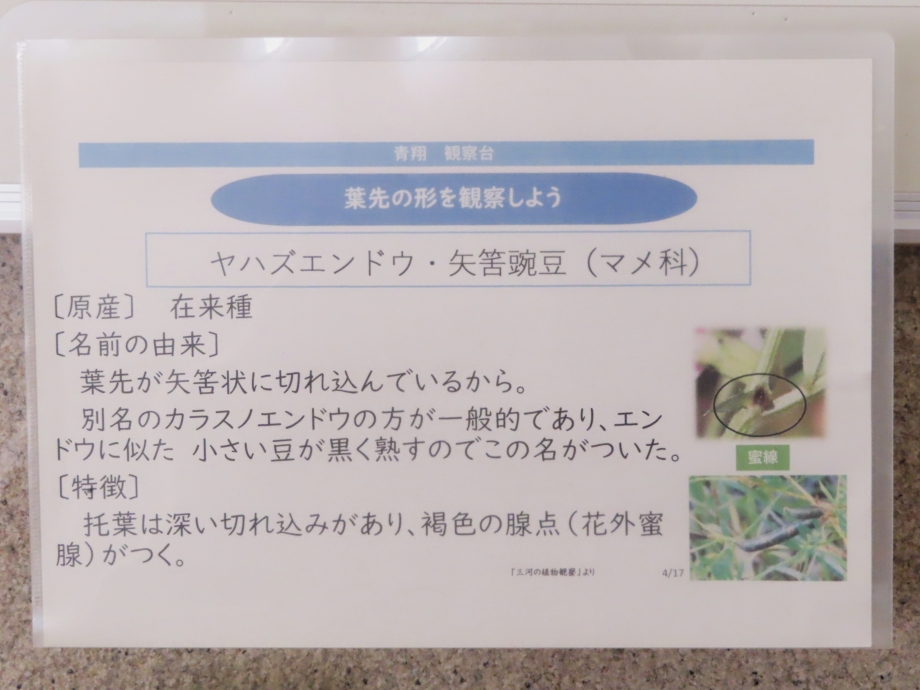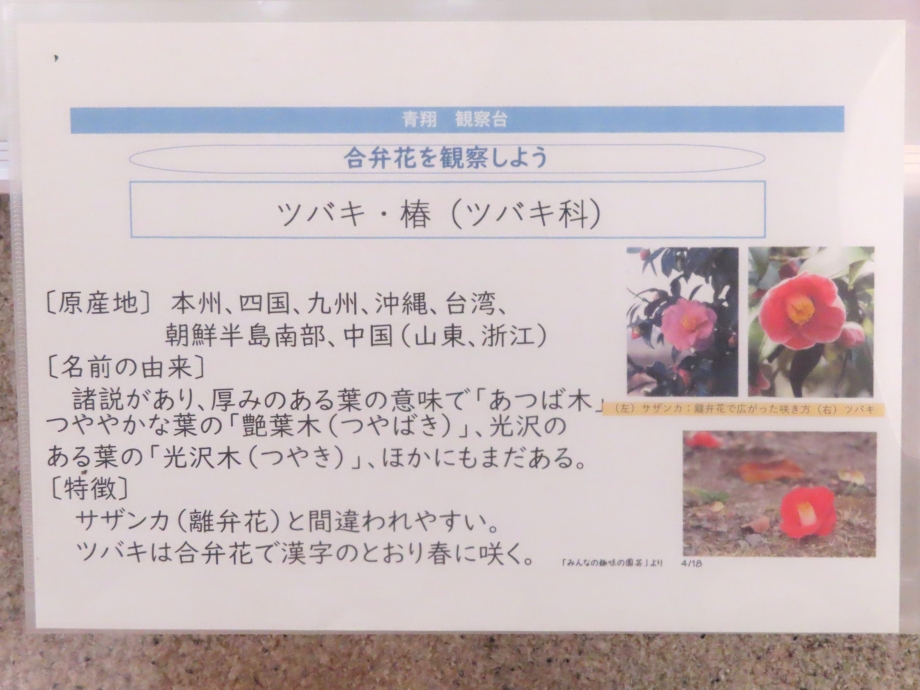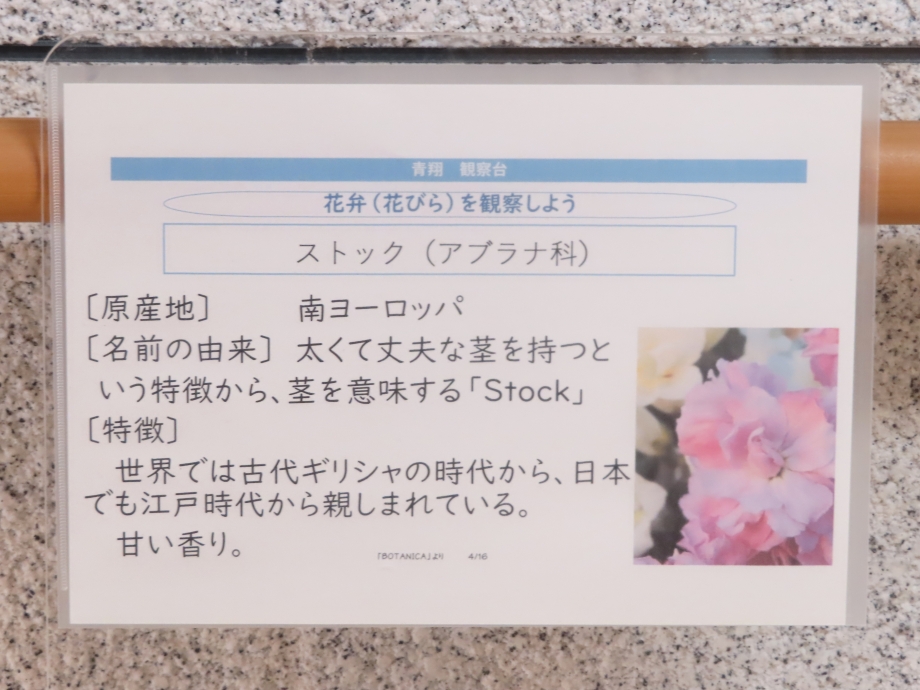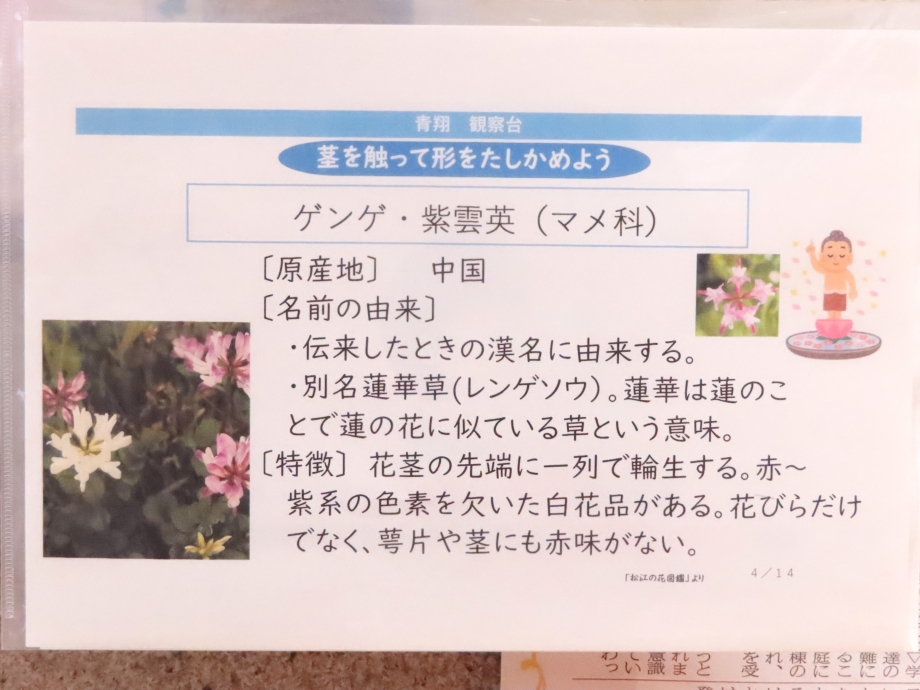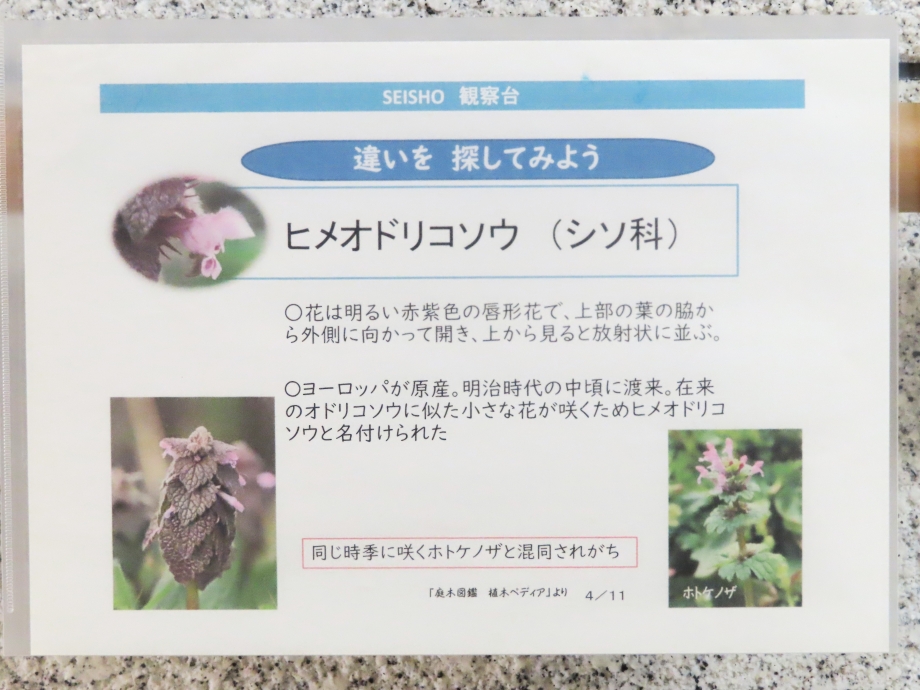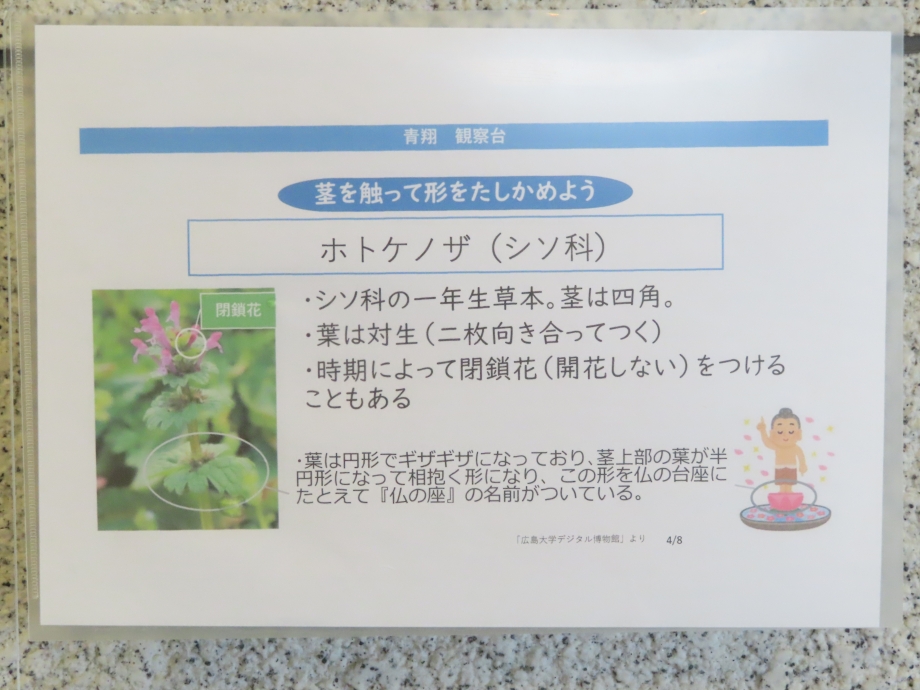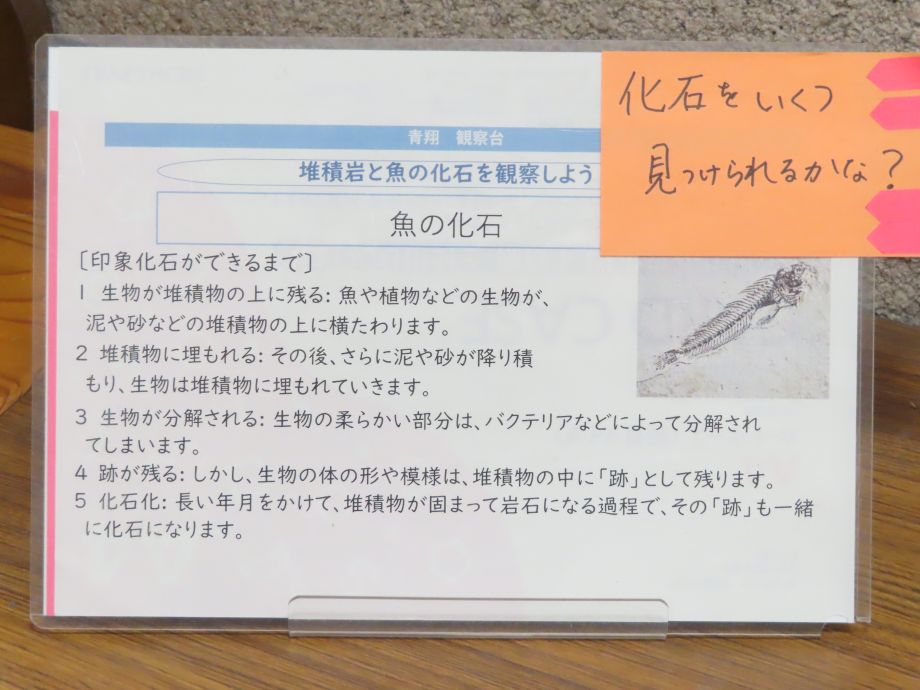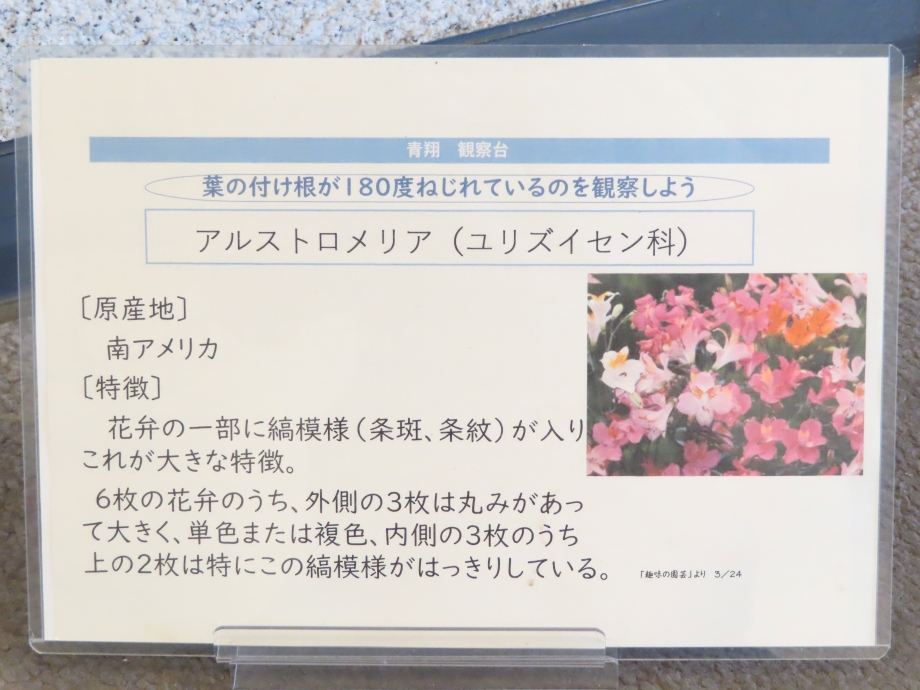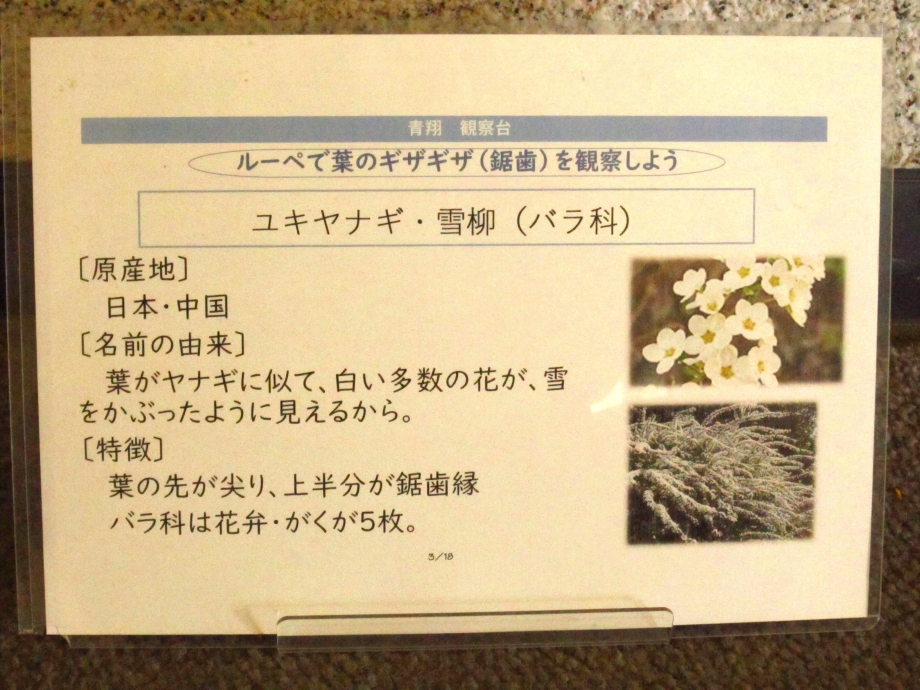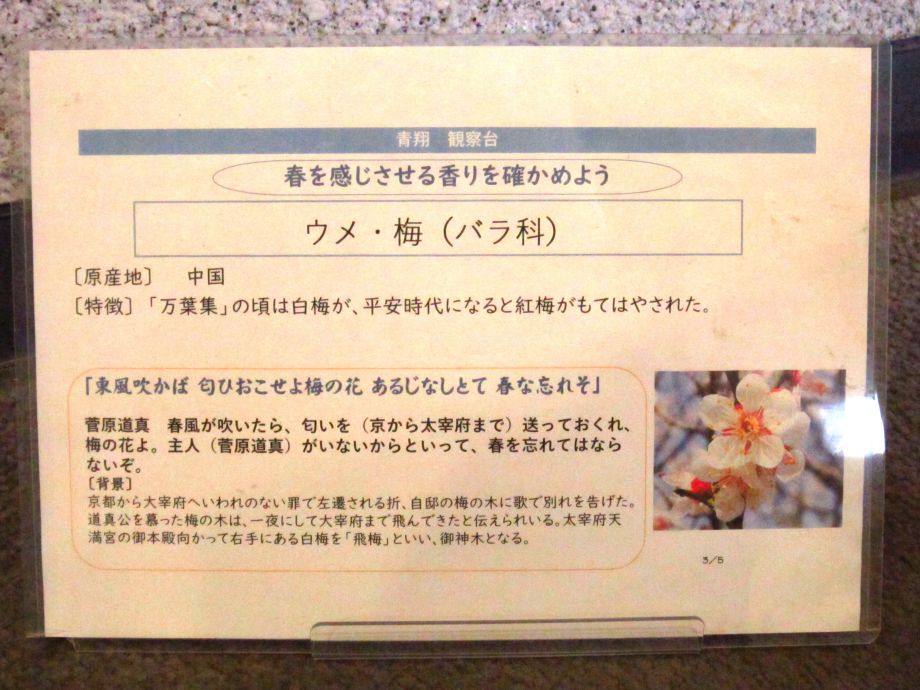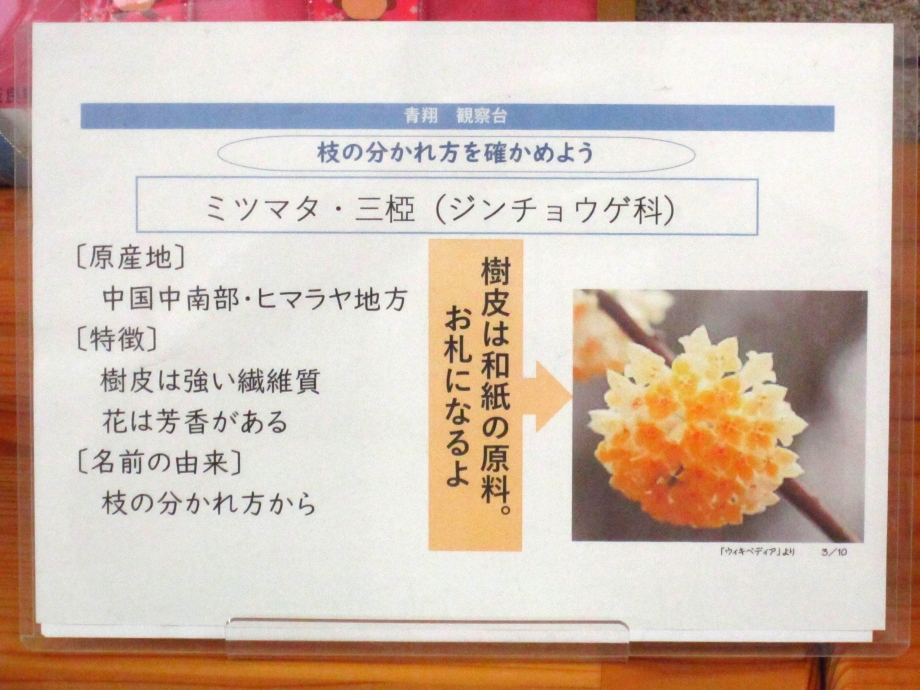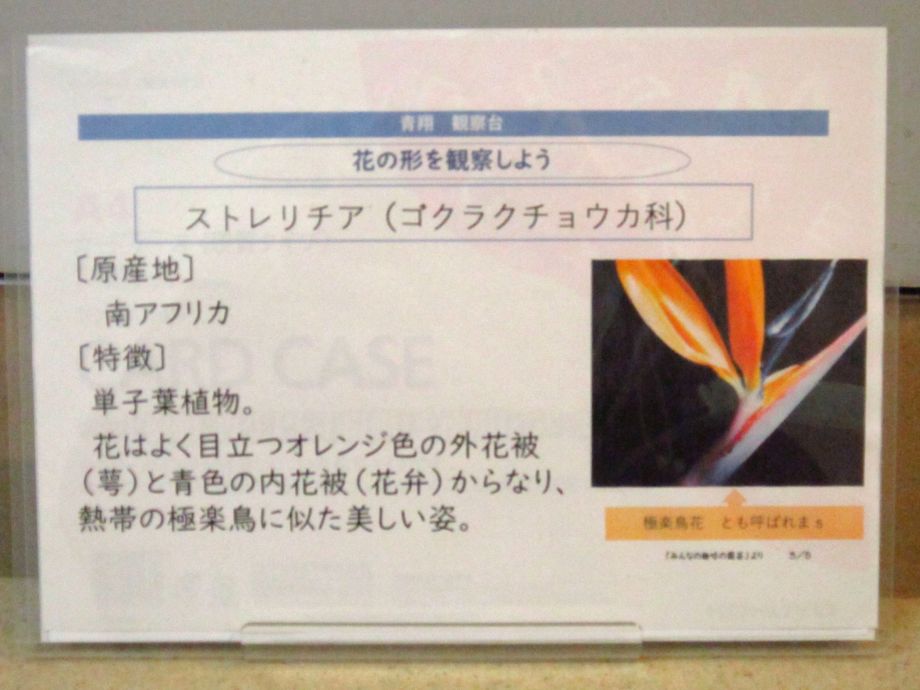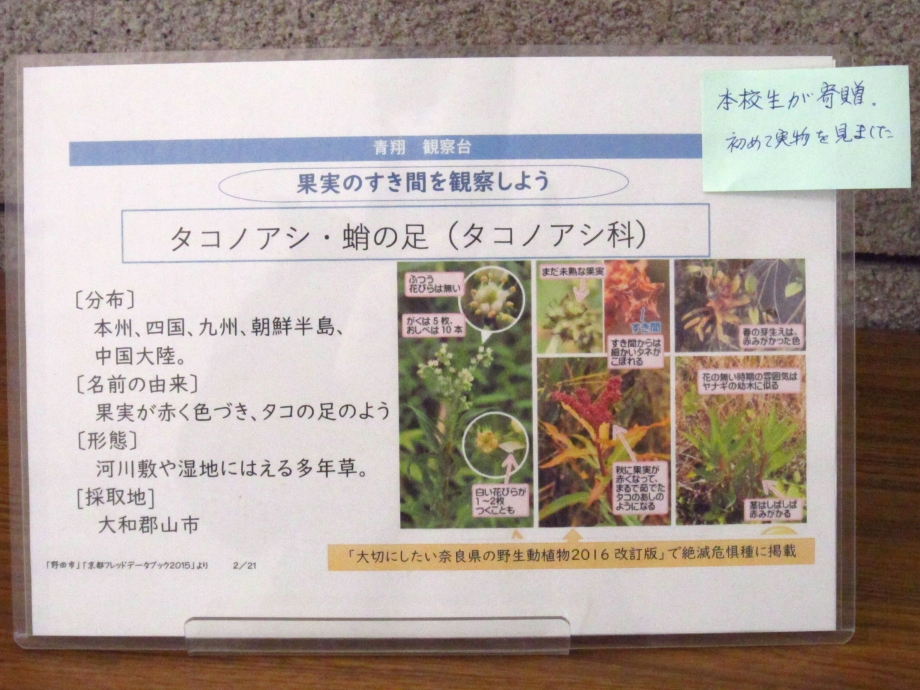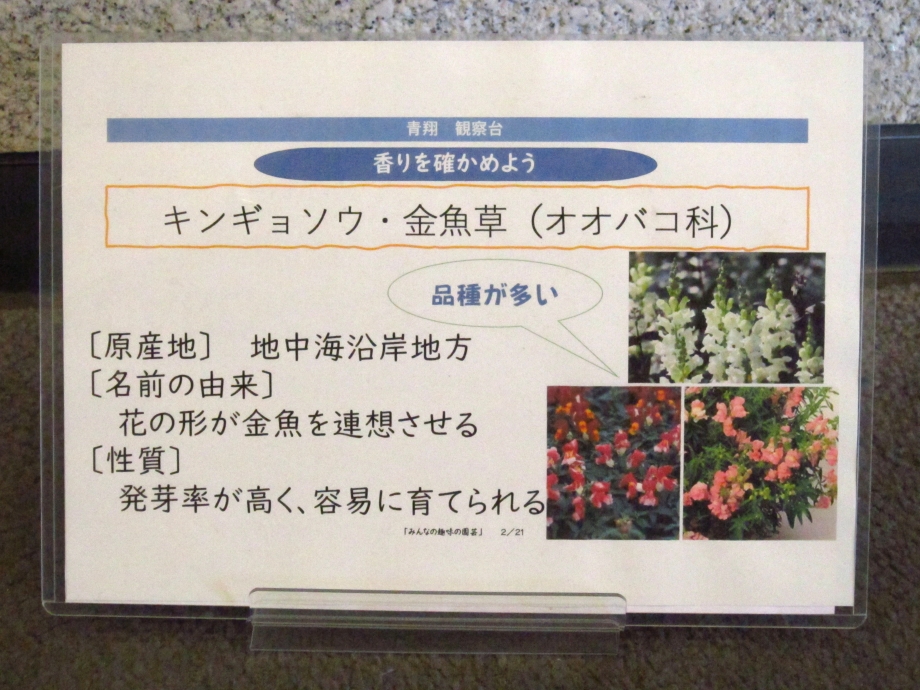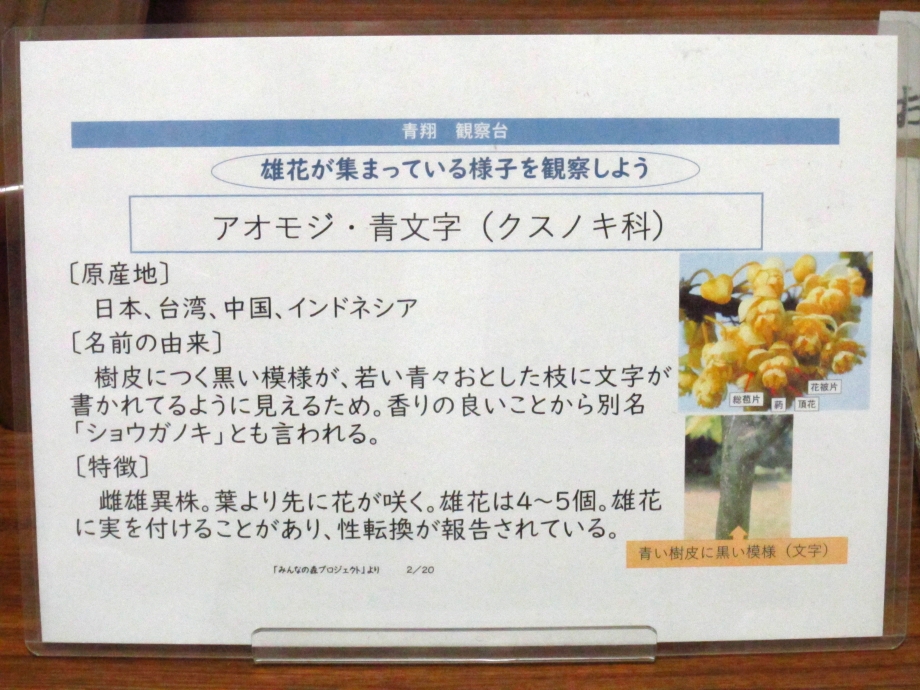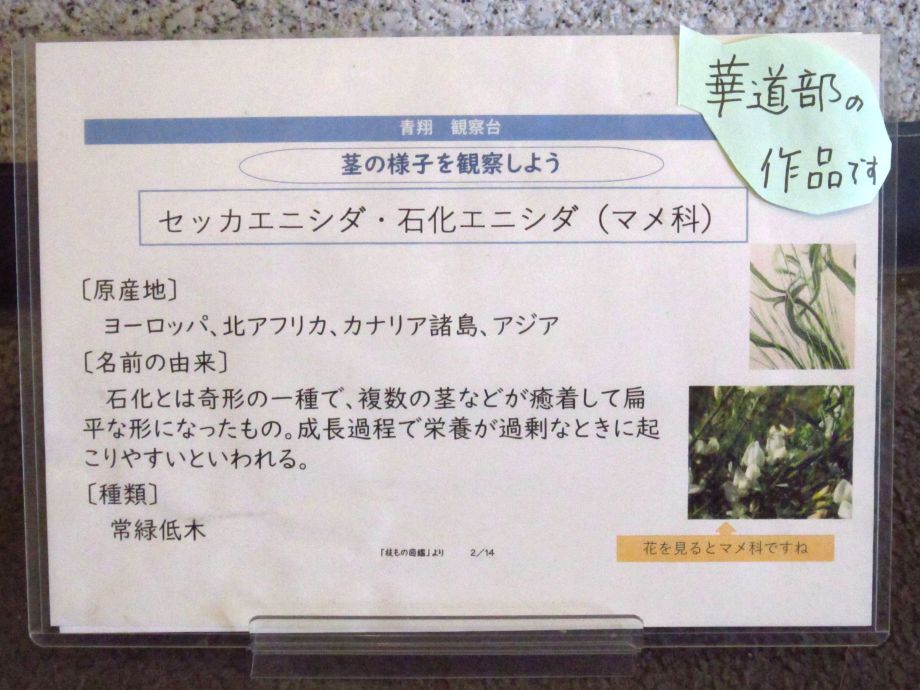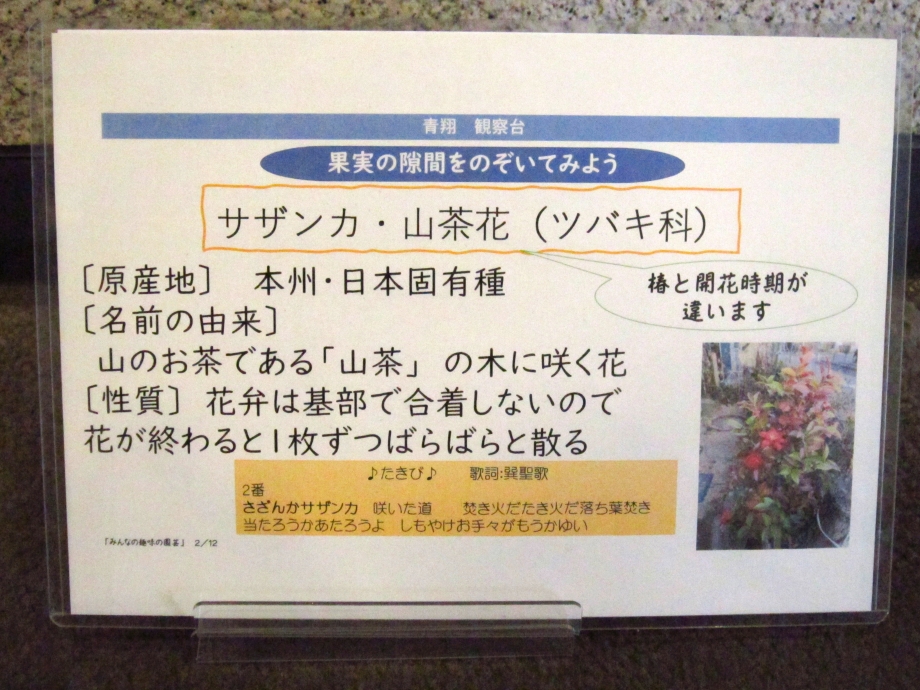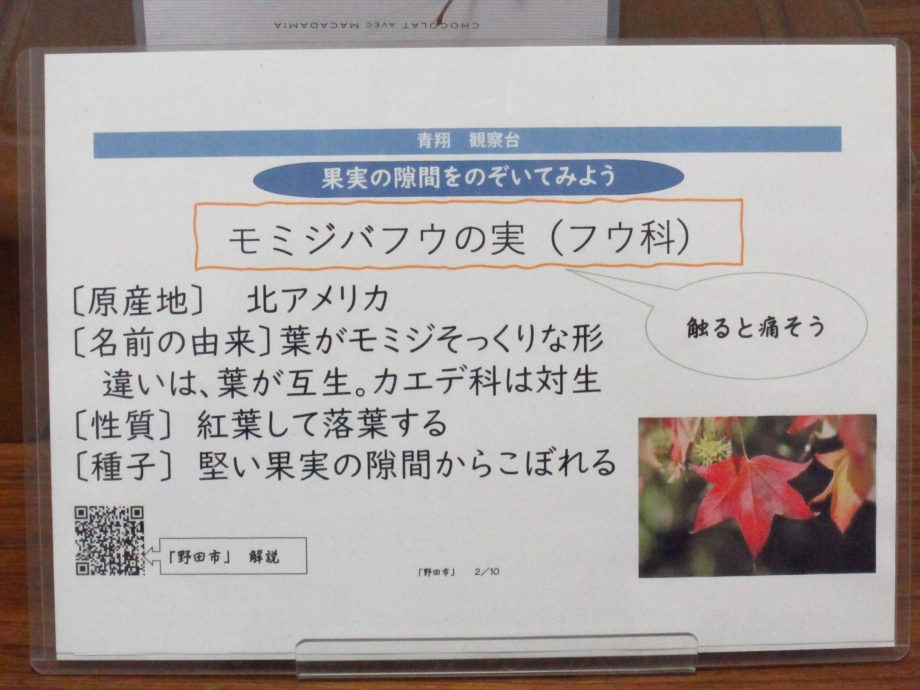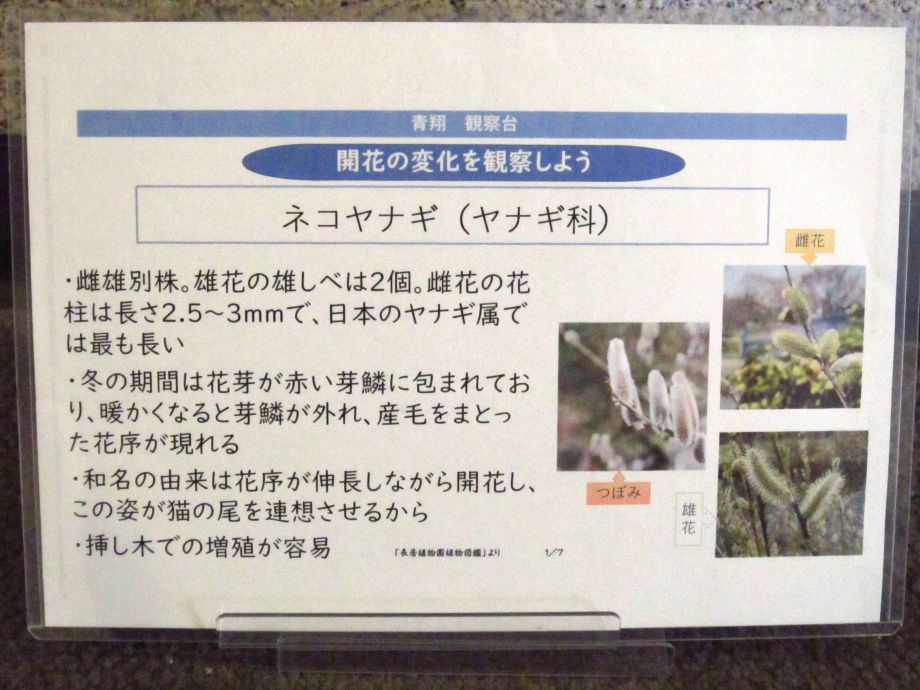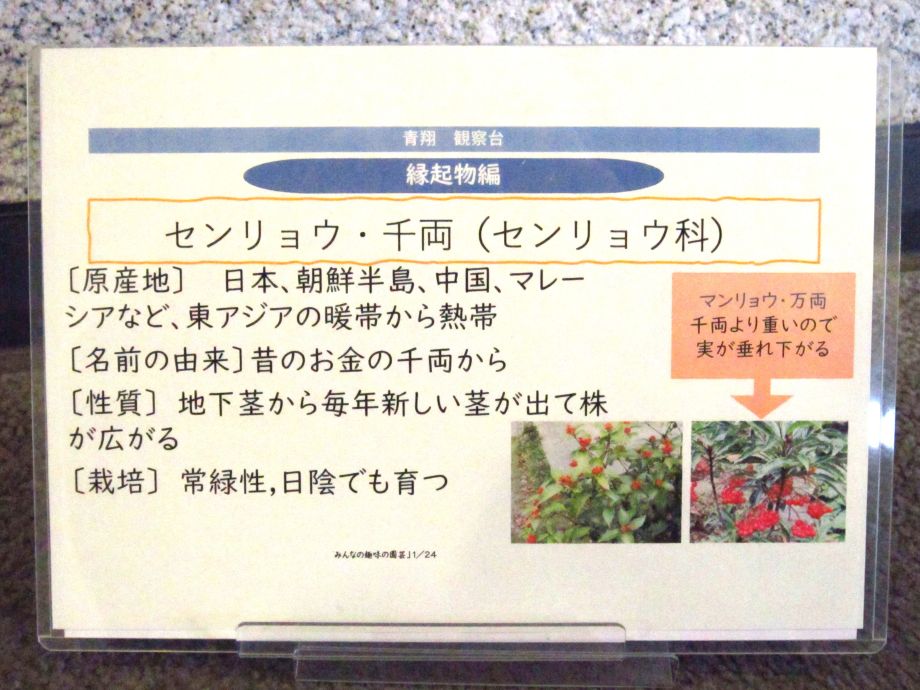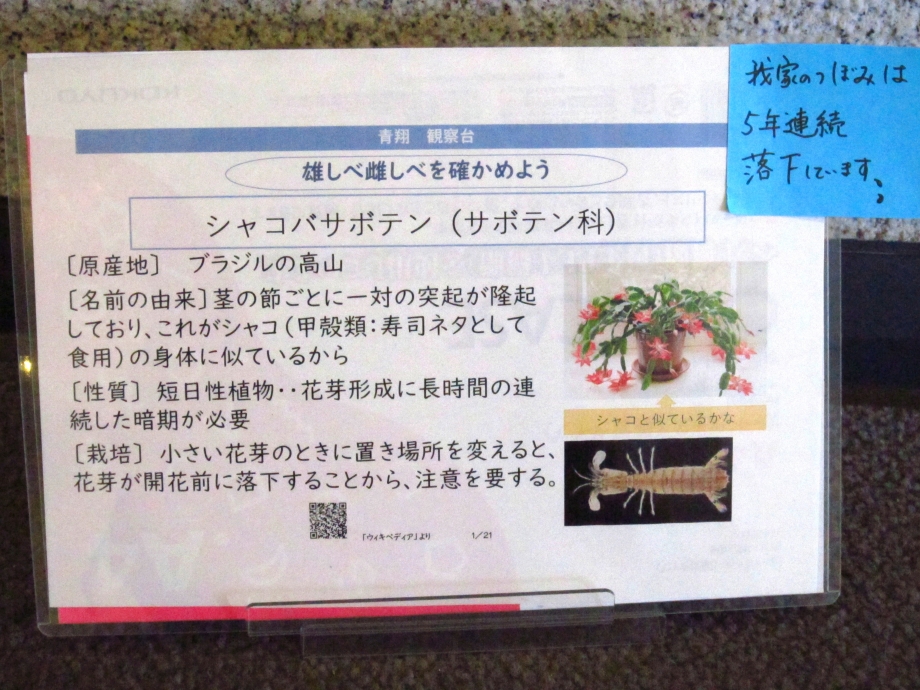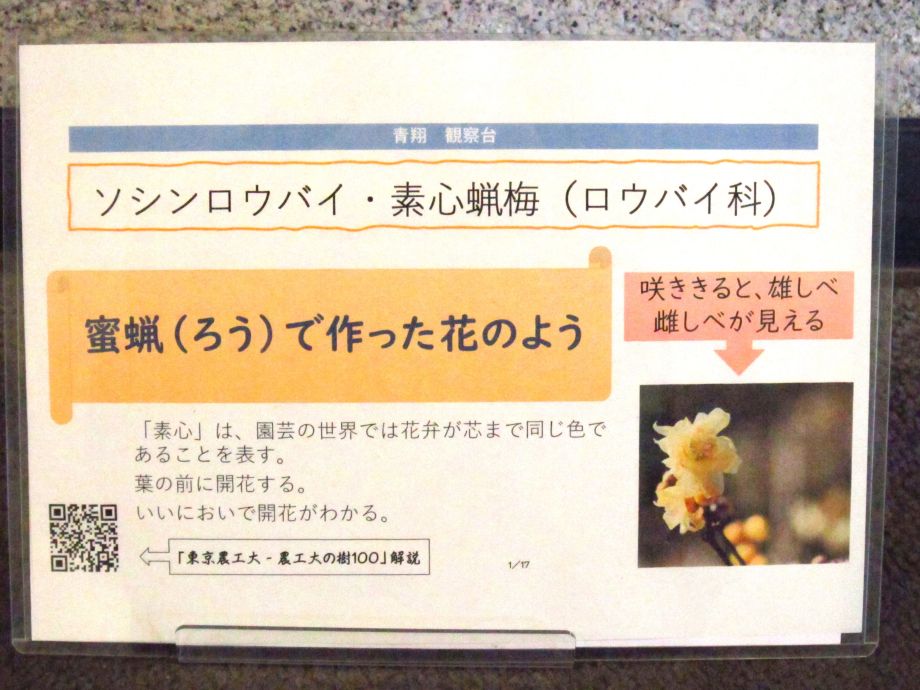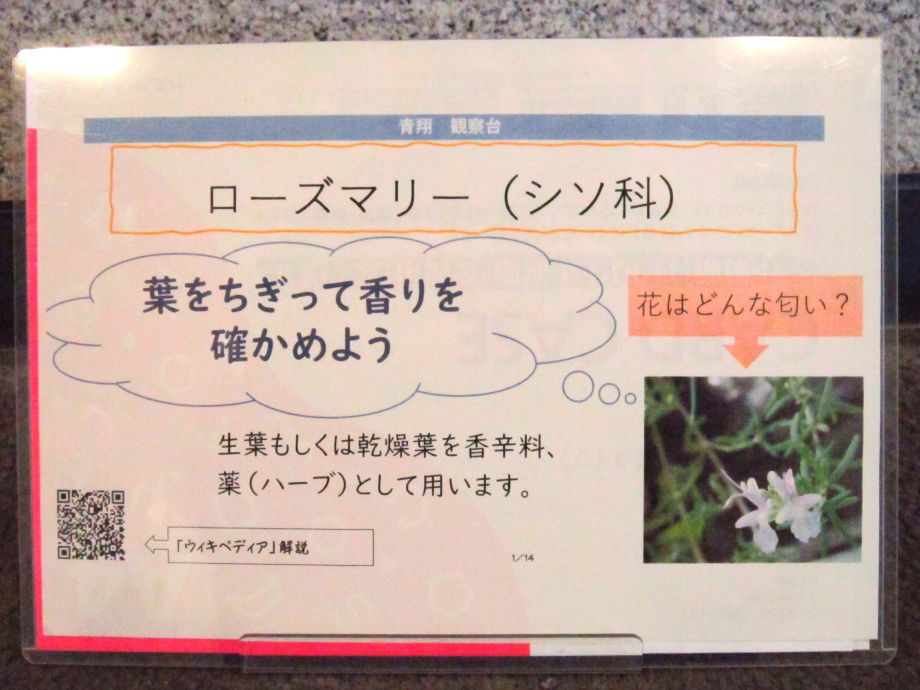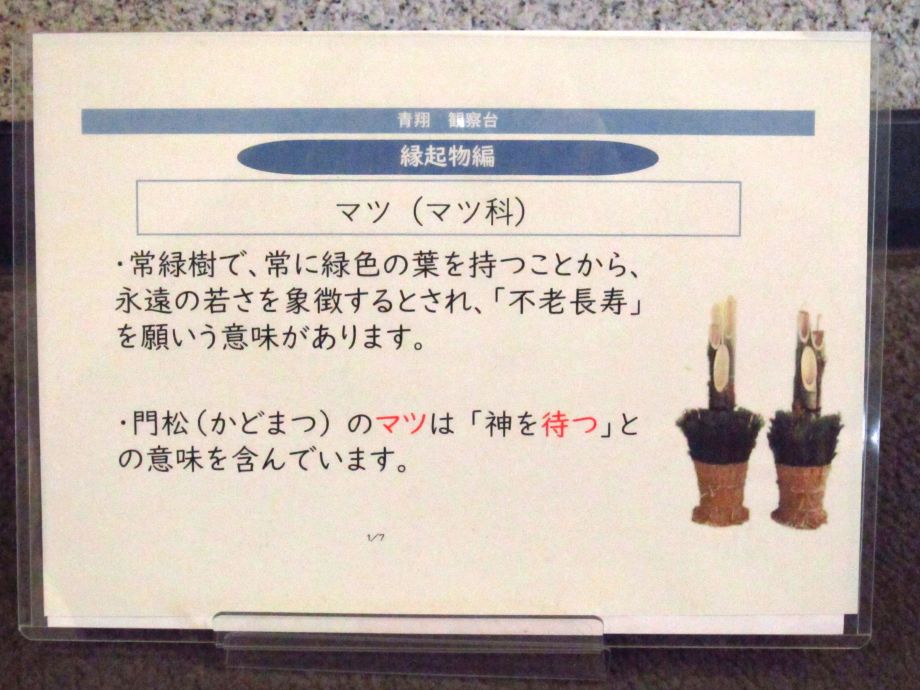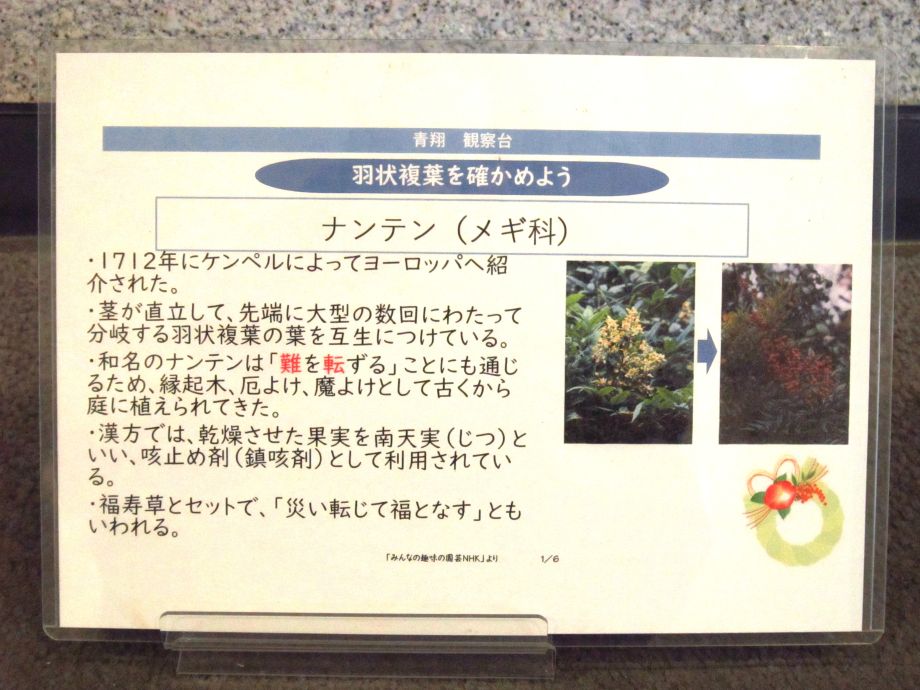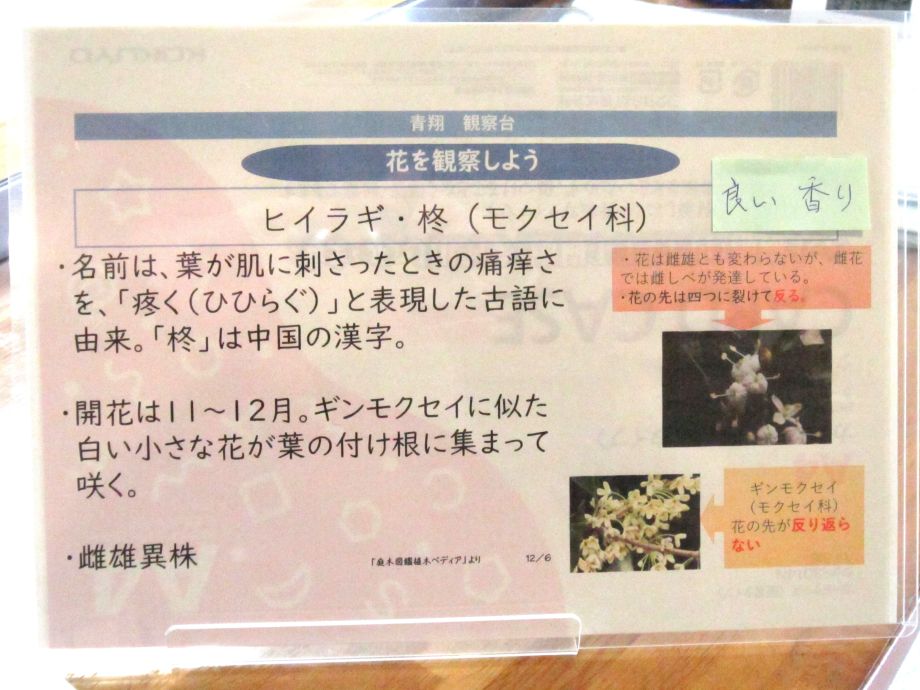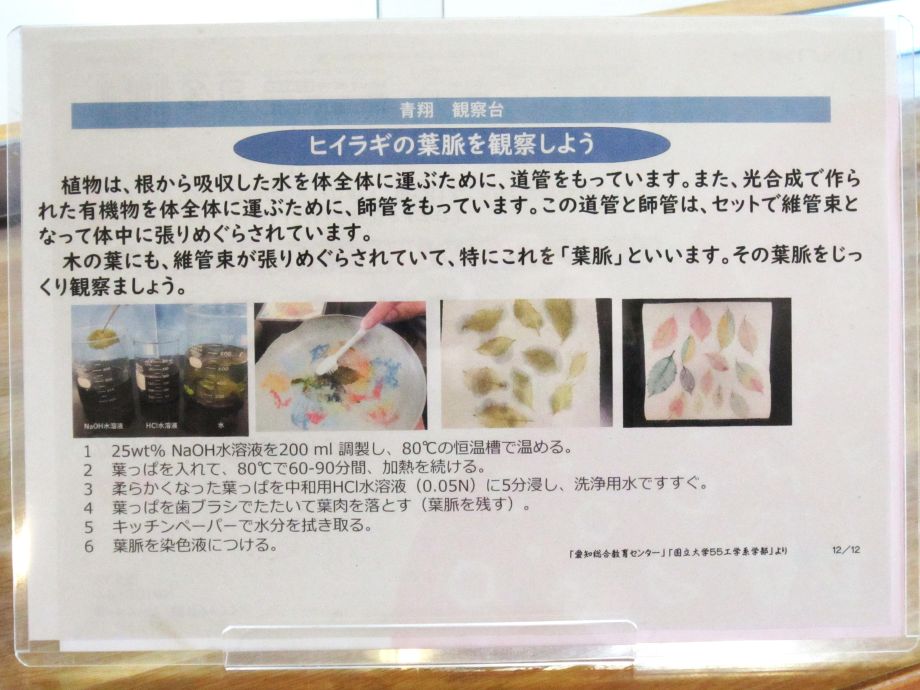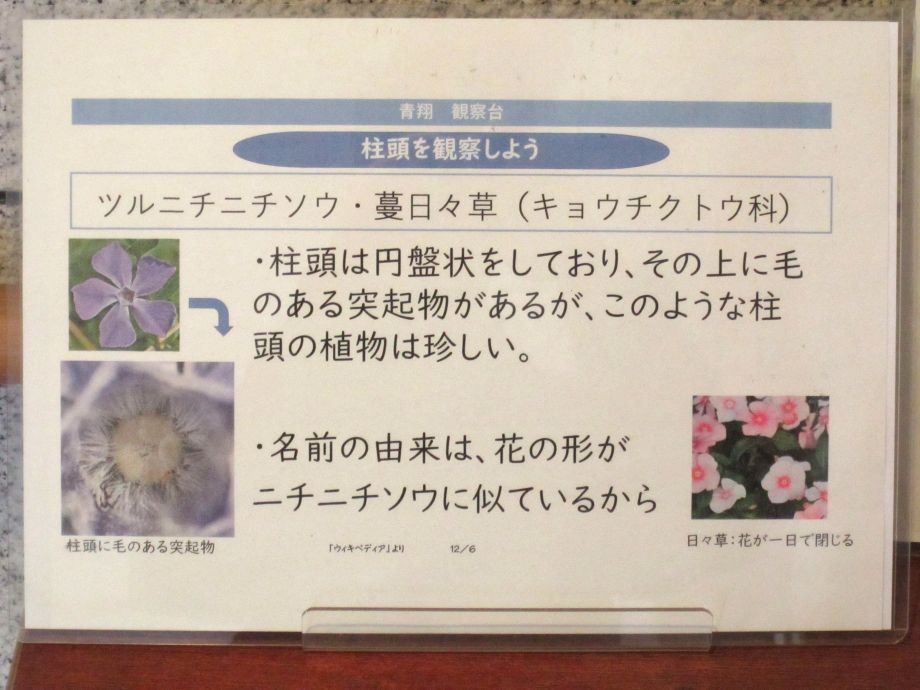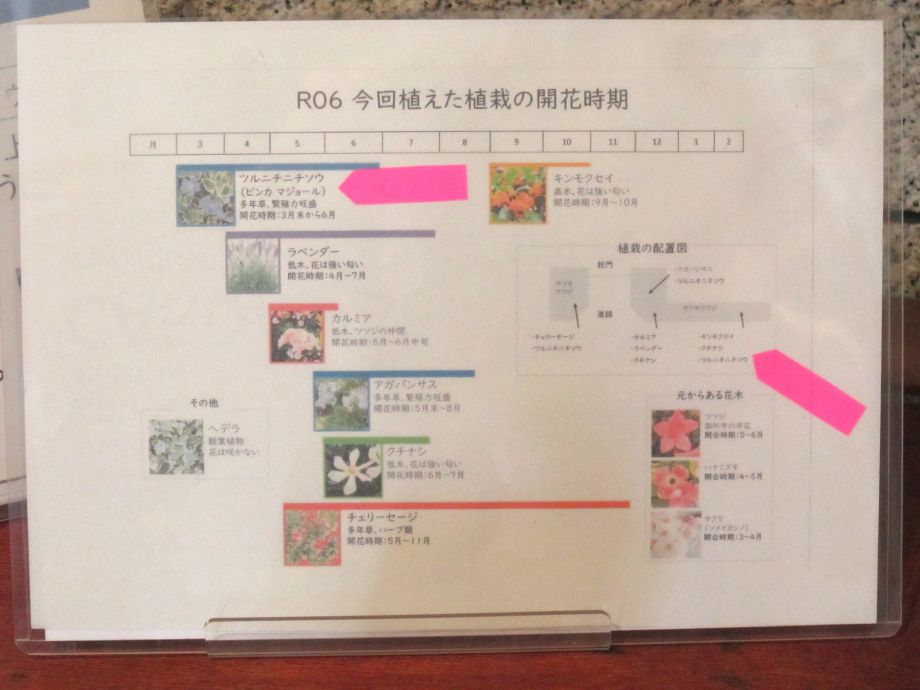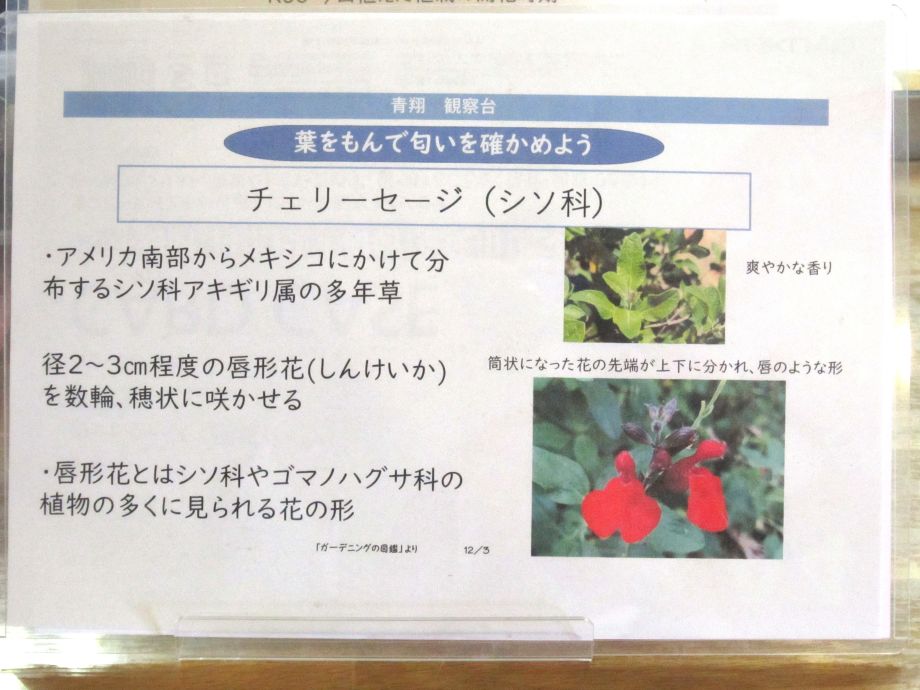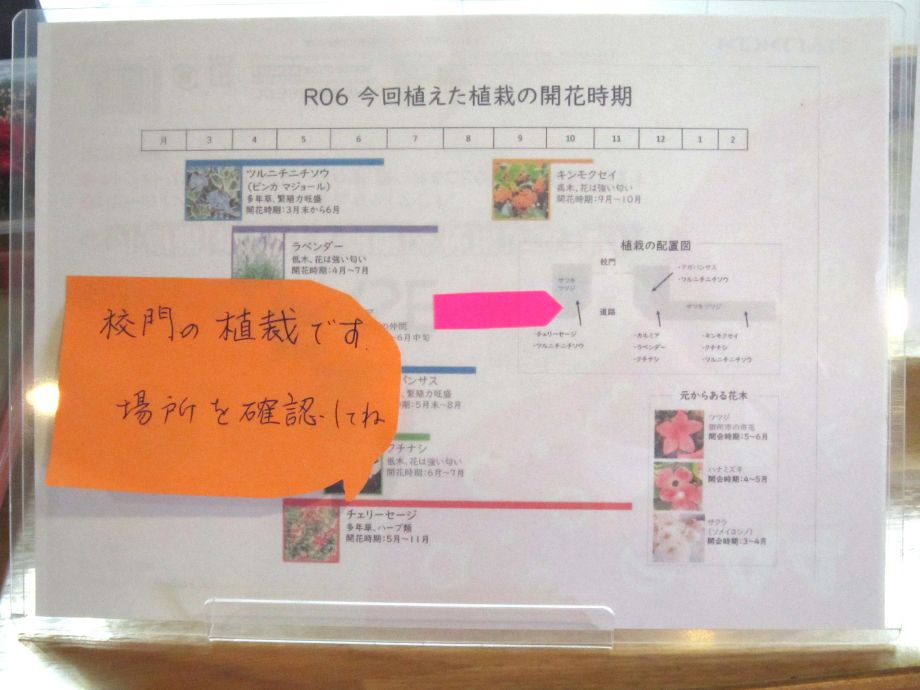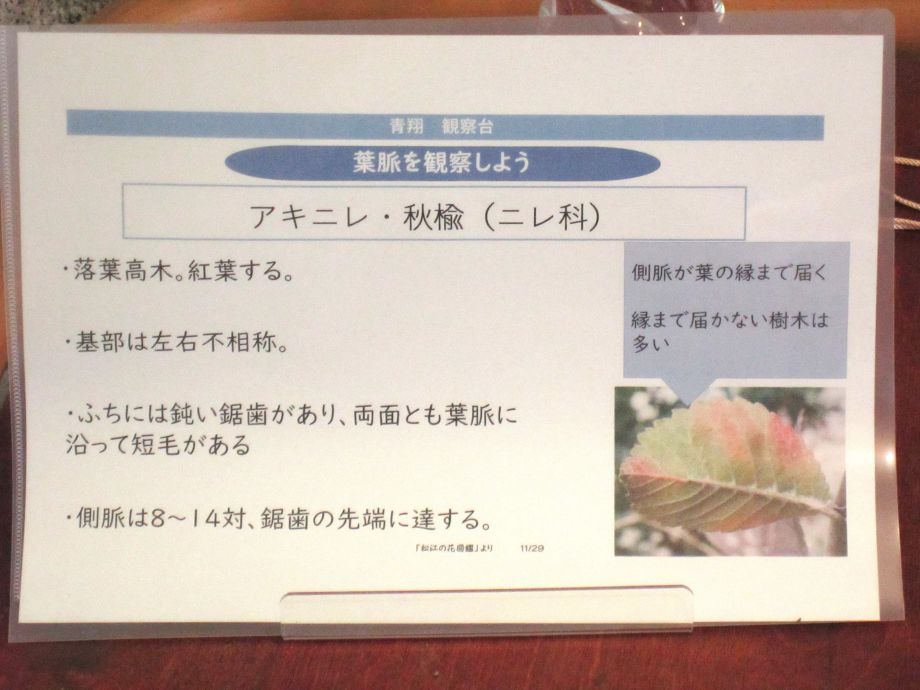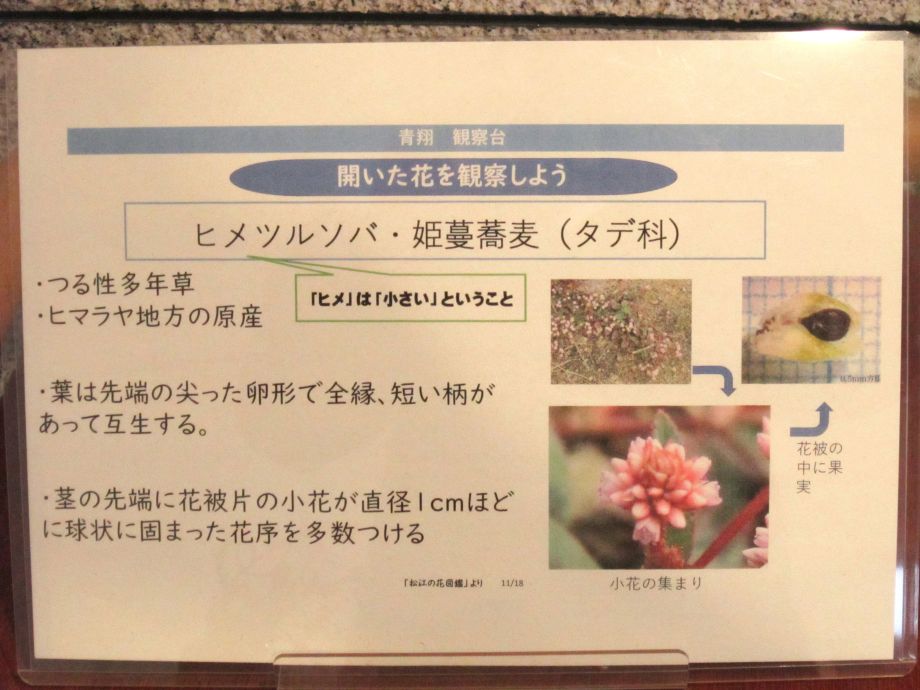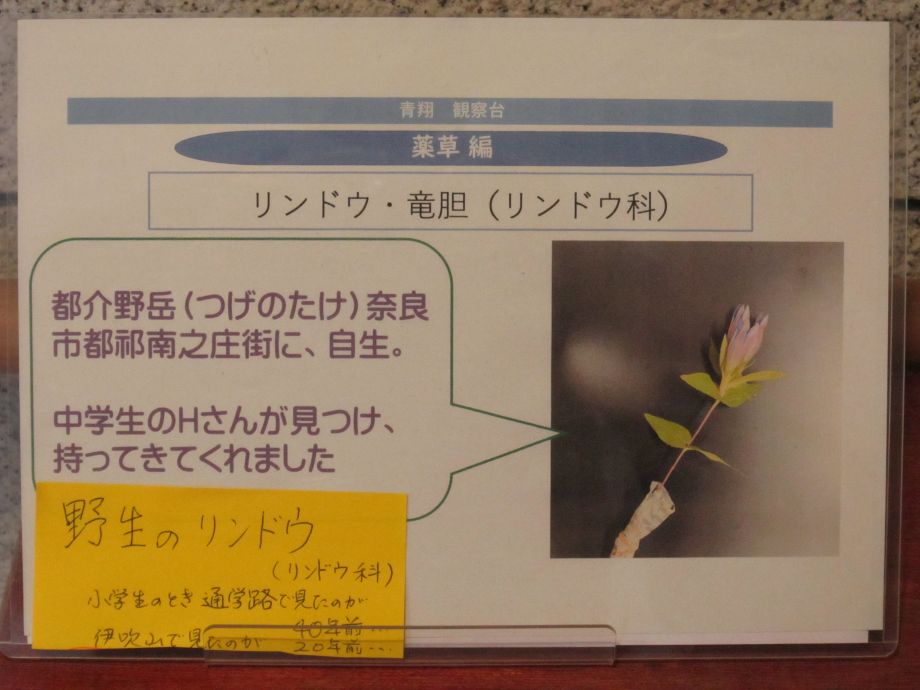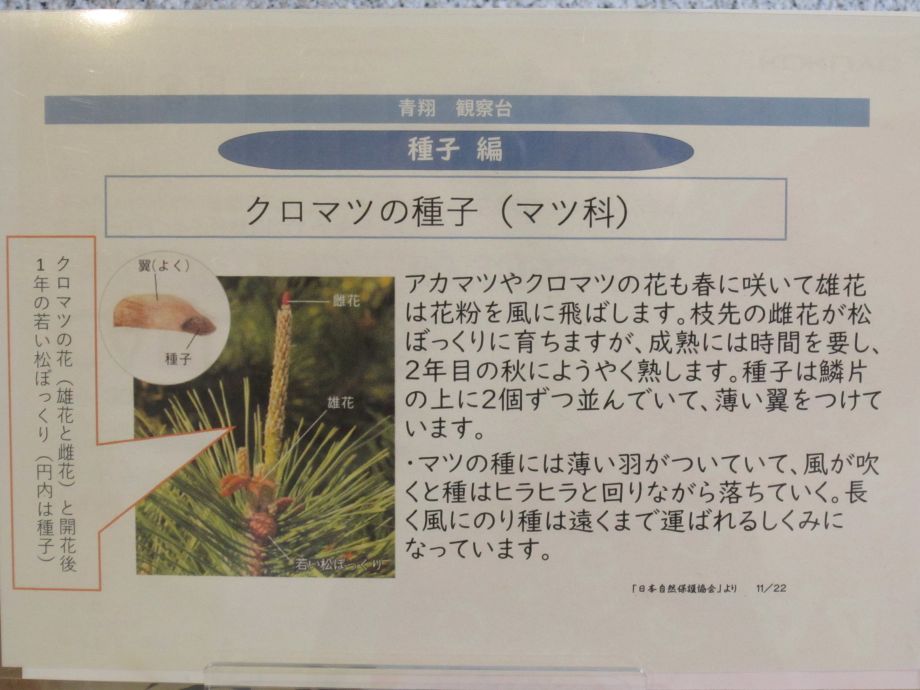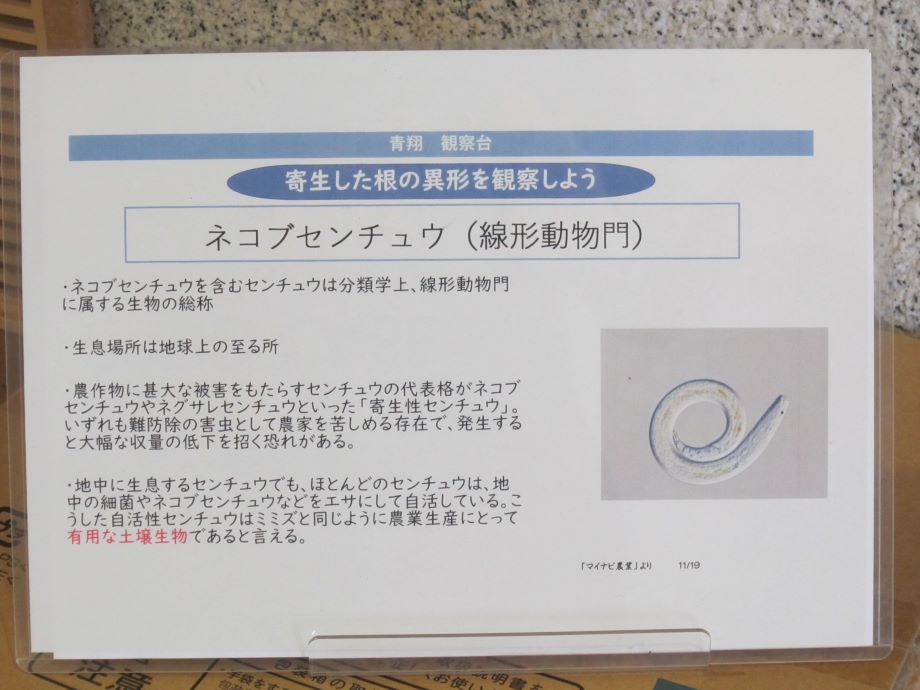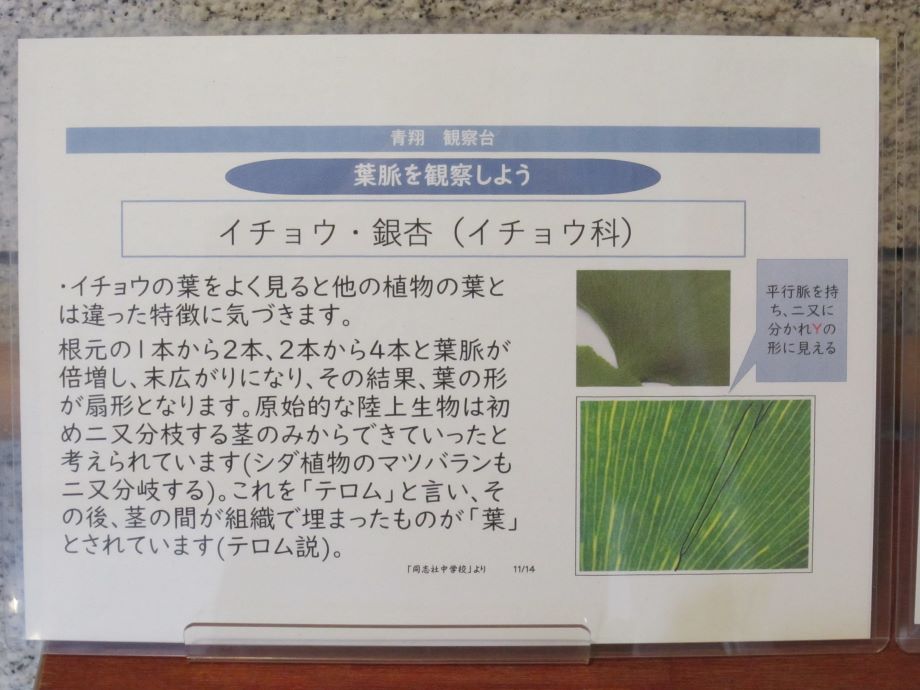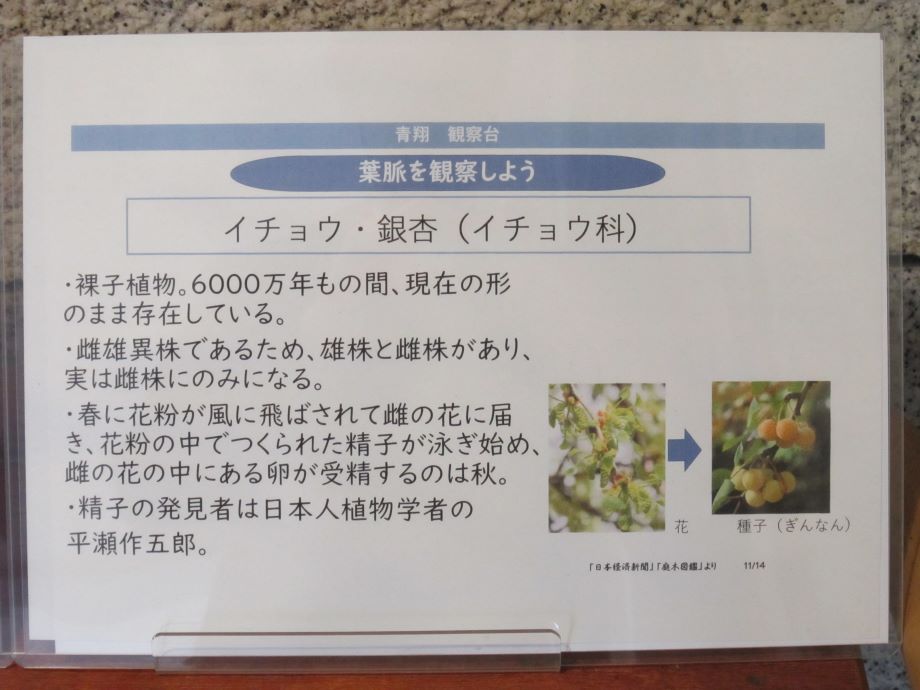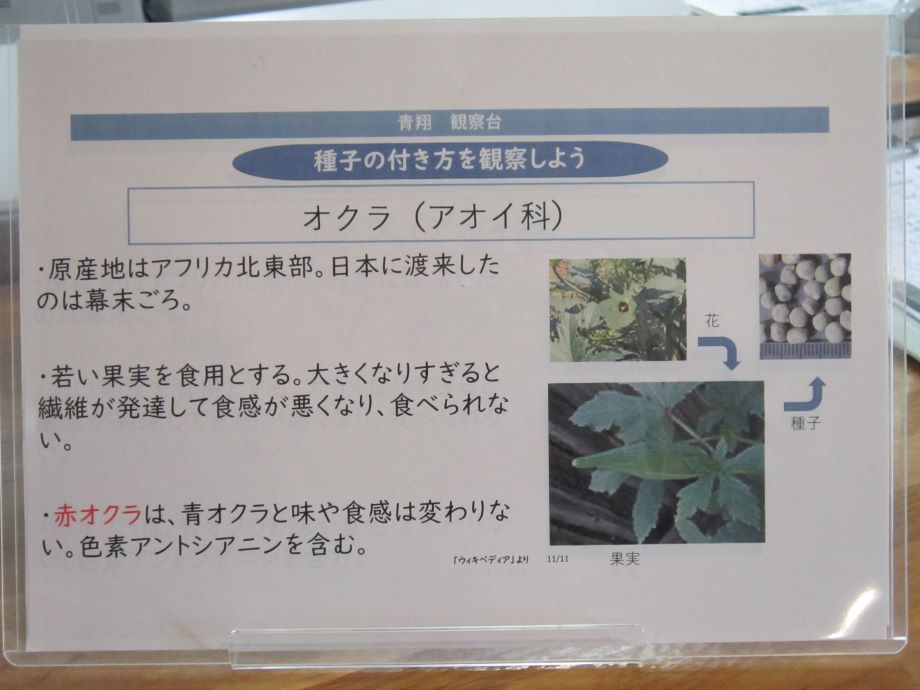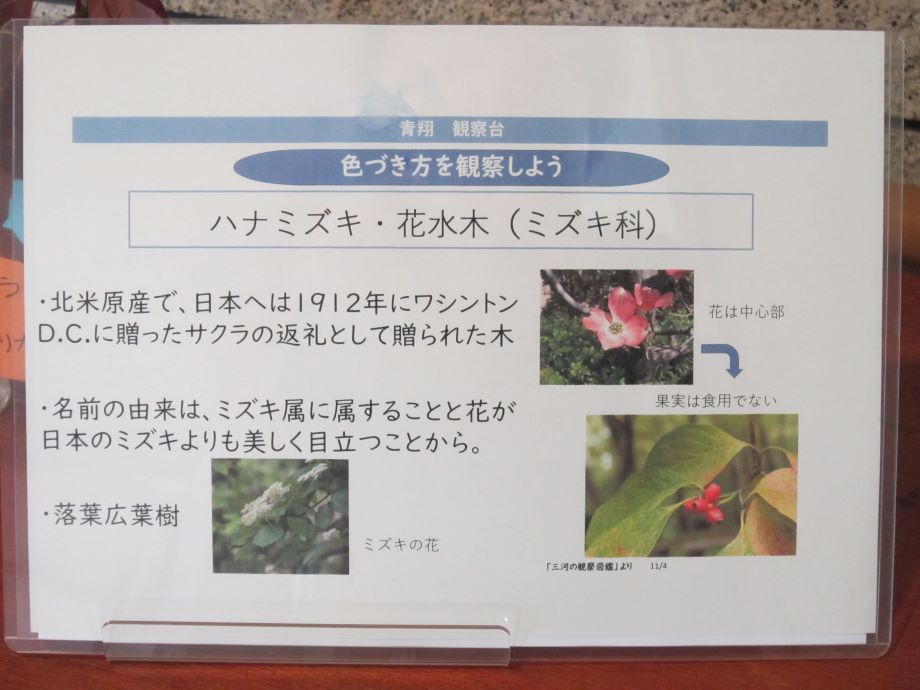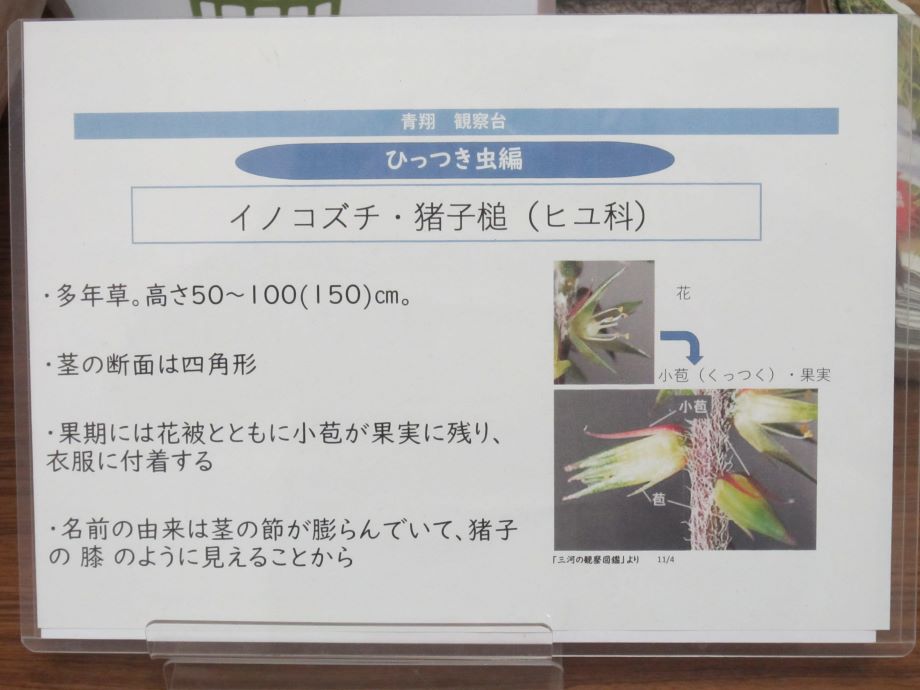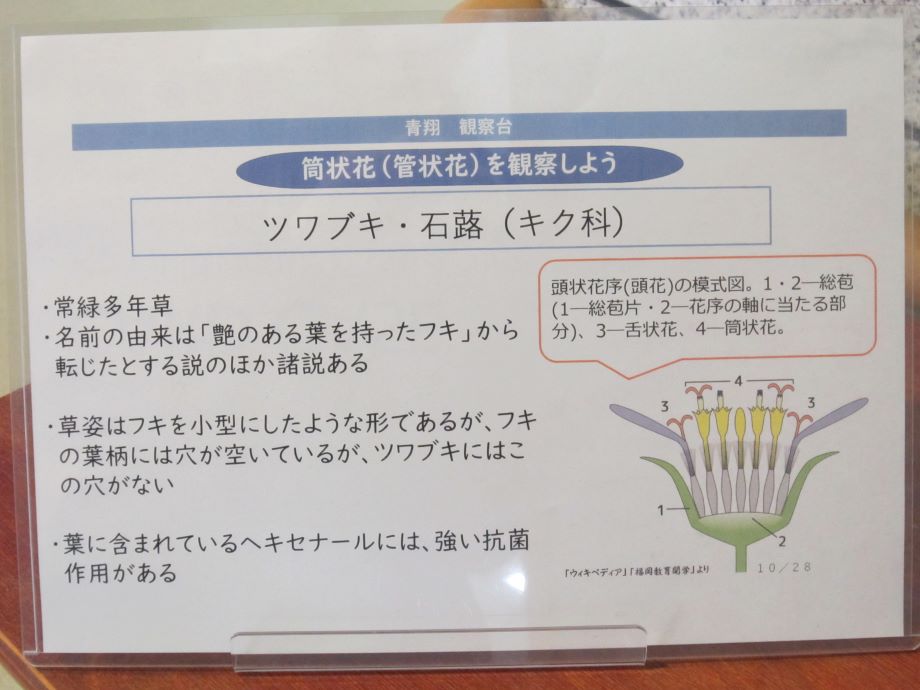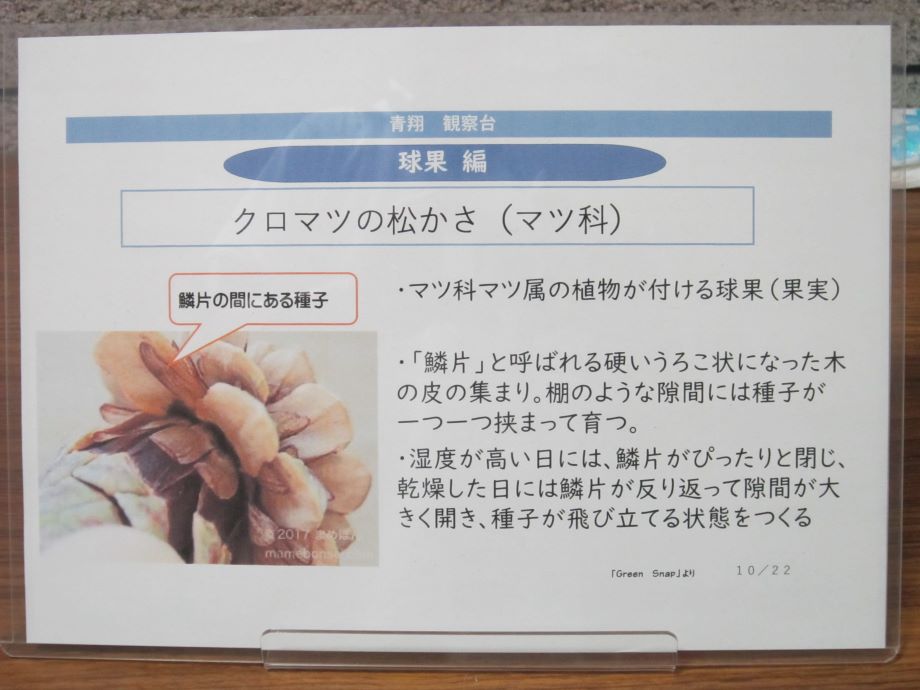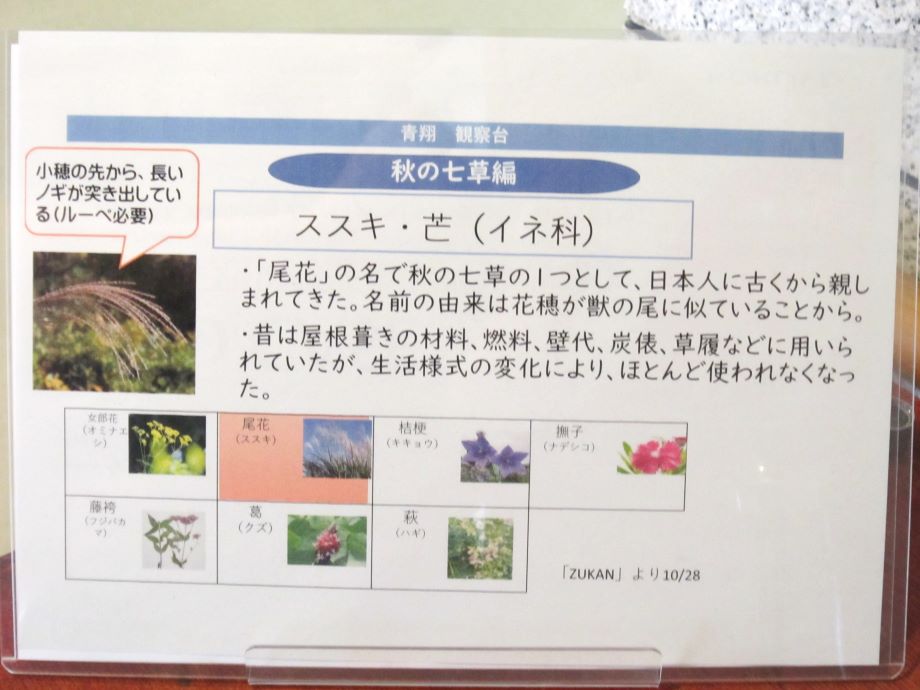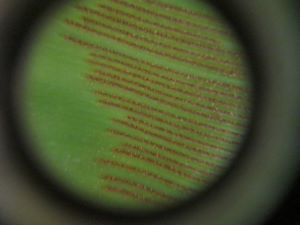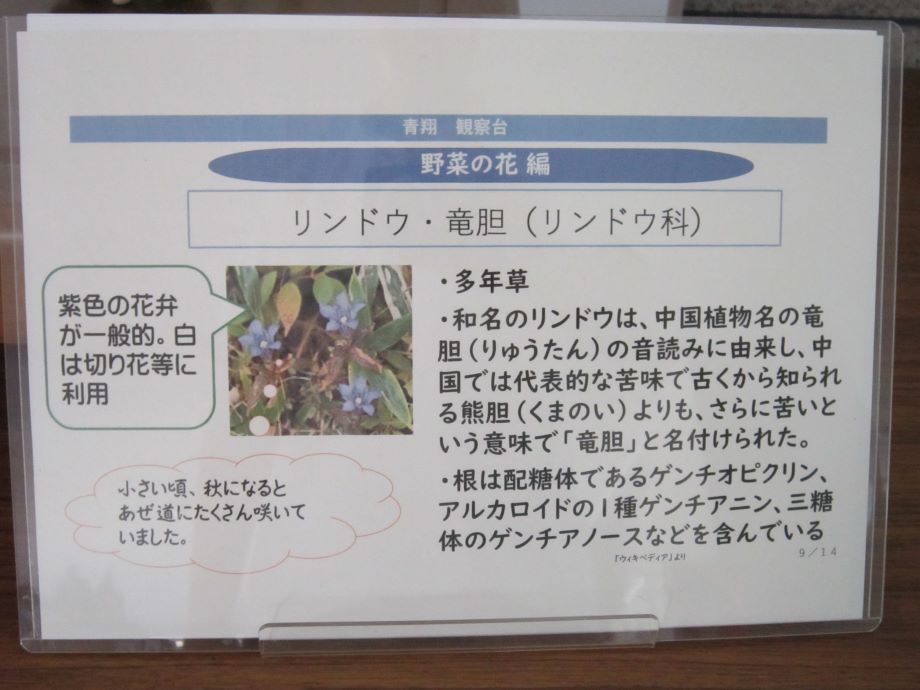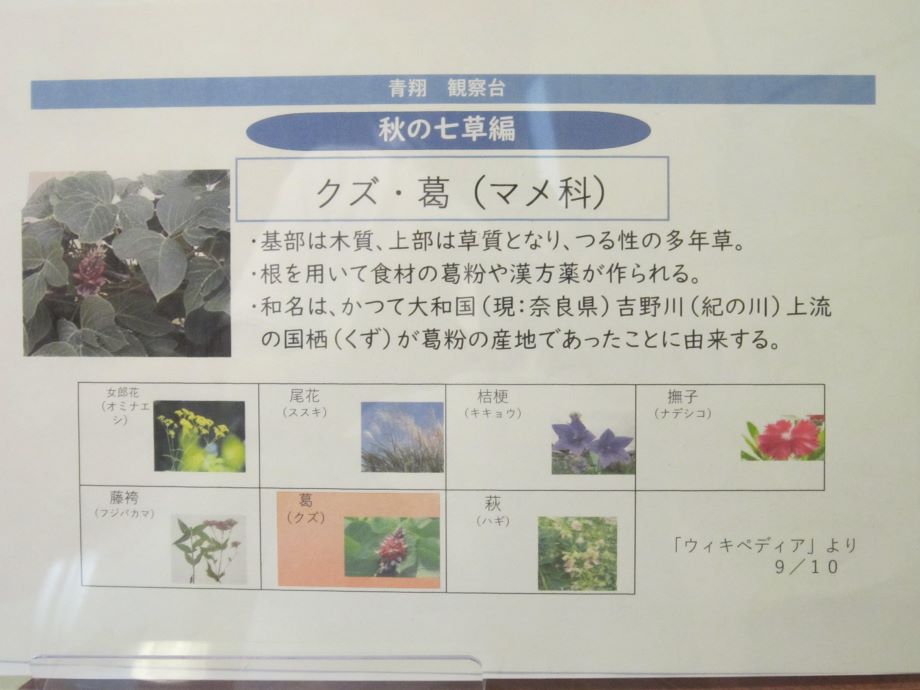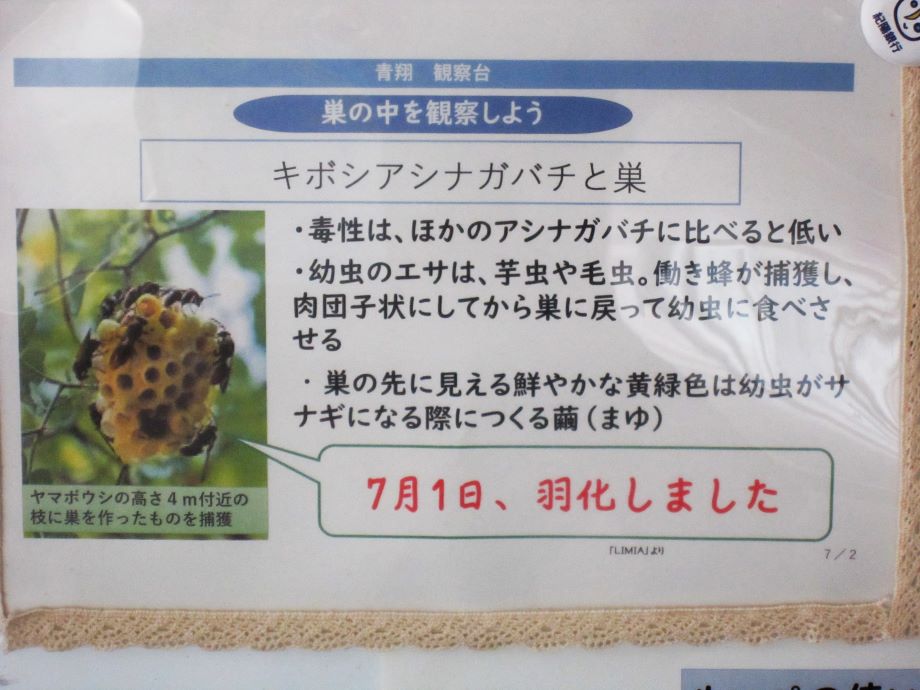青翔観察台
青翔観察台とは
・生物の先生である出口校長先生が、学校周辺で見られる植物や虫などの生き物、またそれらの巣などを、
時には生きたまま展示し、その生態等をじっくり観察できるようにしたものです。
解説には生き物の特徴やマメ知識が記されていて、観察のポイント等も知ることができます。
索引はこちら
ススキ・芒(イネ科) 10月7日



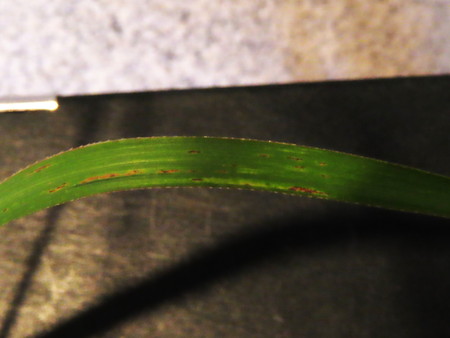
キンモクセイ・金木犀(モクセイ科) 10月7日


ナデシコ・撫子(ナデシコ科) 10月3日




ミズヒキ・水引(タデ科) 10月1日
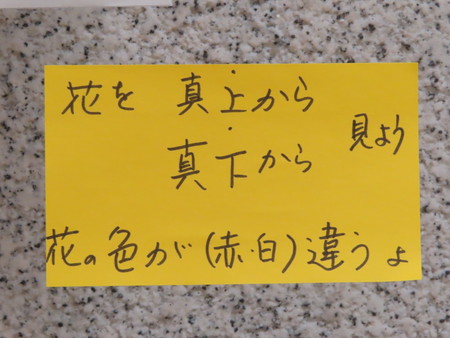



フジバカマ・藤袴(キク科) 10月1日




ヒガンバナ・彼岸花(ヒガンバナ科) 9月25日
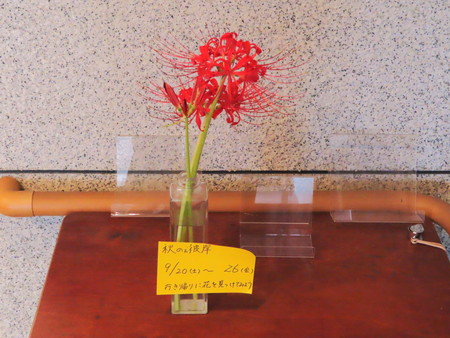
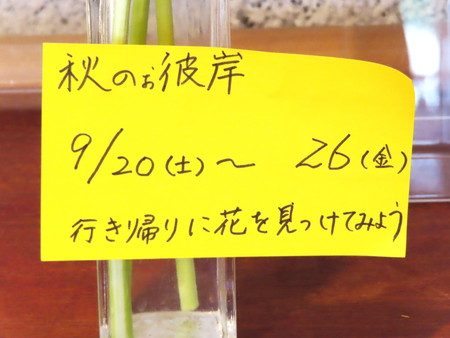




トクサ・砥草(トクサ科) 9月25日




サンショウモ・山椒藻(シダ植物) 9月25日


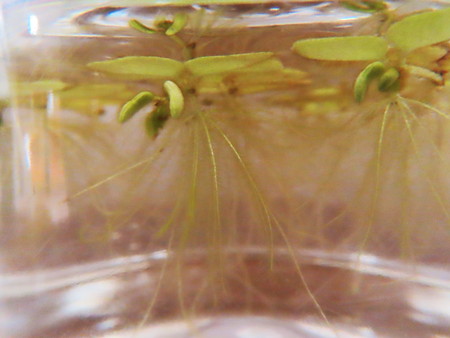

ヤハズソウ・矢筈草(マメ科) 9月18日




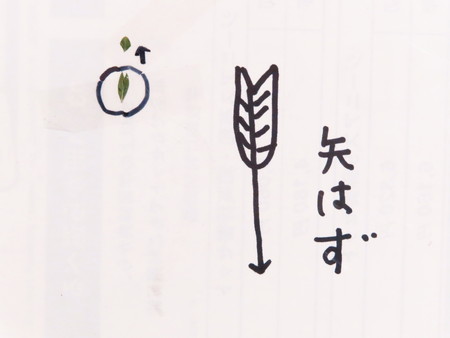
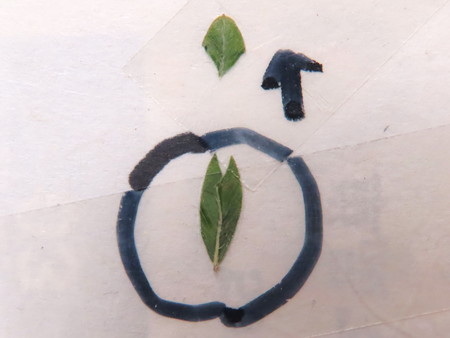
シソ・紫蘇(シソ科) 9月18日




ハギ・萩(マメ科) 9月8日




キク・菊(キク科) 9月4日

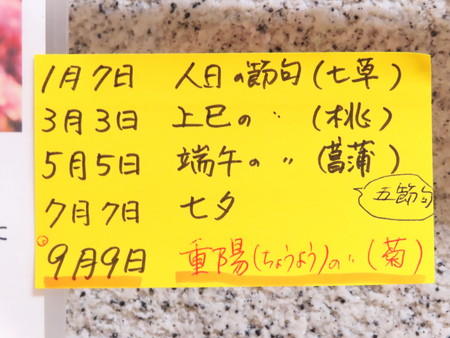


ヤブカラシ・藪枯らし(ブドウ科) 9月2日




ムクゲ・木槿(アオイ科) 9月1日




スズメバチの巣(スズメバチ科) 8月27日




ヘクソカズラ・屁糞葛(アカネ科) 8月27日




ソテツ・蘇鉄(ソテツ科) 8月21日
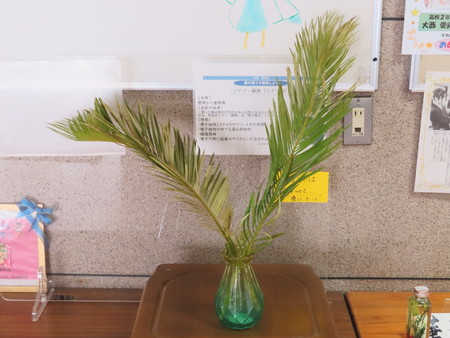
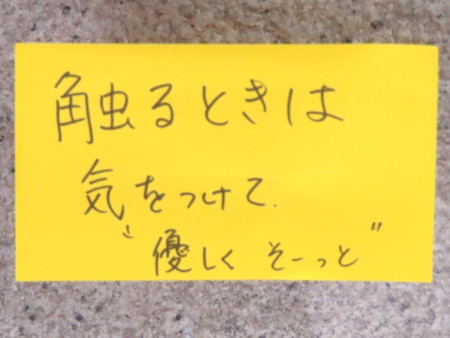
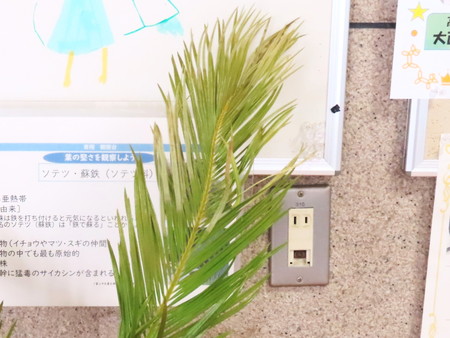



絹糸のうちわ 8月21日

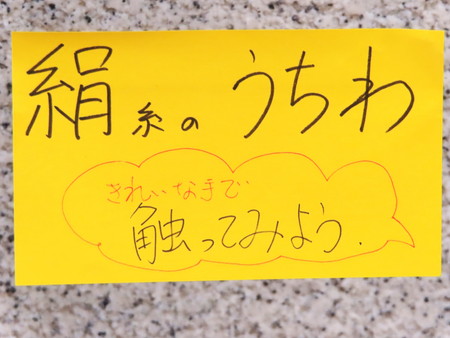


クマゼミの抜け殻(セミ科) 7月17日
※虫(ヌケガラ)注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら




アブラゼミの抜け殻(セミ科) 7月17日
※虫(ヌケガラ)注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら




ヒメツルソバ・姫蔓蕎麦(タデ科) 7月10日




ハマキガの幼虫・葉巻蛾(ハマキガ科) 7月7日
7月15日、羽化しました。





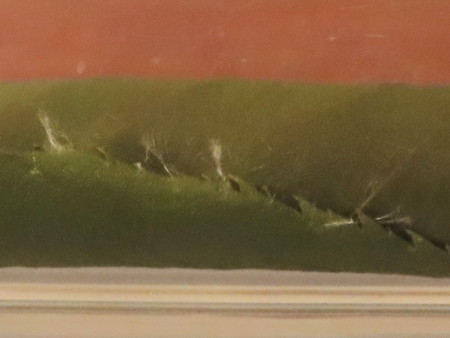
サルスベリ(ミソハギ科) 7月7日
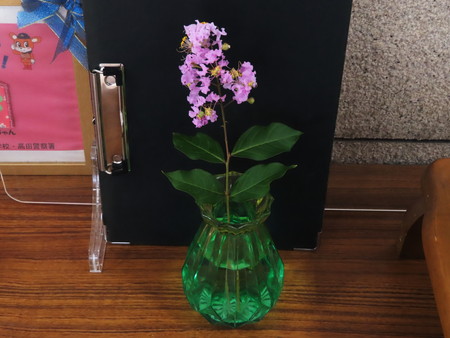
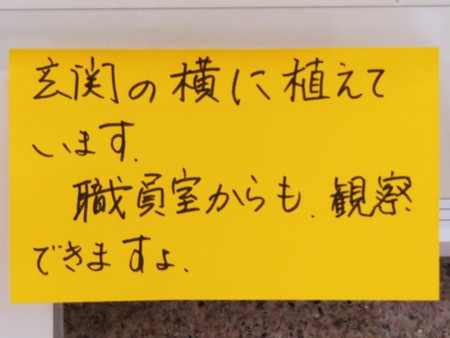



ニイニイゼミ(セミ科) 7月3日
※虫(ヌケガラ)注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら




ハイビスカス(アオイ科) 7月3日




タンチョウアリウム・丹頂アリウム(ヒガンバナ科) 6月30日




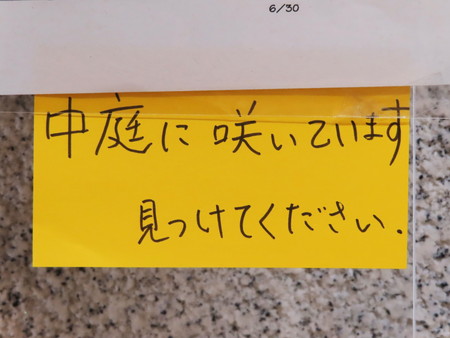
ノコギリクワガタ(クワガタムシ科) 6月25日
※虫注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら






ネジバナ(ラン科) 6月25日




クチナシ・梔(アカネ科) 6月24日
こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。


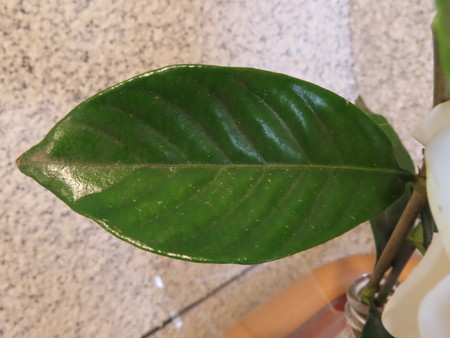



アガパンサス(ヒガンバナ科) 6月20日
こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。
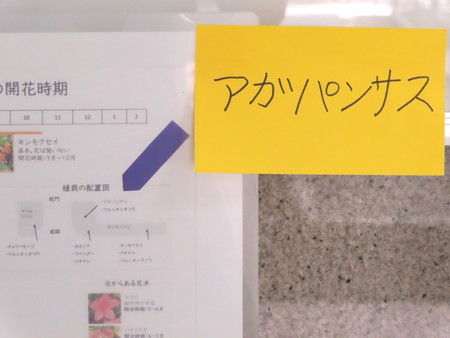
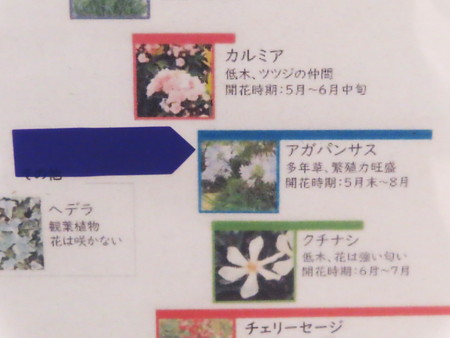




オオタニワタリ・大谷渡(チャセンシダ科) 6月20日
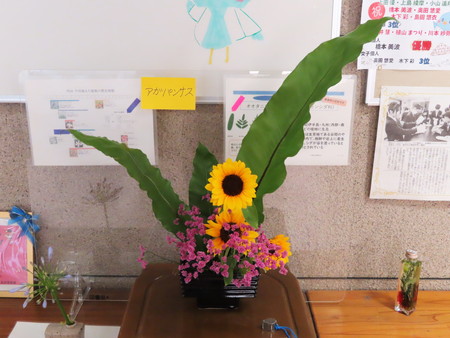





ホタルブクロ・蛍袋(キキョウ科) 6月20日




クビアカツヤカミキリ 6月20日
※虫注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら


クロカキ・黒柿(セリ科) 6月17日




ニワセキショウ(アヤメ科) 6月16日




ウイキョウ(セリ科) 6月16日
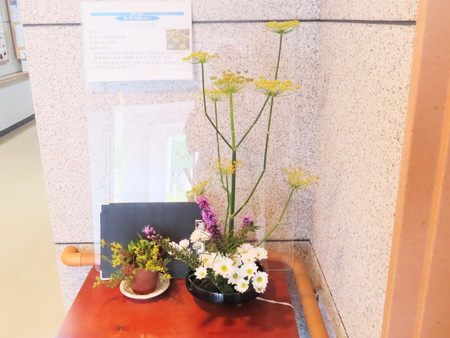



ユウゲショウ(アカバナ科) 6月11日




タイトゴメ・大唐米(ベンケイソウ科) 6月11日




チーゼル(マツムシソウ科) 6月10日




ラミーカミキリ(カミキリムシ科) 6月4日
※注意!虫の写真が現れます。




ウラジロチチコグサ・裏白父子草(キク科) 6月4月




ユキノシタ・雪の下(ツツジ科) 5月27日


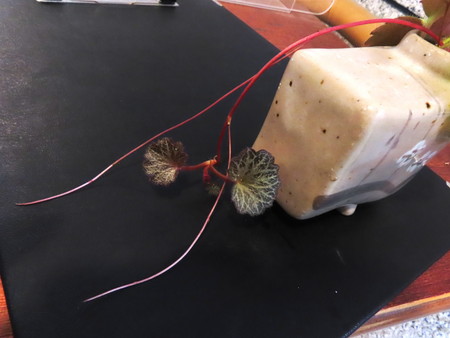



ドクダミ(ドクダミ科) 5月27日




カルミヤ(ツツジ科) 5月27日
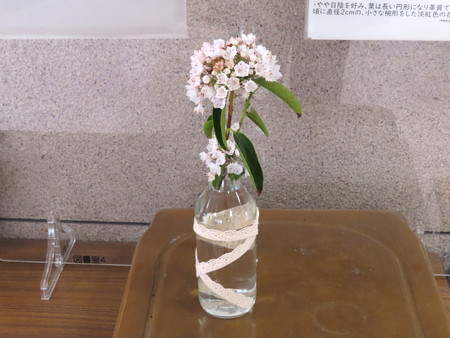



ヒメコバンソウ(イネ科) 5月19日


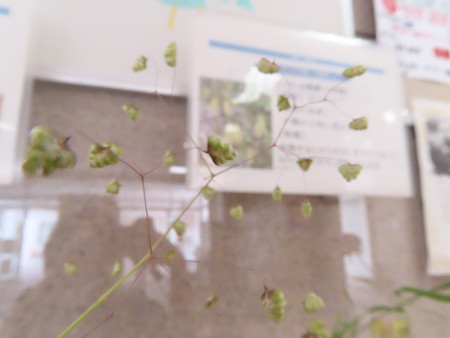

コバンソウ・小判草(イネ科) 5月19日




ムラサキツユクサ(ツユクサ科) 5月19日




クビアカツヤカミキリの幼虫 5月15日
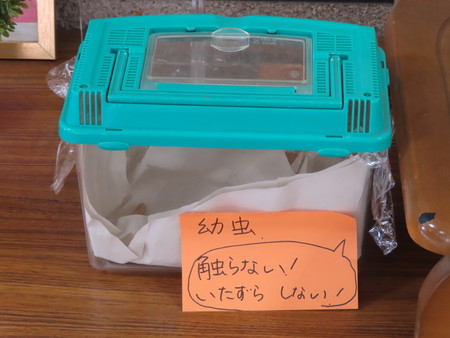
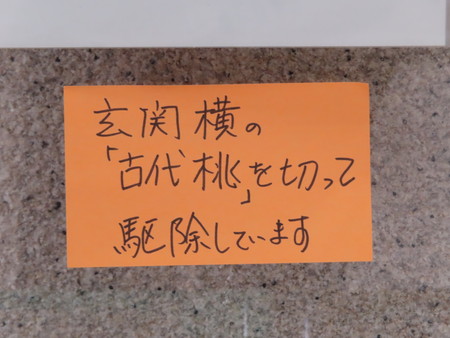

シャクヤク・芍薬(ボタン科) 5月8日

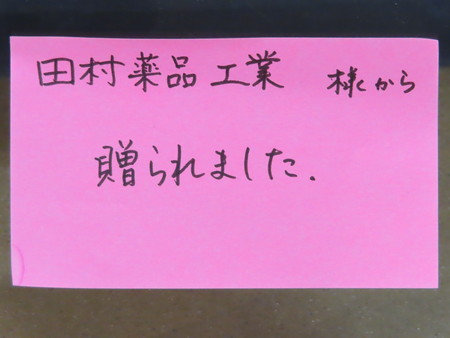




コリアンダー(セリ科) 5月8日




コチョウラン・胡蝶蘭(ラン科) 5月8日

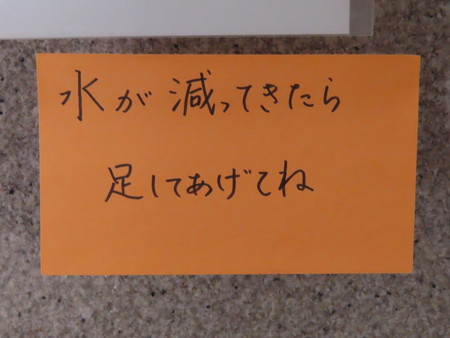

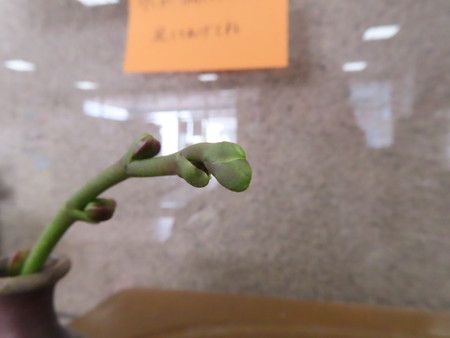
シロツメクサ(マメ科) 5月7日
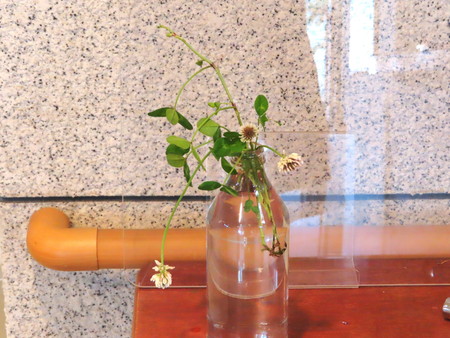



ラベンダー(シソ科) 4月25日
こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。

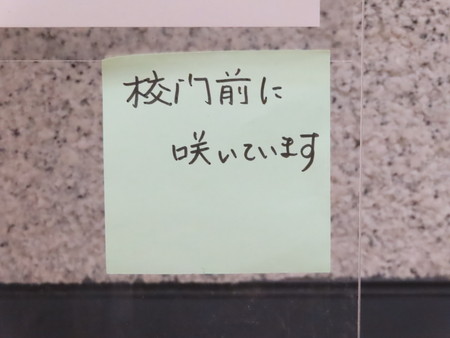
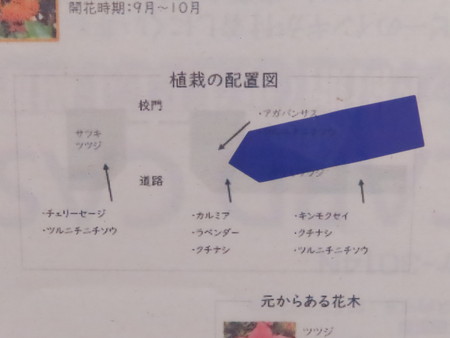



ハナミズキ・花水木(ミズキ科) 4月25日



ジャガ・射干(アヤメ科) 4月25日

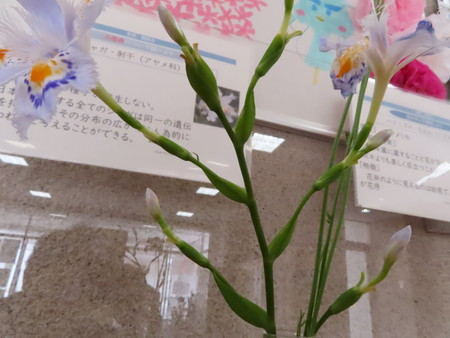


マツバウンラン(オオバコ科) 4月23日




ノウタケ・脳茸(ハラタケ科) 4月23日

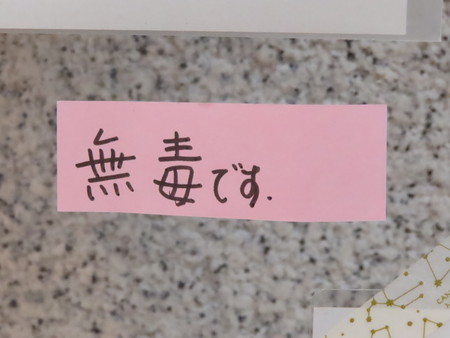


ヤハズエンドウ・矢筈豌豆(マメ科) 4月21日

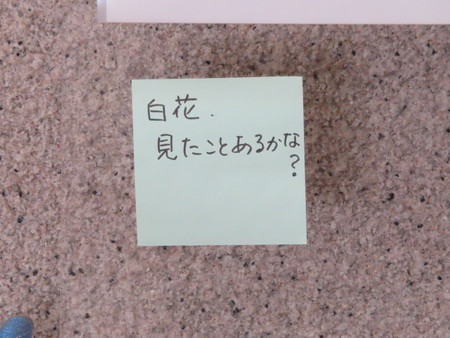




ツバキ・椿(ツバキ科) 4月18日

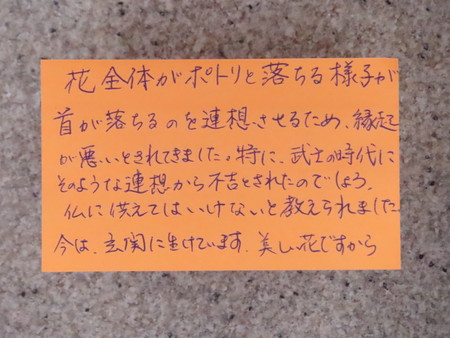




オンシジウム(ラン科) 4月16日




ストック(アブラナ科) 4月16日



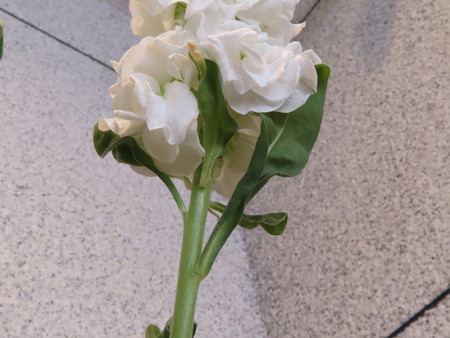


ゲンゲ・紫雲英(マメ科) 4月14日

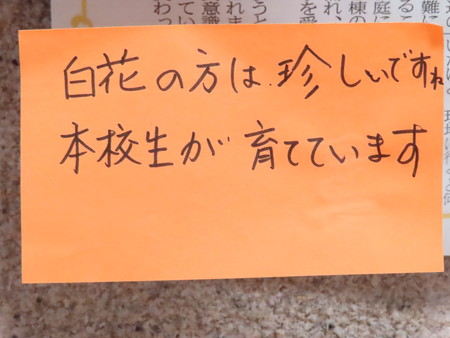


ヒメオドリコソウ(シソ科) 4月7日




ホトケノザ(シソ科) 4月3日




魚の化石 3月28日
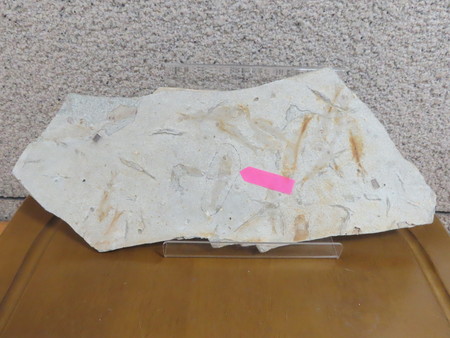



アルストロメリア(ユリズイセン科) 3月28日




ユキヤナギ・雪柳(バラ科) 3月24日
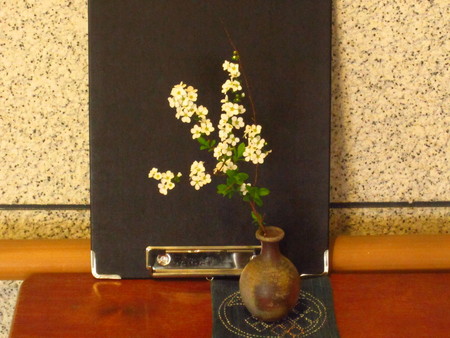



ウメ・梅(バラ科) 3月11日






ミツマタ・三椏(ジンチョウゲ科) 3月11日




ストレリチア(ゴクラクチョウカ科) 3月5日




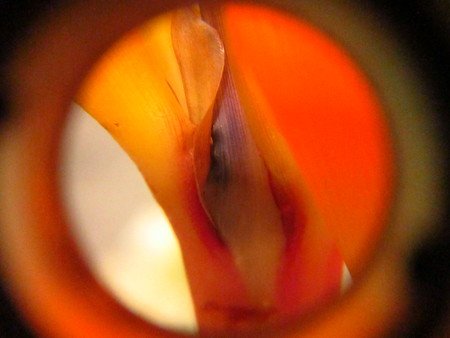



タコノアシ・蛸の足(タコノアシ科) 2月26日



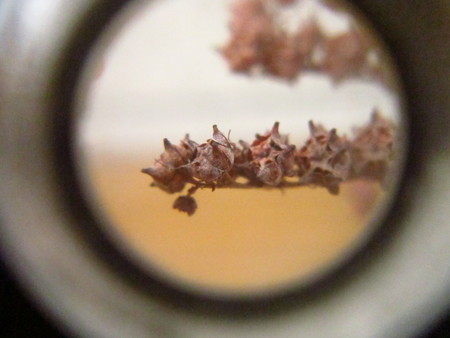
キンギョソウ・金魚草(オオバコ科) 2月21日




アオモジ・青文字(クスノキ科) 2月20日






セッカエニシダ・石化エニシダ(マメ科) 2月18日

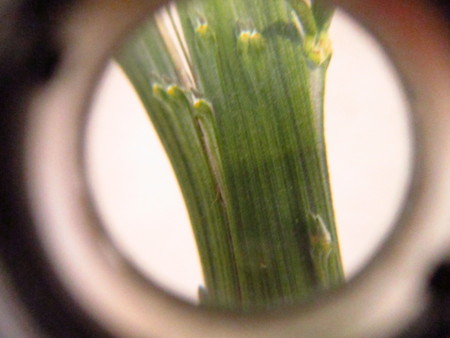




サザンカ・山茶花(ツバキ科) 2月12日

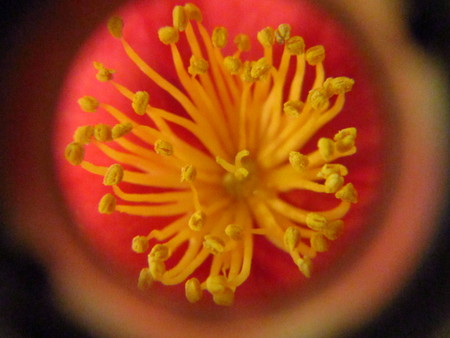
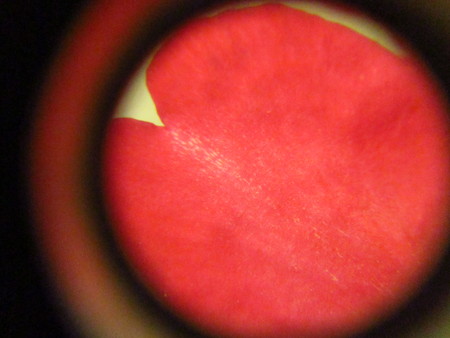
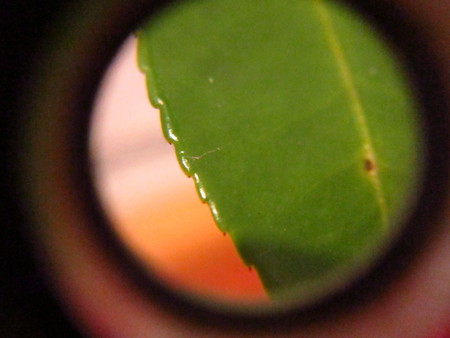
モミジバフウの実(フウ科) 2月10日




ヒイラギ(モクセイ科) 2月1日




ネコヤナギ(ヤナギ科) 1月31日



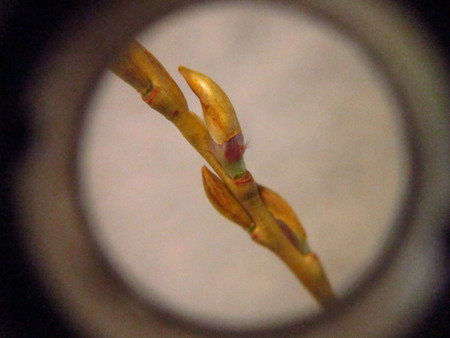
センリョウ・千両(センリョウ科) 1月27日




シャコバサボテン(サボテン科) 1月21日






ソシンロウバイ・素心蝋梅(ロウバイ科) 1月17日


ローズマリー(シソ科) 1月15日


モクレン・木蓮(モクレン科) 1月10日




・1月27日、開花しました。



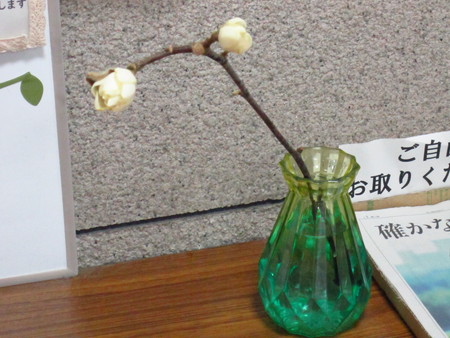
マツ(マツ科) 1月7日


ナンテン(メギ科) 1月6日


ヒイラギ・柊(モクセイ科) 12月13日


ヒイラギの葉脈 12月12日
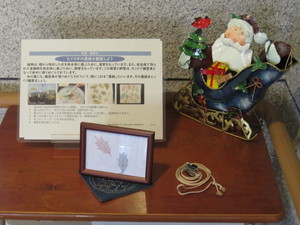




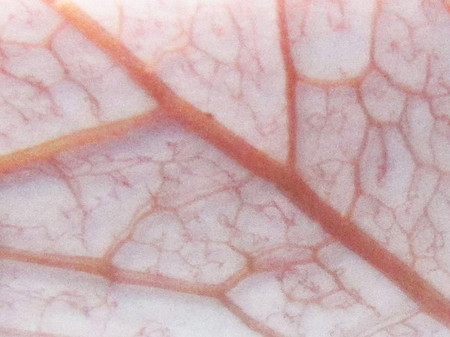
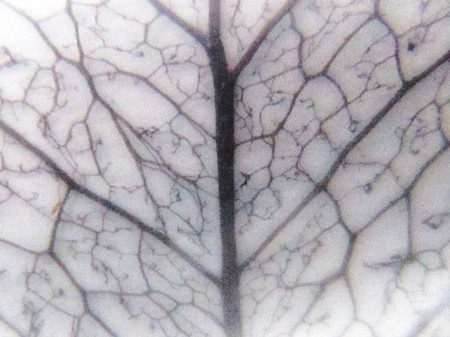
ツルニチニチソウ・蔓日々草(キョウチクトウ科) 12月6日
こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。




チェリーセージ(シソ科) 12月3日
こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。




アキニレ・秋楡(ニレ科) 11月29日



ヒメツルソバ・姫蔓蕎麦(タデ科) 11月28日



リンドウ・竜胆(リンドウ科) 11月25日
・校長先生が昇降口に以前展示されていたリンドウ(9月14日)の解説の中に
「小さい頃、秋になるとあぜ道にたくさん咲いていました。」と
書いてあったのを見た当校の中学生が
登下校の道で見つけてきてくれました。



クロマツの種子(マツ科) 11月22日
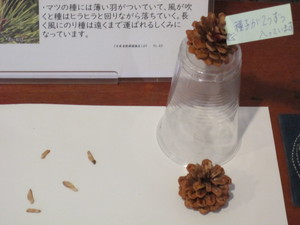
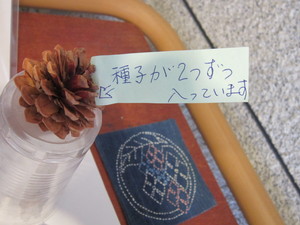


ハイビスカス(アオイ科) 11月20日




ネコブセンチュウ(線形動物門) 11月19日

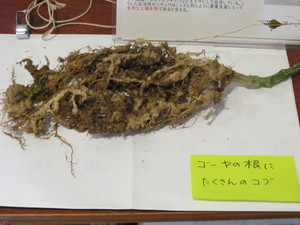

イチョウ・銀杏(イチョウ科) 11月14日



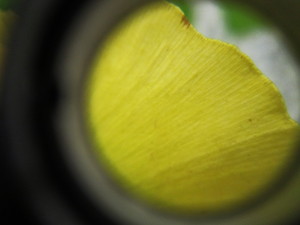
オクラ(アオイ科) 11月11日






ハナミズキ・花水木(ミズキ科) 11月6日
・ハナミズキ



・サクラ
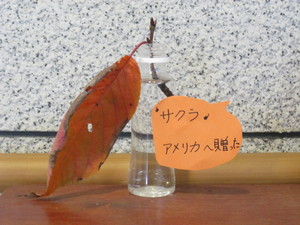


くっつきむし・イノコズチ 11月1日(ポップ等更新しました)



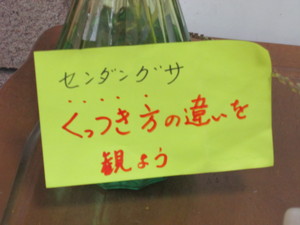
アンスリウム・アンドレアナム(サトイモ科) 10月30日



ツワブキ・石蕗(キク科) 10月28日


リンドウ・竜胆(リンドウ科) 10月24日
・9月14日にも展示がありましたが、今回のリンドウは開花直前です。
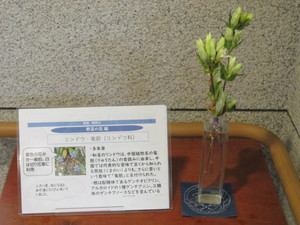


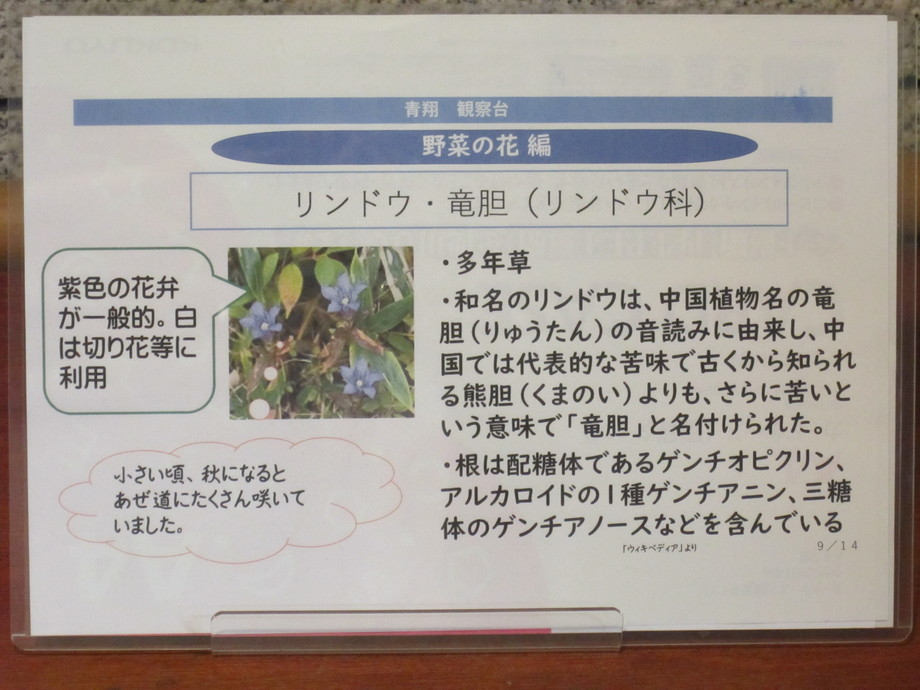
クロマツの松かさ(マツ科) 10月22日
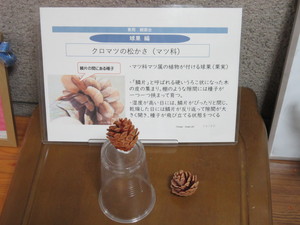


・下の写真の松かさは、向かって右側にある方が霧吹きで水をかけて約2時間後のものです。


ススキ・芒(イネ科) 10月21日(10月24日更新)

・10月24日、花穂が咲きました。


キンモクセイ・金木犀(モクセイ科) 10月17日

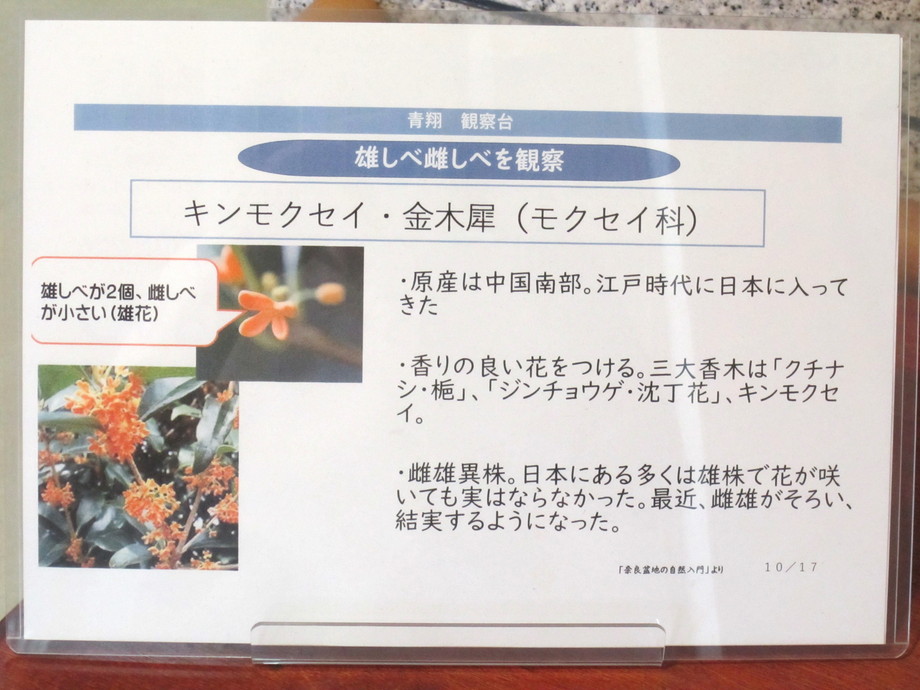
トクサ・砥草(トクサ科) 10月16日

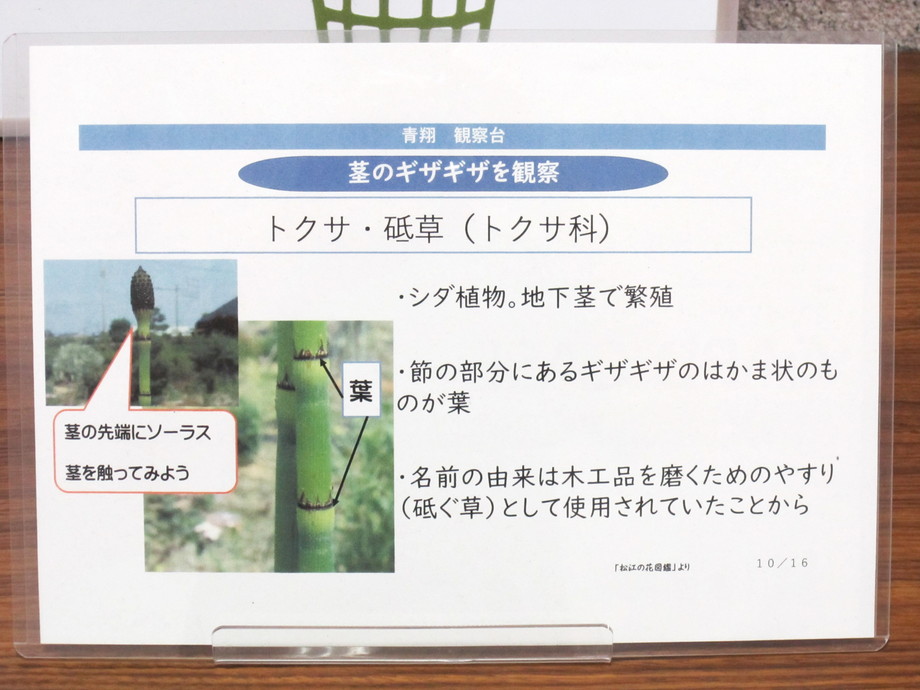
シロバナダングサ・白花栴檀草(キク科) 10月8日


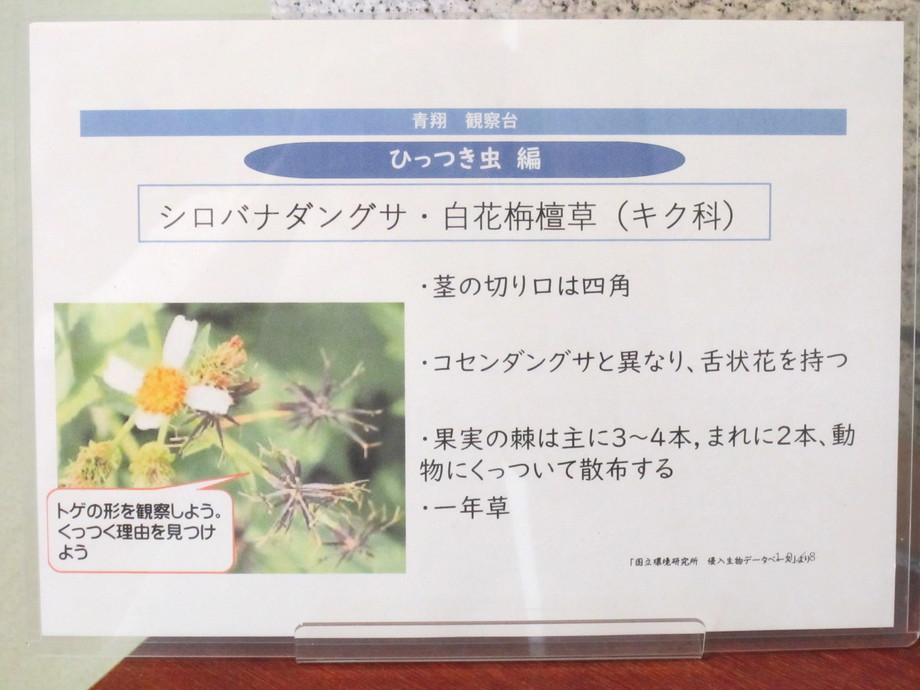
ナデシコ・撫子(ナデシコ科) 10月7日

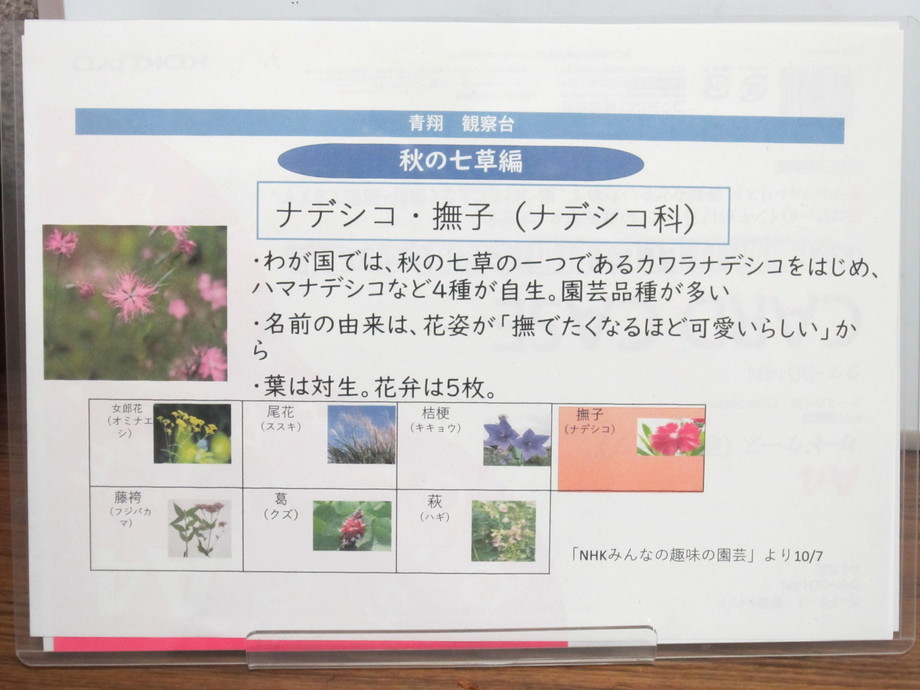
フジバカマ・藤袴(キク科) 9月30日

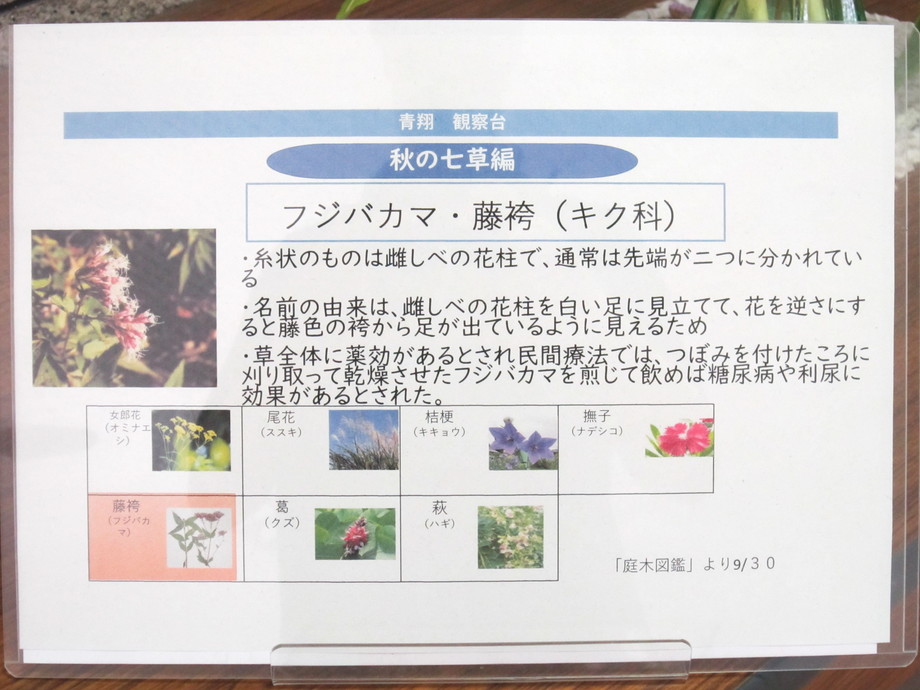
オオタニワタリ・大谷渡(チャセンシダ科) 9月30日

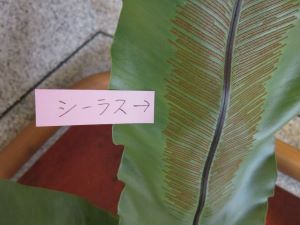
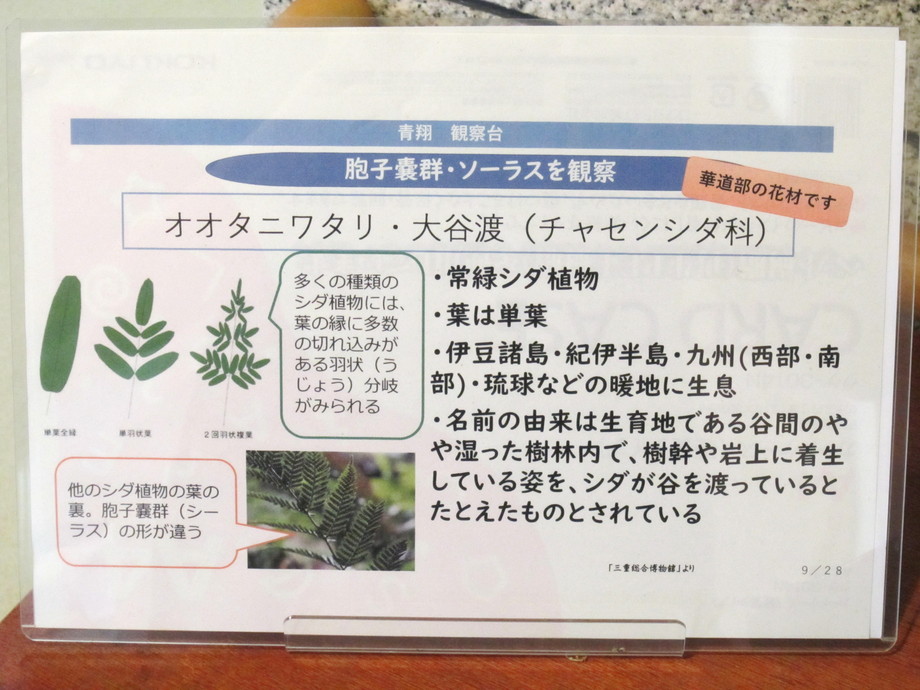
ミズヒキ・水引(タデ科) 9月25日


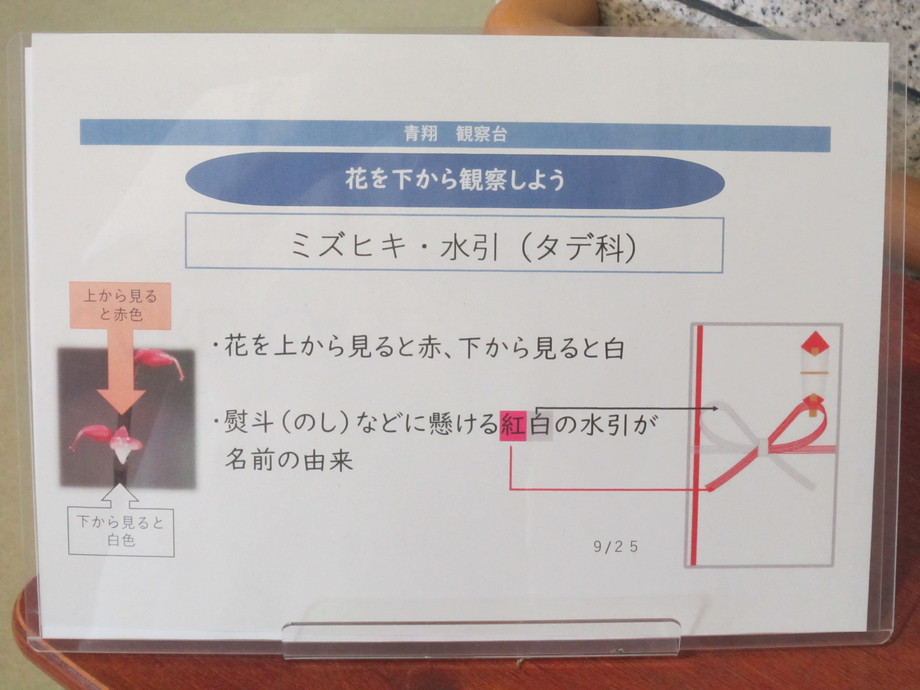
ツユクサ(ツユクサ科) 9月24日

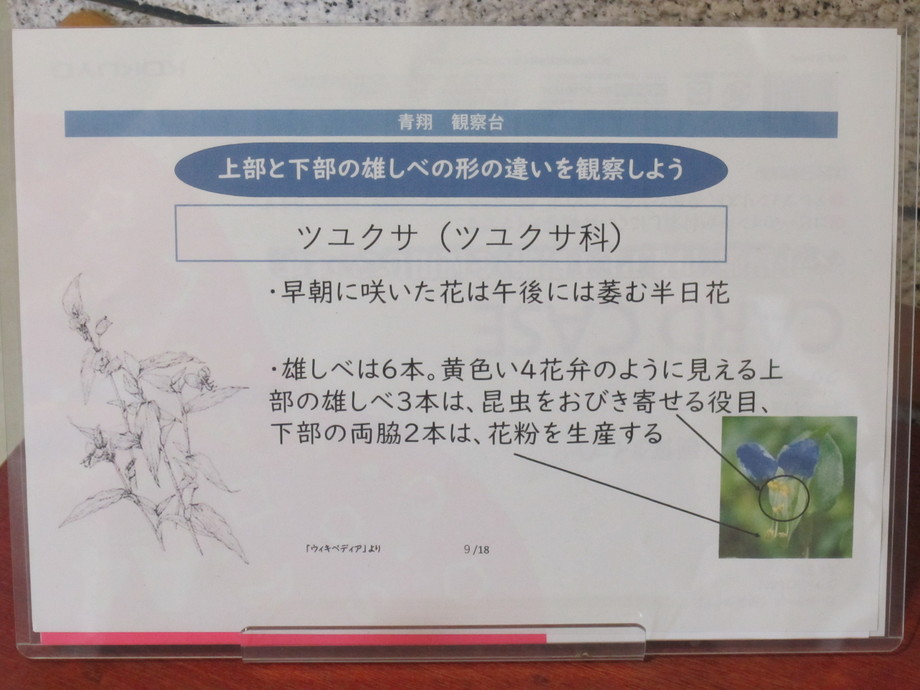
ハギ・萩(マメ科) 9月20日


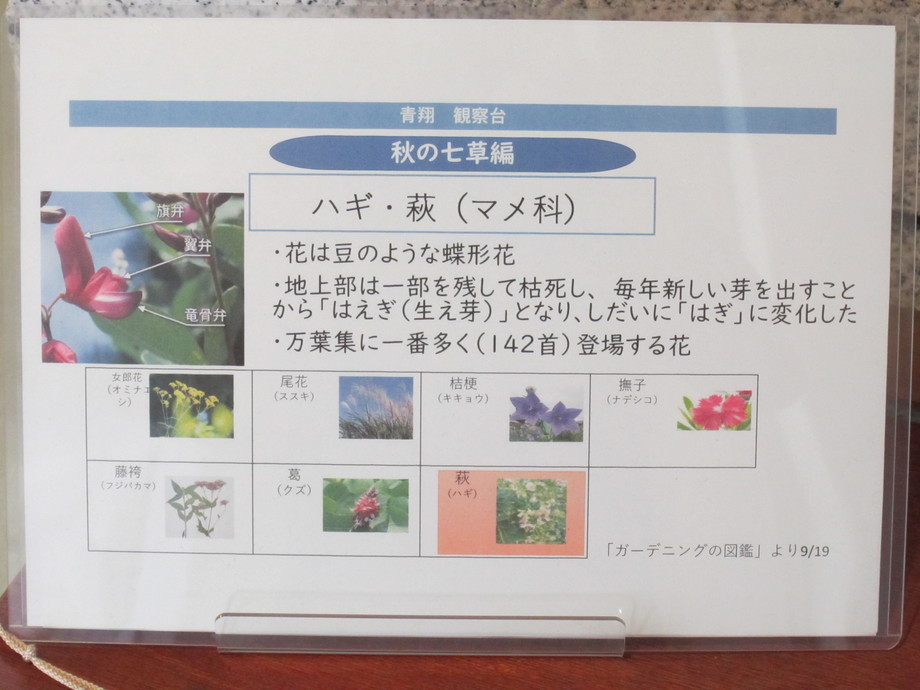
リンドウ・竜胆(リンドウ科) 9月14日

キキョウ・桔梗(キキョウ科) 9月14日


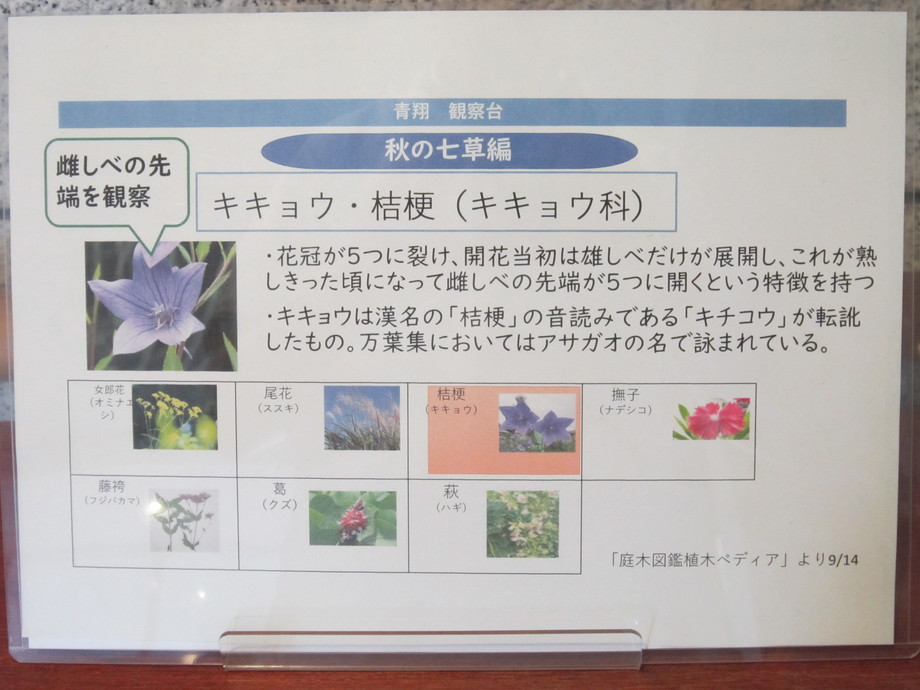
シモツケ・下野(バラ科) 9月12日

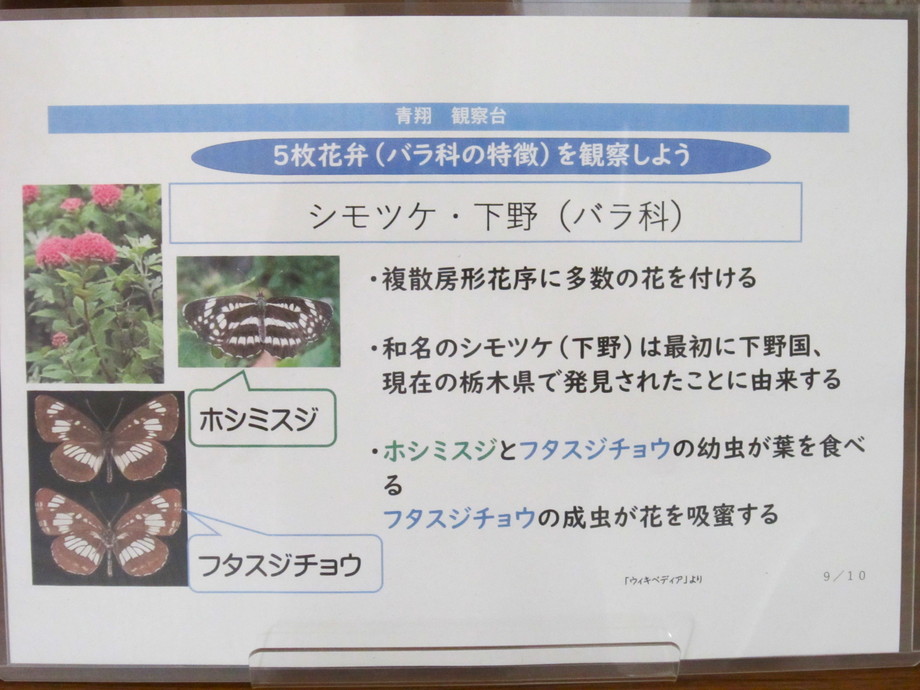
クズ・葛(マメ科) 9月10日

サルスベリ(ミソハギ科) 9月10日

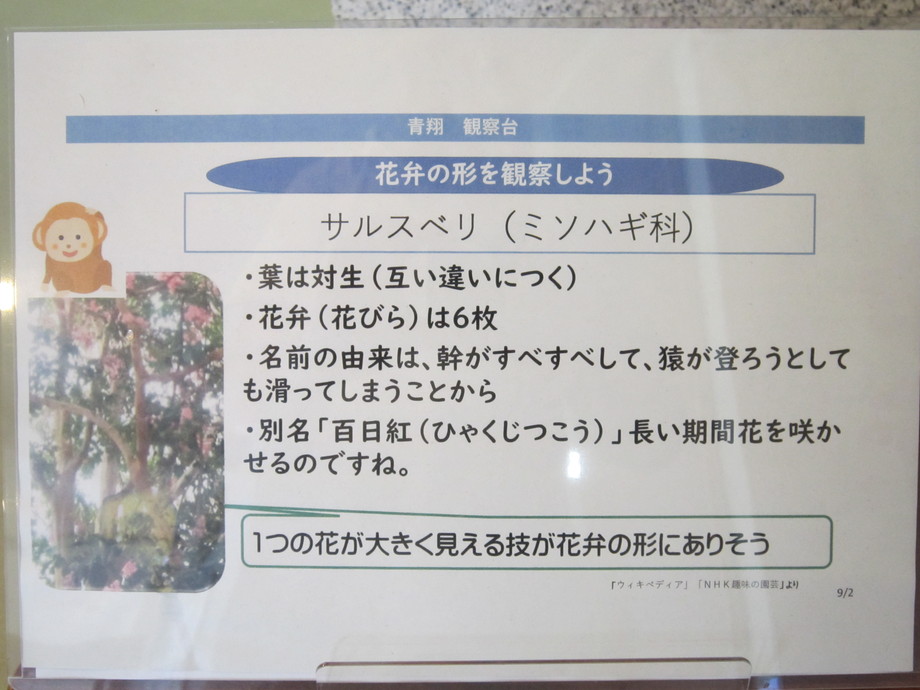
エノコログサ(イネ科) 9月6日

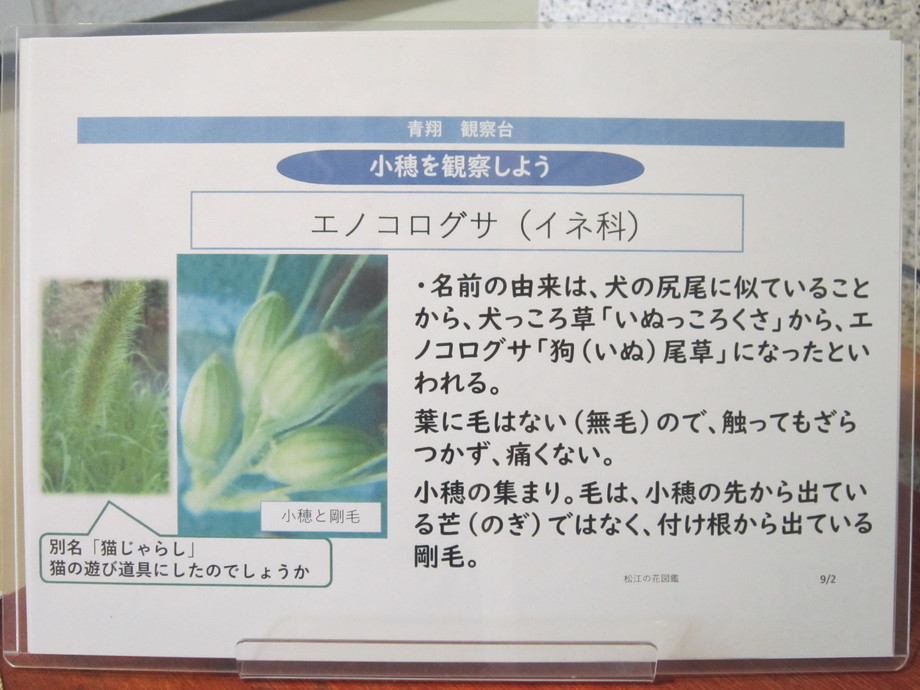
キボシアシナガバチと巣 7月3日
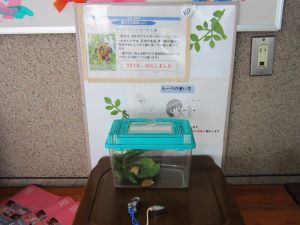
索引
日付順
2025年度
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
2024年度
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
7月
五十音順
ア行
アンスリウム・アンドレアナム(サトイモ科) 2024年10月30日
ウラジロチチコグサ・裏白父子草(キク科) 2025年6月7日
オオタニワタリ・大谷渡(チャセンシダ科) 2025年6月20日
オオタニワタリ・大谷渡(チャセンシダ科) 2024年9月30日
カ行
サ行
シロバナセンダングサ・白花栴檀草(キク科) 2024年10月8日
セッカエニシダ・石化エニシダ(マメ科) 2025年2月18日
ソシンロウバイ・素心蝋梅(ロウバイ科) 2025年1月17日
タ行
タンチョウアリウム・丹頂アリウム(ヒガンバナ科) 2025年6月30日
ツルニチニチソウ・蔓日々草(キョウチクトウ科) 2024年12月6日
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行